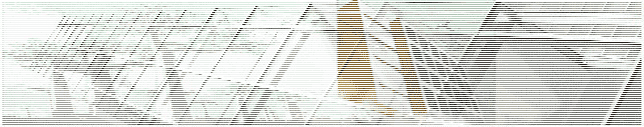| 開会日 |
プロジェクト名 |
発表者/発表題目(敬称略) |
研究報告 |
| 2010年4月24日(土) |
「契丹語・契丹文字研究の新展開」 第1回研究会 |
内容:
1. 松川節(AA研共同研究員、大谷大学)
「このプロジェクトが目指すもの」
2. 武内康則(AA研共同研究員、京都大学大学院生)
「インディアナ大学滞在報告」
|
 |
| 2010年4月29日(木)、2010年4月30日(金) |
「人類社会の進化史的基盤研究(2)」 第1回研究会
|
内容:
1. 春日直樹(AA研共同研究員、一橋大)
「存在論的人類学へ向けて:ミニブタとヒトをめぐる部分的連接」
2. 星泉(AA研所員)
「ルールは誰が決めている?---社会脳とことば」
3. 山越言(AA研共同研究員、京都大)
「チンパンジーの社会組織に関する地域差とその要因」
|
 |
| 2010年5月8日(土) |
「タイ文化圏における山地民の歴史的研究」 第1回研究会
|
内容:
1. 共同研究員全員
「『叢書:知られざるアジアの言語文化』について」
2. クリスチャン・ダニエルス(AA研所員)
「成果論文集の叩き台:James C. Scott The Art of Not being Governed: an anarchist history of upland Southeast Asiaが提示する見方」
3. 川野明正(明治大学)
「中国西南地方の蠱毒と呪術伝承」
|
 |
| 2010年5月9日(日) |
「東・東南アジアにおける地域間越境移住の人類学―結婚(離婚)移住
ネットワークにみる文化・エスニシティとアイデンティティー」 第1回研究会
|
内容:
1. 石井香世子(AA研共同研究員、名古屋商科大学)
「趣旨説明・全体の流れの確認」
2. 全体ディスカッション
「今後の研究の方向性とフィールド調査の実施方法に関して」
|
 |
| 2010年5月15日(土) |
「ダイクシス表現の多様性に関する研究」 第1回研究会
|
内容:
1. 西村義樹(AA研共同研究員、東京大学)
「ダイクシスと主観性」
|
|
| 2010年5月16日(日) |
「アジア・アフリカ地域におけるグローバル化の多元性に関する人類学的研究」 第1回研究会
|
内容:
1. 錦田愛子(AA研所員)
「パレスチナ・ディアスポラ―移動のグローバル化とナショナル・アイデンティティ―」
2. 富沢寿勇(AA研共同研究員、静岡県立大学)
「グローバル化のなかのマレー・ディアスポラ運動」
|
|
2010年5月22日(土)
2010年5月23日(日) |
「節連結に関する通言語的研究」 第1回研究会
|
内容:
2010年5月22日(土)13:00〜18:00
1. 渡辺己(AA研所員)
「本プロジェクト趣旨説明・活動方法等について」
2. 風間伸次郎(AA研共同研究員、東京外国語大学)
「準動詞と節の独立性について」
3. 加藤重広(AA研共同研究員、北海道大学)
「日本語における節の扱いの類型」
2010年5月23日(日)10:00〜13:00
「事例報告・問題提起」
1. 澤田英夫(AA研所員)
「ロンウォー語(ビルマ北部カチン州,チベット=ビルマ系)の節の概観」
2. 河内一博(AA研共同研究員、防衛大学校)
「Sidaama語(エチオピア,クシ語族)の節の連結パターンの概観」
3. 沈力(AA研共同研究員、同志社大学)
「中国語の複文について ―節連結の機能をめぐって―」
4. 塚本秀樹(AA研共同研究員、愛媛大学)
「日本語と朝鮮語における動詞・形容詞述語節と名詞述語節 ―対照言語学からのアプローチ―」
全員「総括・今後の計画」
2010年5月23日(日)14:30〜16:00
「研究発表」(AA研フォーラム/LingDyフォーラム共催、一般公開)
1. Andrej Malchukov (Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology/国立国語研究所)
"Constraining typology of nominalizations"
|
|
| 2010年5月29日(土) |
「北方諸言語の類型論的比較研究」 第1回研究会
|
内容:
1. 呉人徳司(AA研所員)
「趣旨説明」
2. Andrej Malchukov(AA研共同研究員、国立国語研究所客員教授)
“Transitivity parameters and transitivity alternations”
3. 江畑冬生(AA研共同研究員、日本学術振興会特別研究員)
「サハ語のヴォイスを表す接辞と動詞の意味」
4. 佐々木冠(AA研共同研究員、札幌学院大学)
“Non-universality of reflexive analysis for anticausativization: Evidence from the Hokkaido dialect of Japanese”
5. 呉人恵(AA研共同研究員、富山大学)
「コリャーク語の属性叙述−逆受動化と主題化を中心に−」
|
|
| 2010年6月5日(土) |
「インドネシア諸語の記述的研究:その多様性と類似点」 第1回研究会
|
内容:
1. 塩原朝子(AA研所員)「趣旨説明」
2. 野瀬昌彦(AA研共同研究員、麗澤大学)「なぜフィン=ウゴル語からパプアニューギニアに研究を変更したのか」
3. 稲垣和也(AA研共同研究員、大阪大学)「バリト諸語研究について」
4. 三宅良美(AA研共同研究員、秋田大学)「ジャワ語研究について」(仮題)
5. 菊澤律子(AA研共同研究員、国立民族学博物館)「インドネシアの諸言語の文型形成の歴史をひも解く」(仮題)
6. 北野浩章(AA研共同研究員、愛知教育大学)「カパンパンガン語の限定詞」
7. 内海敦子(AA研共同研究員、明星大学)「タラウド語のconveyance voiceの意味と用法」
8. 西山國雄(AA研共同研究員、茨城大学)"Conjunctive agreement in Lamaholot"
9. 降幡正志(AA研共同研究員、東京外国語大学)「未定」
10. 山口真佐夫(AA研共同研究員、摂南大学)「南スラウェシの言語研究」(仮題)
11. Sri Budi Lestari (AA研共同研究員、東京外国語大学博士後期課程)「ジャワ語の受動を表す諸形式」
12. 全員「今後のテーマについて」
|
|