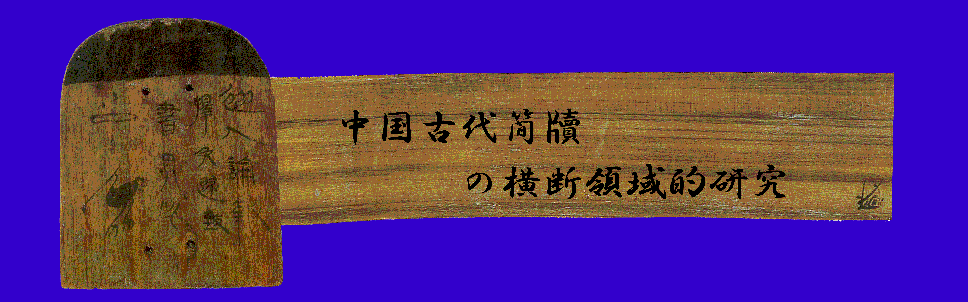恆署に關する覺書き
青木俊介(学習院大学)
里耶秦簡9-671は黑く塗られた上部や形状的特徴から楬の斷片と考えられる。そこには、
■廿九年□[1]
■及諸獄恆署
という記載が見える。
このなかの「恆署」について、『里耶秦簡牘校釋』は「詳情待考」としながらも、嶽麓秦簡「秦律令(貳)」108簡の「恆署書皆以郵行」という規定に依據して、「一種需要緊急傳送的文書」と注釋している[2]。しかし、この見解には二つの疑問が殘る。
一つ目は、「需要緊急」という點である。「恆」は本來、『説文解字』二部に「常也」とあるように恆常的という意味であり、文書中でも「恆會某月某日」という形で定期報告の期日を表す際に使用されるなど、「緊急」とは眞逆の意味を持つ。
確かに、「書當以郵行」は「以疾走」(嶽麓秦簡「秦律令(伍)」109簡)とあるように、速達郵便ではある。かといって、その文書すべてが緊急を要する内容とは限らない。例えば、張家山漢簡「二年律令」行書律276簡では、「獄辟書」や「郡縣官相付受財物當校計者書」が「以郵行」の對象とされている[3]。獄事の決裁や校計が早く終わるに越したことはないが、その内容自體は必ずしも緊急とはいえまい。
嶽麓秦簡「秦律令(參)」214簡に、「郵書過縣廷、縣廷各課其畍(界)中」とあるように、郵書は縣廷を通過するごとにチェック(「課」)を受けた。いわば、書留の機能を有していたといえる。この機能に基づいて、紛失の許されない特に重要文書が郵によって遞傳されたのであり、その内容は急を要するものばかりではないのである。
疑問の二つ目は、『校釋』が「恆署」を文書と見なしている點である。そもそも『校釋』が據りどころとしている「秦律令(貳)」108簡の記載は「恆署書」である。「書」は文書の意に違いないが、それならばむしろ、「恆署」は文書でないことになろう。
「恆署書」は9-1600にも、
恆署書二封〼
卅四年三月〼
という形で見える。「某書若干封」とは、郵書遞傳の記録に頻見する文言であり、里耶秦簡には以下のような事例が存在する。
獄東曹書一封。丞印。詣無陽。●九月己亥水下三刻、走佁以來。(5-22)
獄南曹書三封。丞印。二詣酉陽、一零陽。/卅年九月丙子旦食時、隸臣羅以來。(8-1886)
尉曹書三封。令印。 廿(二十)八年九月庚子水下二刻、走祿以來。
其一詣銷、
一丹陽、
一競(?)陵。(8-453)
戸曹書四封。遷陵印。一咸陽、一高陵、一陰密、一競陵。
廿(二十)七年五月戊辰水下五刻、走荼以來。(8-1533)
司空曹書一封。丞印。詣零陽。 七月壬申□□〼(8-375)
金布書一封。丞印。詣洞庭泰守府。(9-1593)
令曹書一封。丞印。詣酉陽。 十一月丙辰水下七刻守〼(9-593)
吏曹書二封。丞〼(9-905)
これらの事例によれば、「某書若干封」の「某」が示すのは部署名ということになる。さらに、いずれも令・丞の印で封じられていることから、遷陵縣廷内の諸曹であったことがわかる。このことに鑑みれば、まず、「恆署書二封」の「恆署」は文書ではなく部署ということになる。さらに踏み込めば、縣廷内の諸曹に相當するものと推測される。
次いで、「恆署」の記載を持つ二つの文書をあげる。
制書曰、擧事可爲恆程者、上丞相。上洞庭絡帬(裙)直。有書。釦(?)手。
卅二年二月丁未朔辛亥、御史丞去疾、丞相令曰、擧事可爲恆
程者。上帬直。即律(?)令弗𤻮(應)、謹案致□。
【□□】丞相□下【洞】庭守。/□手。
三月丁丑朔壬辰、【洞】庭叚守□□□□□□□□【如律】(8-159正)
令。臨沅下𡩡(索)。門淺・上衍・零陽、各以道次傳。別書□□□□。
書到相報、不報追。𡩡(?)・門淺・上衍・零陽言書到、署□□發。
□□□。道一書。以洞庭發弩印行事。●遷陵報酉陽、署令發。 恆署。
鬲〔酉〕陽報充、署令發。/四月【癸】丑、水十一刻刻下五、都【郵人】□以來。/□=【發】[4]。(8-159背)
六月壬午朔戊戌、洞庭叚守齮下□。聽書從事。臨沅
下𡩡(索)。門淺・零陽・上衍各以道次傳。別書、臨
沅下洞庭都水、蓬下鐵官。
皆以郵行。書到相報、不報、追。臨沅・門淺・零陽・
上衍皆言書到、署兵曹發。/如手。道一書。●以洞庭侯印〼(9-713正)
〼 遷陵報酉陽、署主令發〼
充報零陽、金布發。 恆署。 丁 四。
酉陽報充、署令發。
七月己未、水十一刻刻下十。都郵人鬾以來。/□發。(9-713背)
9-713は主たる要件が不明だが、どちらも洞庭郡が文書を屬縣に下し、その文書を「以道次傳」、いわば所定のルートに沿ったリレー形式での送達を命じている點が共通している。
また、「書到相報」というように、各傳送區閒で文書の受信を報告するよう義務づけている。文書中にいくつか見える「署某發」という記述は、受信報告「報」の封檢に記すべき開封者=宛先を指定したもので、「秦律令(壹)」281簡の「諸書求報者、皆告、令署某曹發」という規定に則したものである[5]。「恆署」は、宛先指定文言が列記された附近の空いた部分に、文面からやや閒を置く形で書かれているのだが、これらの宛先が恆署であることを示しているのではないか。
それから、先ほど觸れた「秦律令(貳)」109簡には以下のようにある。
●令曰、書當以郵行、爲檢令高可以旁見印章、堅約之書檢上。應署令并負以疾走。不從令、貲一甲…〈略〉…
郵で送るべき文書については、封檢の位置を高くして印章(の押された封泥)が見えるようにし、封泥をしっかりと封檢に縛りつける。そして、「應署」が命じて走っていかせるよう定められている[6]。「恆署書」も郵で送るべき文書なので、これが適用されるはずである。
要求に對應する文書を「應書」と呼ぶ[7]ことを踏まえると、「應署」とは「對應部署」の意であろう。前掲郵書遞傳記録に見える「某曹書若干封。令/丞印」という記載は、令もしくは丞の印で封印されているものの、直接的には擔當の曹=應署が發信したことを表しているのであろう。
かつて筆者が論じたように、秦の行政業務は必ず擔當者を置いたうえで執行されていた。そのため、同一案件に關する文書は同一の擔當者(擔當部署)が開封・發信ともに擔う[8]。したがって、8-159や9-713において「恆署」とされている「兵曹」「令」「主令」「金布」などは、「報」の開封者であるとともに、この案件に關する文書の發信擔當者でもあり、應署ということになる。これに「恆」の字義を加味すると、「恆署」とは「恆なる應署」、すなわち「恆常的な對應部署」の謂いなのではなかろうか。
ところで、9-713などは同内容の文書であるにも關わらず、開封者=對應部署が各機關で異なっている。これは、對應部署の決定が各機關の裁量に委ねられていたからであろう。ということは、對應部署を事前に通知されない限り、外部の機關から連絡を取ろうにも、どの部署を宛先とすればよいのかわからないことになる。
それから、前掲の郵書遞傳記録から、遷陵縣では縣廷内の諸曹が恆署にあてられていたとおぼしいことはすでに述べた。9-713の「兵曹」「金布」も郡縣の諸曹であるし[9]、「主令」は「令曹」と互換の利く語である[10]。「令」は縣令のことかもしれないが、遷陵から酉陽への宛先が8-159では「令」、9-713では「主令」となっているので、兩者は同一の可能性がある。『宋書』百官志下に、「諸郡各有舊俗、諸曹名號、往往不同」とあるように、諸曹の名稱は後世に至っても各所で異なっていた。外部機關からすればどこへ宛てればよいのか、なおさら不明瞭なわけである。
そこで、ある條件下の文書については恆常的に對應する部署を「恆署」としてあらかじめ定めておき、「恆署書」とさえ明示しておけばどの部署が對應すべき文書なのかが自明となるようにして、以後の連絡を圓滑ならしめたと考えられる[11]。
では、その「條件」とは何か。郵書遞傳の記録と見られる9-2345正には、「恆書三封」という記述が確認されるが、前掲9-1600「恆署書二封」に照らせば、「恆書」は「恆署書」の略語と思われる。この「恆書」は、睡虎地秦簡「封診式」46~49簡のなかにも見える。
䙴(遷)子 爰書。某里士五(伍)甲告曰、謁鋈親子同里士五(伍)丙足、䙴(遷)蜀邊縣、令終身毋得去䙴(遷)所、敢告。告法(廢)丘主。士五(伍)咸陽才(在)某里曰丙、坐父甲謁鋈其足、䙴(遷)蜀邊縣、令終身毋得去䙴(遷)所論之、䙴(遷)丙如甲告、以律包。今鋈丙足、令吏徒將傳及恆書一封詣令史、可受代吏徒。以縣次傳詣成都、成都上恆書太守處、以律食。法(廢)丘已傳、爲報。敢告主。
ここで注目したいのは、「恆書」が「以縣次傳」の形式で傳送され、傳送後には「報」を要求している點である。前述したとおり、これは8-159・9-713とも共通する。
このことに基づけば「恆署」とは、「以道次傳」の形式で傳送され、「報」を義務づけられた文書、およびその報の恆常的な擔當者として指定された部署と解することができる。
附記:小文は、アジア・アフリカ言語文化硏究所共同利用・共同硏究課題「秦代地方県庁の日常に肉薄する――中国古代簡牘の横断領域的研究(4)」における議論を踏まえているほか、日本學術振興會科學研究費補助金・基盤研究(C)研究課題17K03126「中國古代における家族と「移動」の多角的研究―靜態的家族觀からの脱却をめざして―」(研究代表者・鈴木直美)の硏究成果を含む。
編集者注記:2020年12月5日入稿
注
[1] この未釋字部分について、湖南省文物考古研究所編『里耶秦簡(貳)』(文物出版社、2018年)、陳偉主編『里耶秦簡牘校釋』第2卷(武漢大學出版社、2018年)ともに「□月」の2字と解している。本簡は右側が缺損していて、「月」については1畫目とおぼしき縱の筆畫が見えるのみである。「□」に至っては何も見えないのだが、後を「月」と釋したために數字が入るとして補ったのであろう。しかし、前にある「年」の縱にのびる筆畫と全体の字配りを考慮すると、「年」と「月」の閒に文字の入るスペースはない。加えて、同樣の楬の記載は、「某年某署某文書」あるいは「某年某月盡某月某署某文書」というのが常である。よって「月」ではなく、ここには部署を表す文字が入ると考えられる。殘畫からすれば、「戸」などが該當する。
[2] 前掲注1陳偉主編書175頁、9-671注1。
[3] 諸獄辟書五百里以上、及郡縣官相付受財物當校計者書、皆以郵行。
[4] 本簡の釋讀については、廣瀨薰雄「也談里耶秦簡《御史問直絡裙程書》」(同氏著『簡帛研究論集』、上海古籍出版者、2019年)に從う。
[5] 拙稿「里耶秦簡の公文書における「某主」について―嶽麓秦簡・興律の規定を手がかりに―」(髙村武幸・廣瀨薰雄・渡邉英幸編『周縁領域からみた秦漢帝國2』、六一書房、2019年)。
[6] 陳松長主編『嶽麓書院藏秦簡(伍)』(上海辭書出版社、2017年)では當該部分を、「堅約之、書檢上應署、令并負以疾走」と區切っている。おそらく、「封檢に應署を記す」と解釋しているのであろうが、それならば、「書應署檢上」となるのが自然であろう。このことを踏まえて本稿では、「堅く之れ(=印章)を書の檢上に約す。應署、令して并せて負い以て疾走せしむ」と訓讀した。
[7] 例えば居延漢簡35.8Aは、
陽朔三年九月癸亥朔壬午、甲渠鄣守候塞尉順敢言之。府書
移賦錢出入簿、與計偕。謹移應書一編敢言之。(居延漢簡35.8A)
という内容の文書である。この場合、(都尉)府の要求に照らせば、甲渠鄣守候が提出すべきは「賦錢出入簿」以外にあり得ない。要求に對應する文書という意味で、「賦錢出入簿」を「應書」と呼んでいることは明白である。また、陶安あんど「「應書」に關する覺書」(東京外國語大學アジア・アフリカ言語文化研究所「中國古代簡牘の橫斷領域的研究」HP、http://www.aa.tufs.ac.jp/users/Ejina/note/note21(Hafner).html、2016年12月6日入稿、2020年12月5日最終閲覽)においても同樣のことが指摘されている。
[8] 前掲注5拙稿。
[9] 9-0741+9-0120に「廷金布曹」とあることから、金布も縣廷内諸曹の一種であることがわかる。
[10] 前掲注5拙稿。
[11] 「報」の開封者は各縣がそれぞれ指定するため、8-159と9-713の「恆署」の記述は、發信元である洞庭郡によるものとは考えにくい。傳送されるにつれて各縣で順次指定がなされてゆき、おそらくは最終的に文書を受け取った遷陵縣廷が、これらの指定開封者が各縣の恆署である旨、注記したのであろう。