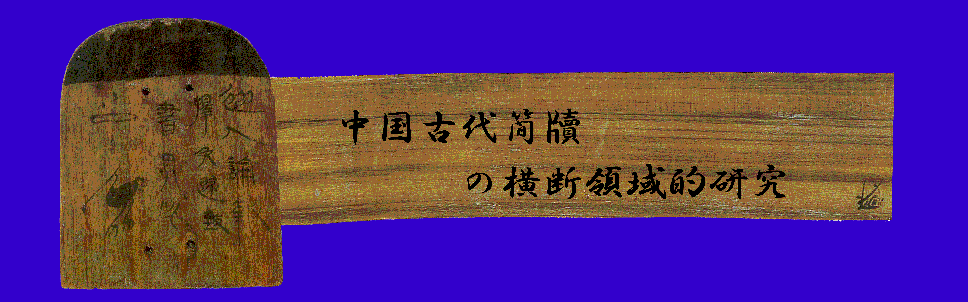徭役を負担する戸の集計
―走馬楼呉簡家族名簿の「定領役民」と「定應役民」は同じか異なるか―
鷲尾祐子(立命館大学)
はじめに―徴発対象となる戸を集計する簡
1996年湖南省長沙走馬楼の平和堂ビル工事現場より、十万枚を越える三国時代・呉の簡牘が出土した(「走馬楼呉簡」と称される)。これらの多くは初代皇帝・孫権が即位して間もない頃に作成されたものであり、当時長沙を管轄していた臨湘侯国の公文書である。出土地一帯は戦国時代以降ずっと地方行政の中心地であったところだが、呉簡の出土後前漢・後漢の公文書簡牘が陸続と出土した。近隣で出土した簡牘は前漢・後漢・三国時代の三代にわたるのであり、すべて発表されれば、長期的なスパンで地域の統治実態の変化を考える上で、貴重な資料となるものと考えられる。
「走馬楼呉簡」の大半は簿籍であり、地域住民の家族名簿を大量に含む。これらの名簿は当地に生きる人々のうち戸籍に登記されている民の記録であり、所属する戸・里を単位として名簿に記載されている。これらは当時の家族の姿を知る上で貴重な資料である。しかしそれを家族の研究に用いるに際して、二つの困難が存在する。一つは、編綴が切れた状態で出土したため、ばらばらになっているものが多く、簿の全体的な構成や、各戸の状況を把握するためには集成が必要であることである。幸い、簡冊の形を維持したまま出土している簿も存在し、これらは比較的検討が容易である。このような簿を中心に、集成や戸の復原の研究が行われている。
第二の困難は、家族名簿に見える書式が複数存在することにある。多くの家族名簿に書かれていることは、だいたい同じような内容であるが、書式は多様である。簡冊の形状を保持して出土しているため同一簿であることが明らかな諸簡ですら、複数の書式を含むことがある。書式の相違は何故なのか、編製意図や機関を異にするから違うのか、それとも単なるバリエーションなのかは、家族名簿とは何か(それは戸籍なのか否かの問題を含めて)を検討する上でも重大な問題であった。
このような困難を抱えつつ、これらの名簿をどの機関が何のために編製したのかということに関する検討が行われてきた。その「何のために」を知る最も有力な手がかりとされてきたのは、簿の集計の部分である。
現状では、最も基層の行政単位である里の集計に次のような項目を有する簿は、同じ種類のものとして認識されている。まず、里の総口数を集計する項目である。嘉禾六年編製の家族名簿に含まれる夫秋里の例(鷲尾祐子2020にて《簿二》として検討した。以下集計aと略称)を挙げる。
| a | |
| 集凡夫秋里魁呉明領吏民五十戸口食三百十九人 | (柒5021/示意図42)【a戸口数】 |
| 其二人前後被病物故 | (柒5000/示意図42)【a死者数】 |
| 一百八十七人男 | |
| 定領見人三百一十七人 其 | |
| 一百卅人女 | (柒4998/示意図42)【a人口確定】【a男】【a女】 |
【a戸口数】は夫秋里の戸口数の集計である。里魁(里の責任者)は呉明であり、戸数は50戸、口数は319人である。【a死者数】は物故者の数であり、【a人口確定】は【a戸口数】から【a死者数】を引いた数であり、それによって317人という口数が得られる。その下に、男女別の口数が附記される。まとめると、この里集計の各項目の配列は、里の戸口数を記載し(【戸口数】)次いで死者の数を記し(【死者数】)、次いで【戸口数】の口数から【死者数】を除して確定した人口を記し(【人口確定】)、それに【男】口数と【女】口数を附記するものとなっている。
定とは、侯旭東2013が指摘するように、計算をチェックしたのち確定した数字を指す。ある項目につき確定した数を計上することが帳簿を作成する目的であるため、「定」が付される集計は、簿中で最も重要な集計であり、その簿の編製目的を表す重要なてがかりとなる。ゆえに、この簿の編製目的の一つは、一里の口数を確定することにあると考えられる。
前掲【a人口確定】以外にも、「定」が見える項目が存在する。それは、徭役に徴発される戸の数を確定する集計である。その例として、嘉禾六年に編製された小武陵郷簿・南郷簿にみえる小武陵郷平陽里の集計を、まず挙げる(竹簡[参]所収。示意図2。竹簡[参]の部分については凌文超2011が集成する。編製年次・簿の構成については鷲尾祐子2020参照。集計bとする)。
| b | |
| 其一百卅八人男 | (参4315)【b男】 |
| 其八十一人女 | (参4311)【b女】 |
| 其一戸給軍吏 下品 | (参4303)【b吏】 |
| 其五戸□□民 [下]品 | (参4302)【b民】 |
| 其七戸□□女戸不任調 下品之下 | (参4301)【b不任戸】 |
| 定領役民卅七戸 | (参4300)【b役民確定】 |
前掲の集計aのように、【b男】の前にこの里の人口を集計した簡が存在するはずだが、該当簡が見つからず確認できない。男性口数(【b男】)・女性口数(【b女】)の集計は残っている。それに続く部分は、集計aには見えない部分である。まず軍吏の集計(【b吏】)、すでに特定の役務についている戸(【b民】、二字不明だが、「民」と見えるため吏卒ではなく徭役に徴発されている民であると類推される。鷲尾祐子2012参照)、女戸などの理由で徴発に耐えない戸の集計が続き(【b不任戸】)、最後に「定領役民」(【b役民確定】鷲尾祐子2012、鷲尾祐子2020)の集計が見える(以上里集計の簡における各集計項目の配列については鷲尾祐子2012にて述べた)。集計bの【b吏】以下は集計aに後続する部分と考えられる。そして集計bによれば、集計aに続く里集計の項目の配列は、まず吏の戸の集計があり(【吏】)、次いですでに役務についている戸の集計が置かれ(【民】)、そのあとに徴発に耐えない戸が数え上げられ(【不任戸】)、最後に「領」(主管)している役民の数を確定する集計項目が置かれる【役民確定】。この「定」が冒頭にみえる役民の集計項目【役民確定】は、集計aの口数を確定する集計項目と並んで重要な集計項目であると考えられる。
吏民簿の多くは、このような二つの「定」集計項目を有する簿である。一つは、死者の数を除して里の現有総口数を確定する集計である(【人口確定】)。もうひとつは、すでに官の仕事に就いている者や徴発に耐えない者を総戸数より除して、徭役に徴発される対象となる戸の数を確定する集計(【役民確定】)である。この二つの集計は、家族名簿を編製する目的を表していると考えられる。そしてこのような集計を有する簿は、戸人簡や成員簡の書式が多少相違していても、同じ目的を有する同類の簿として認識されている(鷲尾祐子2012、侯旭東2013、張栄強2014)。
徭役に徴発される対象となる戸の数を確定する集計(【役民確定】)について、前掲集計bでは「定領役民×戸」と記載され、「役民」がここで数えられている戸を指すと考えられるが、ほかに同類の集計にみえる類似の文言に、「應役民」「事役民」という記載がある。これらの記載について、李均明2008aは、役民・應役民・事役民などは同じであるとし、徭役に服する条件に合致しており役に服している民戸を指すとする。なお、李は後に所説を変更し、徭役に服する条件に合致しているか、あるいはいま徭役に服している民であるとしているが、これらが指す対象が相違するとはしない(李均明2008b)。これに対し、荘小霞2017は、役民・應役民・事役民を相違するものとする。
荘は、これらは呉簡では明確に区別されているとする。しかしどのように区別されているのかについては説明されていないため、表現の相違を以て区別していることの表れと捉えているようである。同時に、典籍において役民は正常に服役すべき百姓を指し、事役は普通一般の労役と同じものを指すことを指摘している。とすれば、荘の紹介する典籍の用例によれば、役民と事役民は同じ対象を指すとも解し得、それらが全く異なるとは必ずしも言えない。
つまるところ、これら「定領役民(確定した(里魁が)主管する役民)」と「定應役民(確定した應役民)」などの集計項目が集計する対象は、李の前説のごとく同一であり、「役民」と「應役民」は同じ対象を指すと考えられる。その理由を、里の集計において各集計項目が配列される中で、これらの集計項目がいかなる位置に置かれるかを検討することにより説明する。
このため、集計aと同じ機会に編製された《二類》の簿の里集計(集計c、集計d)、「竹簡貳」「廣成郷六年簿」の廣成里の集計(集計e)、「竹簡肆」の中郷簿に見える五唐里の簿の集計(集計f)を例として、検討する。もっとも、いったん簡をつづる紐が切れているため、里の集計簡がすべて揃っている事例はほとんど無い。以下の集計例は、dを除きすべて一部の簡が欠けている。
「定領役民」「定領事役民」「定應役民」「定領應役民」
「定領役民」の例については既に掲示した(【b役民確定】)が、次にこれと「定領事役民」「定應役民」「定領應役民」の簡が、同じ対象を集計しているか否かを検討する。各集計項目の配列中、これらが同じ位置にあることを確認する。
まず前掲a簿を含む《二類》に見える「定領事役民」の例を挙げる。集計aで挙げたのは夫秋里の集計であるが、次例は吉陽里であるから、区別するために集計cと略称する。すべて「竹簡柒」示意図42である。
| c:(簡番号/示意図内の番号) | |
| 右吉陽里魁番羊領吏民五十戸口食三百八十四人 | (柒5865/909)【c戸口数】 |
| 一百九十六人男 | |
| 定領見人三百七十六人 其 | |
| 一百八十人女 | (柒5889/933)【c人口確定】【c男】【c女】 |
| 其二戸私學 | (柒5888/932)【c私學】 |
| 其一戸四六佃吏 | (柒5887/931)【c吏】 |
| 其一戸新吏 | (柒5886/930)【c吏】 |
| 其二戸郡吏 | (柒5885/929)【c吏】 |
| 其十二戸尫羸窮老不任役 | (柒5884/928)【c不任戸】 |
| 定領事役民卅二人 | (柒5883/927)【c役民確定】 |
| 魁 潘 羊 主 | (柒5882/926)【c責任者】 |
「示意図42」より簡の出土位置を見ると、冒頭の【c戸口数】が一つずれた列にある以外は、すべて時計回りの方向に、間に他の簡を交えることなく一列に並んでおり(図1参照)、その位置に従って各集計項目の配列を復原すると、集計a・集計bにほぼ一致する。まず、【c戸口数】があり、次にあるはずの死者数の項目はこの近辺に残存しないが(ほとんど文字が見えない柒5881/925が其れである可能性もある)、【c人口確定】【c男】【c女】は存在する。次いで私學(民間の学生)の集計があり、続いて佃吏(耕作関連の吏と考えられる。李均明2008b参照)新吏・郡吏など【c吏】の集計が並び、次いで障碍疾病貧困老年などで徴発に堪えない人々の戸の集計が見える【c不任戸】。集計cは、前掲【戸口数】【人口確定】【男】【女】が存在する点で集計aと同じであり、【男】【女】【吏】【不任戸】が存在する点では集計bに同じである。以上、集計cの各簡の集計項目については、【死者数】が見あたらないほかは、集計aの記載事項と一致し、【私學】の項目以外は集計bと一致する。
.files/figure01.jpg) |
| 図1:示意図42中のc簿簡(▲が集計c諸簡。○は里名が明らかな簡) |
そして、次に問題の「定領事役民」の集計がくる。これは、集計bの最後にある【b役民確定】の集計項目と、各集計項目の配列上で同じ位置にある。そしてこの前の集計項目が集計bとほぼ合致していることから、「定領事役民」集計は「定領役民」集計に同じ役割を有していると考えられる(さらにその後に、この里の責任者である里魁の名前が記される【c責任者】)。
「定領事役民」の例をもう一つ挙げる。集計a・cと同様、鷲尾2020《二類》の簿の例である。集計a・cと区別するため、集計dとしておく。
| d | |
| 集凡常遷里魁黄春領吏民五十戸口食四百廿二人 | (柒5454/498)【d戸口数】[1] |
| 其十四人前後被病物故 | (柒5453/497)【d死者数】 |
| 二百六十二人男 | |
| 定領見人四百八人 其 | |
| 一百卌六人女 | (柒5452/496)【d人口確定】【d男】【d女】 |
| 其四戸郡縣吏 | (柒5451/495)【d吏】 |
| 其一戸縣卒 | (柒5450/494)【d卒】 |
| 其二戸私學帥客 | (柒5477/521)【d私學帥客】 |
| 其一戸劉口驛兵 | (柒5492/536)【d兵】 |
| 其五戸貧羸老頓不任[役] | (柒5491/535)【d不任戸】 |
| 定領事役民卅七戸 | (柒5513/557)【d役民確定】 |
| 魁 黄 春 主 | (柒5512/556)【d責任者】 |
示意図42によって出土時の各簡の位置を確認すると(図2参照)、孤立して出現しているものと、同じ位置に竝んで出現しているものがある。同じ位置にならぶものは、順列を考える手がかりになる。まず、5453から5450までは、時計回りに間に他の簡をまじえず並んでおり、簡冊のもとの状態を反映していると考えられる。次に5492と5491、5513と5512も同様に時計回りに並んでいて、この二組ももとの状態を保持しているであろう。さらにa・b・c簿の配列を参考にして、まとまりのある三組と孤立している二枚とを以上のように配列した。
.files/figure02.jpg) |
| 図2:示意図42中のd簿簡(▲が集計簡) |
次に集計項目の内容について紹介する。冒頭に、戸口総数【d戸口数】・死者数【d死者数】・【d戸口数】の口数から【d死者数】を引いた人口総数【d人口確定】の三者が並ぶところは、a簿に全く同じである。それに次いで郡県の官吏【d吏】・県の兵卒【d卒】の集計が見える。【d吏】は【b吏】軍吏の集計に類する。次いで私学帥客の集計【d私學帥客】が見える。吏民簿にみえる「客」には、国家の機関に使役される者と、私家に属して使役される者とがある。私家に属する客は私家の戸の一員として記載されるが、ここにみえる戸は、戸単位で国家に把握されているため、国家によって差配される者としての客であると考えられる。この「客」の戸は、すでに国家に使役されておりそのために徭役に徴発される対象とはならないのであり、この点において集計bの【b民】に類似する存在である。次に劉口驛兵【d兵】が見えるが、これは湘水と瀏水の合流地点にある瀏口戍(『水経注』三八。安部聡一郎2017によって教示を受けた。)に付設されている驛の兵であろう。次いで貧困や老年などの理由で徴発に堪えない戸の集計があり【d不任戸】、これは【b不任戸】に同じである。このように集計dは、いくつかの集計bに無い項目があるが、共通する項目も多く、これらは基本的に集計bと同じ書式を有すると考えられる。なお、里の戸数五十から【d吏】~【d不任戸】までの合計の数を引くと、【d役戸確定】の数に一致する。
そして、その次に、問題の「定領事役民」の集計がくる。これは、集計bにおいて【b役民確定】が【吏】【民】などの徴発されない存在の集計項目・徴発に耐えない戸の集計項目(【不任戸】)のうしろに配置されるのと同じように、【吏】【卒】【私學帥客】【兵】【不任戸】のあとに配置されている。そしてこの前の集計項目が集計bと同様、すでに官の仕事に従事している人々や徴発に堪えない人々のそれであることから、「定領事役民」集計は「定領役民」集計と同じ集計項目であると考えられる(さらにその後に、集計cに同じくこの里の責任者である里魁の名前が記される(【d責任者】)。
次いで、「定應役民」の集計項目について検討する。それは竹簡[貳]広成郷六年簿(侯旭東2009・2013、鷲尾祐子2010、關尾史郎2015にて集成と検討がなされている。)の廣成里集計にみえる(集計eと略称する)。
| e | |
| 右廣成里領[吏]民五十戸口食二百九[十]□[人] | (貳1671)【e戸口数】 |
| 其□人□□[被]病物故 | (貳1672)【e死者数】[2] |
| 其二戸給郡園父 | (貳1701)【e民】 |
| 其一戸給朝丞 | (貳1702)【e民】 |
| ●其五戸尪羸老頓貧窮女戸 | (貳1705)【e不任戸】 |
| ●定應役民廿戸 | (貳1704)【e役戸確定】 |
| ●魁(?) 蔡 喬 〔主〕 | (貳1700[3])【e責任者】 |
集計eの集計項目とその配列も、前掲の集計b・cと類似する。【口数確定】【男】【女】は残存していないが、【e戸口数】【e死者数】は見えており、【吏】【卒】は無いものの【e民】すでに特定の徭役についている民戸の集計(貳1672の給郡園父・貳1702の給朝丞)と、身体障碍や老齢・貧窮・女戸であるなどの理由から徴発に耐えない戸の集計(【e不任戸】)は同じように存在する。そして「定領役民」戸集計は存在しないが、b・c簿【役戸確定】と同じ簿の締めくくりの位置に、「定應役民」戸の集計が存在する。とすれば、b・c簿の【役戸確定】集計と同じ集計項目が「定應役民」集計であると考えられる。
また、集計eが含まれているのは「廣成郷六年簿」だが、この簿全体を通して、「定領役民」はみえず「定應役民」のみ見える。同一簿に二者が同時に見えるならば、双方の意義は相違していると判断すべきである。しかし一つしか見えないのであれば、「定應役民」と「定領役民」とは表現は異なっているものの同じ役割を負っていると判断し得る。
もう一つ例を挙げる。「竹簡肆」中郷簿(楊芬2011参照。鷲尾祐子2015・2017などで「竹簡肆」嘉禾五年・六年中郷吏民簿【吏民簿5】として紹介した。)である。同一里の簿に属することが確認可能な記載として、五唐里の集計を挙げる(集計fと略称。示意図2)。
| f | |
| ●集凡五唐里魁周□領吏民五十戸口食二百八十九人 | (肆380)【f戸口数】 |
| 其一百六十二人男 | (肆379)【f男】 |
| 其一百廿七人女 | (肆378)【f女】 |
| 其四戸縣吏 | (肆377)【f吏】 |
| 其二戸郡吏 | (肆376)【f吏】 |
| 其□戸州吏 | (肆374)【f吏】 |
| 其五戸給新吏 | (肆373)【f給吏】 |
| 其一戸縣卒 | (肆372)【f卒】 |
| 其―戸佃帥 | (肆371)【f民】 |
集計fの五唐里集計も、集計b・c・eに似ている。戸口数の次にあるべき死者数と確定口数は見えないが、男女口数が残存し、次いで吏、給吏、卒の集計が続く。
そして、五唐里のものであると確定し得る「定領役民」集計は見えない。一方、同じ機会に作成された簿にふくまれるこれに類する集計として、どの里のものであるかは不明だが、以下の三簡が存在する。
| 定領應役民卅戸 | (肆767/示意図4)[4] |
| 定領應役□□五戸 | (肆792/示意図4)[5] |
徴発対象戸数を特定する集計項目として「定領役民」が見えず、「定領應役民」のみ見えることから、この「定領應役民」こそが「定領役民」に相当するものであると考えられる。
繰り返しになるが、確認すると、里の集計として総戸口数、死亡者数に次いで口数を確定する項目が存在し、それに続いてすでに特定の役務に徴発されていたり官吏であったりする者を、種類別に集計した項目が存在するのが、これらの簿の共通点であり、このことはこれらが共通の目的によって編製されていることを反映している。そしてこのような集計の末尾に置かれる「定應役民」「定領役民」「定領應役民」の集計項目は、同一簿に重複して出現することはない。とすれば、表現が異なっていても、これらは同一の対象を集計する項目であり、すべて徴発対象戸を集計する簡である可能性が高い。
結―徴発対象戸集計簡のバリエーション
以上、「定領役民」「定領事役民」「定應役民」「定領應役民」などが、里の集計のなかで同じ役割を果たしており、徴発される対象となる戸の数を確定していると考えられることを、吏民簿に見えるさまざまな里の集計の例を挙げて論じた。
また、「應役民」と「役民」とは、語義から考えても同じ対象を指していると考えて差し支えない。應役民とは、「まさに役すべき民」であり、役に徴発すべき民である。役民とは徭役に徴発される対象となる民である(「凡そ貲有る者は、多ねこれ士人にして復除せらる。その貧極まれる者は、悉く皆な露戸の役民なり」大意:資産の有る者は士人として徭役を免除され、極貧の者が徭役の対象となる。『南斉書』四六、陸慧暁伝附顧憲之伝)。また、荘が述べるように、事役は一般の徭役を指し、事役民は徭役に徴発される対象となる民を指すとも解し得る。つまり、役民・應役民・事役民はすべて徴発対象となる民を示している。
また、書式や表現の相違を以て、その記載対象が相違していると判断し得るかといえば、呉簡においては必ずしもそうではない。呉簡の住民家族名簿においては、同類の簿の同じ事を記載している箇所であっても、書式の相違は存在する。たとえば、同類の簿と考えられる前掲の集計bと集計eがそれぞれ含まれる簿の間でも、戸人や戸成員を記載する書式は、非常に異なる。
| 集計bの簿: | |
| 平陽里戸人公乘黃風年六十八 | (参4271/示意図2)【b戸人】 |
| 妻大女□年七十七 子男客卅五 | (参4270/示意図2)【b成員】 |
| 客妻大女草年廿三 客子男□年四歳 | (参4269/示意図2)【b成員】 |
| 三人男 | |
| 右風家口食五人 其 | |
| 二人女 | (参4268/示意図2)【b戸集計】 |
| 集計eの簿: | |
| 縣卒區象年十八 象妻大女沾年廿一筭一 | (貳2119)【e戸人】 |
| 象小妻大女汝年廿 象父公乘專年七十六 | (貳2117)【e戸成員】 |
| 專妻大女□年六十 象女弟汝年十六筭一 | (貳1536)【e戸成員】 |
| ●右象家口食廿二人 | (貳1728/示意図)【e戸集計】 |
b・eの簿を比較すると、各戸の冒頭の戸人の簡について【b戸人】は戸人だけが一つの簡に記載されているのに対し、【e戸人】では戸人とその妻が同一簡に記載されており、また【e戸人】には筭(徭役・筭賦の負担者であることを示す)が記載されているが【b戸人】には無い。各戸の記録を締めくくる戸の集計簡についても、【b戸集計】には男女の口数が記載されているが【e戸集計】には無い。このように、同類の簿の間でも、書式には相違が存在する。
また、里の集計にも、同様のバリエーションがある。前掲の集計eでは、里の戸口数の集計(【e戸口数】)は「某里領里民×戸口食×人」だが、集計fでは「集凡某里魁某領吏民戸×口食×人」(【f戸口数】)である。さらに集計bはこれらとは著しく相違し。「右某里魁某領吏民×戸父母妻子合×人」(【b戸口数】)である。吏民の「父母妻子」の合計と記されているため、あたかも父母妻子のみ集計しほかの親族は集計されていないようにも見えるが、戸成員の簡にはほかの親族も記載されており、もちろん父母妻子以外も集計の対象であると考えられる。これは、表現が相違していても実質は相違していないことを示すよい例である。
また、それに続くすでに特定の徭役に従事する者の集計(【民】)や、官吏(【吏】)・卒(【卒】)などの集計でも、戸品が書かれているものと無いものとがある(集計bの【民】【吏】には戸品が見えるが、集計c・e・fには無い)。
同類の簿であっても、簿の書式にはバリエーションが存在するのであり、「定領役民」と「定應役民」との表現の違いも、このようなバリエーションの一つであると考えられる。
つまり、「定領役民」「定應役民」「定領事役民」の役民・應役民・事役民はすべて徴発対象となる民を指し、里の簿の締めくくりに置かれるこれらの集計項目は、すべて徴発対象となる民戸の数を集計するものである。
走馬楼呉簡テキスト
竹簡[貳]:長沙市文物考古研究所・中国文物研究所・北京大学歴史学系・走馬楼簡牘整理組2007(編)『長沙走馬楼三国呉簡 竹簡[貳]』全三冊,文物出版社.
竹簡[参]:長沙市文物考古研究所・中国文物研究所・北京大学歴史学系・走馬楼簡牘整理組2008(編)『長沙走馬楼三国呉簡 竹簡[参]』全三冊,文物出版社.
竹簡[肆]長沙簡牘博物館・中国文化遺産研究院・北京大学歴史学系・走馬楼簡牘整理組2011(編)『長沙走馬楼三国呉簡 竹簡[肆]』全三冊,文物出版社.
竹簡[柒]:長沙簡牘博物館・中国文化遺産研究院・北京大学歴史学系・故宮研究院古文献研究所・走馬楼簡牘整理組2013(編)『長沙走馬楼三国呉簡 竹簡[柒]』全三冊,文物出版社.
参照文献
日文
安部聡一郎2017「漢三国期長沙地域からみた走馬楼呉簡」長沙呉簡研究会七月例会発表
關尾史郎2015「長沙呉簡吏民簿の研究(上)─「嘉禾六(二三七)年廣成郷吏民簿」の復元と分析─」,『新潟大学人文学部人文科学研究』137.
鷲尾祐子2010「長沙走馬楼呉簡連記簡の検討―家族の記録について」,『中国古代史論叢』七,立命館東洋史学会→「長沙走馬楼呉簡連記式名籍簡的探討―関于家族的記録」『呉簡研究』第三輯.中華書局.2011年.長沙簡牘博物館(編)『走馬婁呉簡研究論文精選』上、所収、岳麓書社、2016年
2012「走馬楼呉簡吏民簿と郷の状況―家族研究のための予備的検討―」,『立命館東洋史学』35.
2015「分異時期と家族構成の変化について─呉簡による検討」,伊藤敏雄・窪添慶文・關尾史郎(編)『湖南出土簡牘とその社会』,汲古書院.
2017『資料集:三世紀の長沙における吏民の世帯─走馬楼呉簡吏民簿の戸の復原』,東京外国語大学アジアアフリカ研究所.https://publication.aa-ken.jp/ChangshaRegister.pdf
2020「走馬楼呉簡吏民簿の編製時期について」,關尾史郎・伊藤敏雄(編)『後漢・魏晋簡牘の世界』,汲古書院,2020年刊行予定.
中文
侯旭東2009「長沙走馬楼呉簡《竹簡》貳“吏民人名年紀口食簿”復原的初歩研究」,『中華文史論叢』2009年第1期.
2013「長沙走馬楼吳簡「嘉禾六年(広成郷)弦里吏民人名年紀口食簿」集成研究―三世紀初江南郷里管理一瞥」,邢義田・劉増貴主編『第四屆国際漢学會議論文集 古代庶民社會』,中央研究員歴史語言研究所.
李均明2008a「走馬楼呉簡人口管理初探」,卜憲群・揚振紅主編『簡帛研究』2006.広西師範大学出版社.
李均明2008b「長沙走馬楼呉簡所反映的戸類與戸等」『華學』九・十輯(一)
凌文超2011「走馬楼呉簡采集簡“戸籍簿”復原整理与研究―兼論呉簡“戸籍簿”的類型与功能」,長沙簡牘博物館・北京大学中国古代史研究中心・北京呉簡研討班(編)『呉簡研究』第三輯,中華書局,凌文超『走馬楼呉簡采集簿書整理與研究』,広西師範大学出版社,2015年,所収.
楊芬2011「孫呉嘉禾年間臨湘中鄕所轄里初歩研究」,2011年3月,湖南省長沙,中日長沙呉簡学術研討会.
張栄強2014「再論孫呉簡中的戸籍文書―以結計簡為中心的討論」『北京師範大学学報(社会科学版)』2014年第5期
荘小霞2017「走馬楼呉簡“役民”、“應役民”、“事役民”辨析―兼論走馬楼呉簡所見孫呉徭役制度」,長沙簡牘博物館(編)『長沙簡帛研究国際学術検討会論文集』,中西書局.
本論は、JSPS科学研究費JP17K03126およびJP18K01013・JP19K01027の研究成果である。また、アジア・アフリカ言語文化硏究所共同利用・共同硏究課題「秦代地方県庁の日常に肉薄する――中国古代簡牘の横断領域的研究(4)」の研究成果を含む。
編集者注記:2020年4月6日入稿
注
[1]人の前の一字は編綴の縄がかぶさって見えない。釈文では一だが、とりあえず二とする。
[2]冒頭の一字は釈文では未釈字だが、他の類例によって補った。
[3]魁は「竹簡[貳]」釈文では「羅?」とされ、主は釈読されていなかった。侯旭東2013の修正に依拠した。
[4]「竹簡[肆]」釈文は「凡領應役民卌戸」であるが、図版より改めた。
[5]役と五の間は字が消えていたり、裂けた編綴の縄に覆われていたりするため見えない。空間の大きさから五の前に二字存在すると推測した。釈文では「定領應役民五戸」とする。この二例以外に、「 〼役戸卅四戸」(肆885)が存在するが、断片であるためひとまず考慮しない。