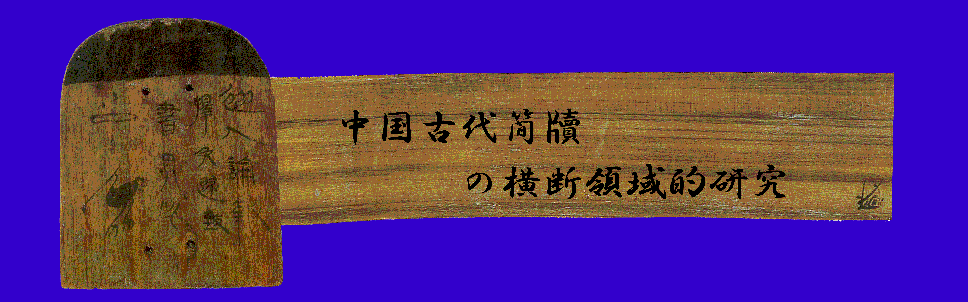上古漢語における「何」の意味に關する覺書
陶安あんど(東京外國語大學)
漢文の世界では、「何」と「何如」もしくは「如何」は、明確に區別される。「何」は、基本的に「なに」と讀まれ、「何如」や「如何」には、「いかん」や「いかんせん」という讀み方が使われる[1]。それは、訓讀の單なる習わしというよりも、古漢語における意味上の差異を巧みに表現している。つまり、「何」が基本的に事物を尋ねるために使われるのに對して、「何如」や「如何」は性質・狀態もしくは方法、つまり事物がどうであるか、もしくはそれをどうするかという意味を表す。
楊伯峻は、文法の視点から、「何」の使い方を次の三種類に纏める。
(一)「何」は、「代詞」(≈代名詞)として文の獨立した「謂語」(述語)・述部の中の「賓語」(目的語)及び稀には文の「主語」となり得る。それぞれについて、次のように楊伯峻が擧げた例文の中から一つのみ揭げる。
①「謂語」:所以然者何?水土異也。(『晏子春秋』内篇雜下)
然らしむる所以は何ぞや。水土異なれば也。
②「賓語」:孟嘗君曰:“客何好?曰:“客無好也”。曰:“客何能?”曰:“客無能。(『戰國策』齊策四)
孟嘗君曰わく、客、何をや好む、と。曰わく、客、好む無き也、と。曰わく、客、何をや能(よ)くする、と。曰わく、客、能くする無し、と。
③「主語」:公笑曰:“子近市,識貴賤乎?”對曰:“既利之,敢不識乎?”公曰:“何貴?何賤?”(『左傳』昭公三年)
公笑いて曰わく、子、市に近し。貴賤を識るか、と。對えて曰わく、既にこれを利とすれば、敢えて識らざらんや、と。公曰わく、何(いづ)れや貴き、何れや賤き、と。
説明すべきは、「賓語」(目的語)の場合は、「動詞+目的語」という通常の語順と違って、「何+動詞」というように、「何」が多く動詞の前に倒置されることと、「何」の含む意味が廣く、①のように理由を尋ねる場合等もあることである。
(二)「何」は、「定語」(形容詞的修飾語)として、名詞の前に置かれることがある。
予豫謂童子:“此何聲也?汝出視之。”(歐陽修『秋聲賦』)
予、童子に謂う。此、何の聲ぞ。汝、出でて之れを視よ。
というように、眞正な疑問を表す場合もあれば、
不知何一男子自謂秦始皇。(『論衡』實知篇)
知らず何の一男子や、自ら秦始皇なりと謂う。
というように、知らない狀況を表す場合もある。
(三)「何」は「狀語」(副詞的修飾語)として質問もしくは反語に使われる。
夫子何哂由也?(『論語』先進。)
夫子、何ぞ由を哂える。(『論語』先進。)
というのが本當の質問で、
彼,丈夫也;我,丈夫也。吾何畏彼哉。(『孟子』滕文公上)
彼も丈夫なり。我も丈夫なり。吾、何ぞ彼を畏れんや。
というのが、反語として實際は否定の意味を表す。
次に、「何如」については、楊伯峻は、「定語」と「狀語」のほかに、「謂語」という用法のみを擧げるが、中國社會科學院語言硏究所古代漢語硏究室編『古代漢語虛詞詞典』[2]には、主語と目的語の用例も列記されているので、文法的にはそれを「何」と同樣に理解することができる。以下「何」に關わる楊伯峻の分類に從って、「何如」の用例を揭げるが、文法的機能が同じながら、意味が「いかん」・「どうであるか」というように、「何」と異なることが一目瞭然となろう。
(一)「代詞」(の單獨使用例)[3]:
①「謂語」:貧而無諂,富而無驕,何如?(『論語』學而)
貧しくして諂う無く、富んで驕る無きは、何如。
②「賓語」:秦攻宜陽。周君謂趙累曰:“子以爲何如?”對曰:“宜陽必拔也。”(『戰國策』東周策)
秦、宜陽を攻む。周君、趙累に謂いて曰わく、子、何如と以爲う。對えて曰わく、宜陽、必ず拔かれんなり。
③「主語」:何如爲大痍?大痍者,肢或未斷,及將長令二人扶出之,爲大痍。(睡虎地秦簡『法律答問』簡208)
何如なるをや[4]、大痍と爲す。大痍とは、肢或は未だ斷ぜず、及び將長、二人に令して之れを扶出せしむるは、大痍と爲す。
(二)「定語」:
釋之久之前曰:“陛下以絳侯周勃何如人也?”上曰:“長者也。又復問:”東陽侯張相如何如人也?”上復曰:“長者。”(『史記』張釋之列傳)
釋之、之を久しくして前みて曰わく、陛下以(おも)うに、絳侯周勃は何如なる人ぞ、と。上曰わく、長者なり、と。又た復た問うらく、東陽侯張相如、何如なる人ぞ、と。上復た曰わく、長者なり、と。
(三)「狀語」:
鳳兮鳳兮,何如德之衰也。(『莊子』人閒世篇)
鳳や鳳や、何如ぞ德の衰えたる。
統語論的にみれば、以上の用例で、「何」と「何如」・「如何」の用法はほぼ出盡くしたように思われるが、意味論的違いについては、藤堂明保と近藤光男の分類が參考になる[5]。藤堂と近藤によれば、疑問詞を使った古代漢語の疑問文は、以下の八種類に分類できる。その中では、「何」と「何如」・「如何」はそれぞれ(ハ)と(二)に對應しており、その意味は、やはり事物を尋ねる場合と性質狀態方法を尋ねる場合とに分かれる。
(イ)どれかを指定することを求めるばあい。(孰/孰與)
(ロ)人を尋ねるばあい。(誰)
(ハ)事物を尋ねるばあい。(何・奚)
(ニ)性質狀態方法を尋ねるばあい。(何如・如何・如-何)
(ホ)工具や方式を尋ねるばあい。(何以)
(ヘ)理由・原因を尋ねるばあい。(何以・何爲・何)
(ト)場所・方向を尋ねるばあい。(何・奚・惡・安・焉)
(チ)數量や時閒を尋ねるばあい。
さて、秦漢の出土文字資料には、「なに」と「いかん」もしくは「いかんせん」という讀み分けでは、文意が正確に表現できない場合がある。例えば、里耶秦簡の簡J1⑧0644には、次のような記載が見られる。
敬問之:吏令徒守器而失之,徒
當獨負。●日足以責,吏弗責,負者死
亡,吏代負償。 J1⑧0644正
徒守者往戍,何[6]?敬訊而負之,可不可?
其律令云何?謁報。 J1⑧0644背
問題となるのは、背面第一行の「何」字であるが、それを除けば、大よそ次のようにそれを讀むことができよう[7]。
|
文書構造 |
讀み下し文 |
||
|
文書本體 |
前置 |
敬いて之れを問う。 |
|
|
本文 |
根據資料 |
吏、徒に令して器を守せしめて之れを失わば、徒、當(まさ)に獨り負うべし。 ●日、以て責むるに足るも、吏、(これを)責めず、負う者死・亡せば、吏代わりて償を負う。 |
|
|
用件 |
徒の守する者、往きて戍するは、何。敬訊して之れに負わしむるは、可なるや不可なるや。その律令は、何と云う。 |
||
|
附記 |
謁うらくは、報ぜよ。 |
||
この簡の記載は、一枚で完結しており、年月日などを省略した簡略な書式の上行文書である。發信者と受信者は、恐らく縣廷内部の人閒である。言葉遣いから推測するに、屬吏が長官(もしくは副長官などの上司)に、法律解釋について質問しているように思われる。
發信者の疑問は、器物の損傷に伴う賠償責任をめぐるが、關連する律文は、類似した規定を次のように、睡虎地秦簡『秦律十八種』簡077-079から窺うことができる。
| 077 | 百姓叚(假)公器及有責(債)未賞(償),其日 |
| 078 | 其日月減其衣食,毋過三分取一,其所亡衆,計之,終歲衣食不 |
| 079 | 【死】亡,令其官嗇夫及吏主者代賞(償)之。 金布 |
百姓(ひゃくせい)、公器を假り、及び債有りて未だ償わず、その日以て之れを收責するに足るに、(これを)收責せず、其の人死亡する(ものは、その官嗇夫及び吏の主する者をして之れを代償せしむ)[8]、及び隸臣妾、公器・畜生を亡(うしな)う者有らば、其の日より月ごとに其の衣食を減じ、三分より一を取るを過ぐるなく、其れ亡う所衆(おお)く、之れを計るに、終歲、衣食以て稍償するに足らずんば、之れを居せしむべきに、其れ之れを居せしめず、其の人死亡する(もの)は、其の官嗇夫及び吏の主(つかさど)る者をして之れを代償せしむ。 金布。
やや込み入った構文ではあるが、要するに、賠償責任を負うべき百姓や隸臣妾に對して、官吏が然るべき債權回收(もしくは勞働による強制執行)の手續きを怠った場合には、債務者の死亡もしくは逃亡によって債權回收ができなくなれば、官吏が代わって辨濟義務を負う、という定めである。本簡の前半に引用されている律の規定では、賠償責任主體が「徒」と入れ替わっているが、死亡もしくは逃亡における官吏の責任に變わりがない。
では、本簡の主眼とするところが何かというと、屬吏が把握している律文では、徒の死亡もしくは逃亡によって回收不能が生じることが要件として規定されているが、徒の兵役のため強制執行が實施できなくなった場合に、官吏の責任がどうなるかということに焦點が當てられる。死亡の場合と同樣に、擔當の官吏が代わって賠償責任を負うか否か、負うならその官吏に對して取り調べ(敬訊)の上賠償責任債務を取り立ててよいか否か。畢竟するところ、法的狀況がどうであるか、もしくはその下でどうすればよいのか、ということが問われる。
そこで、話を「何」の讀み方に戾すと、原文を「徒の守する者、往きて戍するは、なんぞや」と讀んでいては、文意が通じがたい。むしろ、「徒の守する者、往きて戍するは、いかん(どうであるか)」もしくは「いかんせん(どうするか)」と讀むべきように思われる。
類似した問題は、睡虎地秦簡『法律答問』に見える「何論」・「論何」と張家山漢簡『奏讞書』等に見える「何解」・「解何」についても生じる。楊伯峻の整理に從えば、「何」の位置の變化は單なる倒置に過ぎず、どの場合にも「何」は「論」もしくは「解」という動詞の目的語であるようにも見える。傳統的な漢文の知識でも、原文の語順に拘わらず「何をや論ずる」もしくは「何をや解する」と讀むことになろう。しかし、前後文脈を調べると、ここもまたそうした傳統的な讀み方では文意が正確に表現できない。
まず、『奏讞書』から原文を檢討してみよう。『奏讞書』には、被告に對する獄吏の詰問が記される文面が多くみられるが、詰問の末尾は、決まって「何解」で結ばれる。例えば、事案二簡011-012には、
| 011 | (前略)詰媚:媚故點 |
| 012 | 婢。雖楚時去亡,降爲漢,不書名數。點得、占數媚,媚復爲婢,賣媚當也。去亡,何解? |
媚を詰(といつ)むるに、「媚はもと點の婢なり。楚の時に去亡し、降りて漢と爲ると雖も、名數を書せず。點、媚を得(とら)えて占數すれば、媚、復た婢と爲り、媚を賣るは當(しか)るべきなり。去亡するは、何解」。
という。この事案では、漢高祖十一年の三月に大夫祿が江陵縣に訴え出ている。祿の陳述によれば、六年の二月に婢の媚を士伍の點より購入したが、十一年三月に媚が逃亡した。祿が媚を捕獲したら、媚は、漢楚抗爭時に楚から漢に投降したので、楚の時の婢身分は消滅したと主張した。獄吏の取り調べにおいても、媚は同じ主張を繰り返したので、獄吏は、上に引用したように、「名數(戸籍に類似した公的登錄)」を屆け出なかったという法的瑕疵、および點の登錄行爲によって媚が再びその婢となった事實を指摘した上、「去亡」に關する釋明を求める。この文脈では、「何解」を「何をや解する」と讀むのが困難である。獄吏が尋ねているのは、何を釋明するかではなく、(去亡を)どのように釋明するかである。したがって、文意に適った讀み方は、「いかにか解する」というほかなかろう[9]。
「何解」は、『奏讞書』のほか嶽麓秦簡『爲獄等狀』、里耶秦簡および居延漢簡等に多くの用例が見られるが、『奏讞書』と同樣に、何れもどのように釋明するかを尋ねる語として用いられる。例えば、1970年代居延漢簡のEPT59.357には、
●詰尊:省卒作十日輒休一日,于獨不休,尊何解?□![]()
●尊を詰(といつ)むるに、省卒、十日作せば輒ち一日休むに、于獨り休まざるは、尊、何(いか)にか解する。□![]()
『漢簡語彙』[10]は、「何」を「助字。なに。なぜ」と解し、EPT59.357を用例として揭げつつ「何解」を「どのようなのか説明せよ。なぜ。説明を求める常套句。『解何』に同じ」と注釋するが、やはり「何」を「どのように」と捉えない限り、「何解」は正確に説明できまい。
一方、「解何」は『奏讞書』と『爲獄等狀』といった法律文獻には見られず、里耶秦簡と居延・敦煌漢簡等の文書史料にのみ見られる。しかも、里耶秦簡も目下次の一例しか確認できない。J1⑧1639には、
以決事解何殹。
(……)以て事を決するは、解何。
という。文章は他の不明の簡から續いており、正確に分からないところが殘るが、恐らく誤判についてその理由を問い詰めていると推測される。「以て事を決する」とは、先行文章に述べられた事柄に基づいて判決を下すことをいうように思われるが、それに對して、「解何」と聞いているのは、やはりどう釋明するかと捉えるほかなかろう。文法的には、「何」は「解」の目的語ではなく、楊伯峻の謂う所の「謂語」(述語)と考えられるので、讀み方は「解いかんぞ」となろう。
「何論」・「論何」も基本的に「何解」・「解何」と同樣に理解できるので、一例のみ揭げておく。『法律答問』簡008には、次のようの問答が記されている。
| 008 | 司寇盜百一十錢,先自告。可(何)論。當耐爲隸臣,或曰貲二甲。 |
司寇、百一十錢を盜み、先に自ら告(つ)ぐ。何(いか)にか論ぜん。まさに耐して隸臣と爲すべし。或ひと、二甲を貲(はか)る と曰う。
何を論斷すべきかは自明である。司寇は錢百十相當の盜みを犯したので、盜百一十錢という罪を論ずることは問うまでもない。この問答で問われているのは、「司寇」という身分、「先自告」という特殊な事情を考慮した場合、盜百一十錢という罪をどのように裁くかにほかならない[11]。
以上を要約すると、秦漢時代の出土文字資料には、「なに」・「なんぞ」等よりも、「いかに」・「いかん」と讀んだ方がすわりがよいような記述が少なからず見受けられる[12]。この現象をどのように理解したらよいのだろうか。
筆者が思うに、劉淇『助字辨略』の次の記述が一定の手がかりを提供する。『助字辨略』卷二の「何」條は、「夫子何哂由也」という『論語』先進の句を引用して、その「何」について
此何字,猶云何以。
此の何字、猶お「何を以て」と云うがごとし。
と分析する。藤堂と近藤の分類では、「何以」は、理由・原因を尋ねる疑問詞として揭げられる。『助字辨略』は『論語』のほかに、
人性不甚相遠也,何三代之君有道之長,而秦無道之暴也?
人の性、甚しくは相遠からざるも、何ぞ三代の君、有道之れ長きに、秦の無道、之れなるや。
というように、『漢書』賈誼傳をも引用するが、原文を調べてみると、後續文書は果して
其故可知也。
其の故は知るべき也。
となっており、「何」字が理由を尋ねることは疑いない。
さらに、『助字辨略』は、次のようにも述べる。
又『孟子』:“何以利吾國?”此何以,猶云何如,計量之辭也。”
又た『孟子』(梁惠王章句上)には、「何を以てか吾が國を利する」とあり。此の「何以」は、猶お何如と云うがごとく、計量の辭なり。
つまり、『助字辨略』では、「何」を「何以」と、「何以」をさらに「何如」と結びつけて解釋する。「何」の一字で「何以」と同樣に、理由を尋ねる意が表現されることは、次のように、藤堂と近藤も認めるところである。
前にふれておいたように、古代語の「何」「奚」の含む意義は廣くて、時には「何」「奚」だけで「何以」「何爲」などと同じく、理由原因を尋ねる働きを演じさせることもある。
藤堂と近藤が最初に揭げる例文も、『助字辨略』と同樣に、「夫子何哂由也」という『論語』先進の句である。古代漢語の「何」の含む意義が極めて廣いことには、藤堂と近藤は、場所・方向を尋ねる疑問詞を述べるところでも言及する。
このばあい(すなわち「場所・方向を尋ねるばあい」、筆者注)にも、たんに「何」や「奚」だけで「どこ」「どちら」という意味を表すばあいがあるから、注意しなければならない。
言語學的背景を説得的に説明するには、筆者の專門的知識が不足するが、「何」の一字で、「何以」のように理由、「何處」のように場所を表現することが可能ならば、「何如」のように、性質や狀態を表すことができるのではないだろうか[13]。秦漢時代の出土文字資料に見える「何解」・「解何」や「何論」・「論何」がそのような可能性を強く示唆するように思われる。
附記:小文は、アジア・アフリカ言語文化研究所共同利用・共同研究課題「里耶秦簡と西北漢簡にみる秦・漢の繼承と變革――中國古代簡牘の横斷領域的研究(二)」のほか、科學研究費(基盤研究B)「最新史料の見る秦・漢法制の変革と帝制中国の成立」(代表:陶安あんど)の研究成果を含む。
編集者注記:2016年6月22日入稿
[1] 例えば、加藤徹『白文攻略 漢文法ひとり學び』(白水社、2013年初版)59頁、江連隆『漢文語法ハンドブック』(大修館書店、1997年初版)50・62・64頁、柳町達也『漢文讀解辭典』(角川書店、1978年初版)64-67頁等。
[2] 中國社會科學院語言硏究所古代漢語硏究室編『古代漢語虛詞詞典』(商務印書館,1999年初版、2000年第3次印刷)。
[3] 「定語」もしくは「狀語」という文法機能を擔っても、「何」もしくは「何如」・「如何」が「代詞」であることに變わりがないので、楊伯峻の分類は品詞と統語の問題を混同しているともいえようが、「代詞」として纏めた用例は、畢竟するところ、「定語」や「狀語」の修飾語と違って、「何」・「何如」が單獨で、主語・述語・目的語といった文の成文となる文法的特徵を持つ。
[4] 日本語の読み下しでは、格助詞の「を」を伴うが、中国語では、「受事主語」とされる。
[5] 藤堂明保・近藤光男『中國古典の讀み方――漢文の文法』(江南書院、1956年)294-309頁。
[6] 原釋文と校釋は「何」を「可(何)」に作るが、圖版には、「可」形の左側になお微かな墨跡が確認できる。本簡の後續文章から、「可」と「何」が明確に使い分けられている事實が判明するので、この字は「何」と確定できる。
[7] 内容を理解しやすくするために、讀み下し文を表形式で揭げる。
[8] この條文は、二つの要件について同一の法效果を規定するが、要件と效果を次の表のように整理することができる。
|
要件 |
效果 |
|
百姓叚(假)公器及有責未賞(償),其日 |
令其官嗇夫及吏主者代賞(償)之。 |
|
隸臣妾有亡公器、畜生者,以其日月減其衣食,毋過三分取一,其所亡衆,計之,終歲衣食不 |
[9] ちなみに、池田雄一編『奏𤅊書』(刀水書房、2002年)は、讀み下し文を「去亡するは、何れの解あらんか」とし、口語譯を「逃亡したことについて、何か辨明することがあるか」とする。同書には、飯島和俊「『解』字義覺え書――江陵張家山『奏𤅊書』所出の『解』字の解釋をめぐって」を收めるが、この論文も數回「何解」に言及しつつ遂に正確な讀み方を提示しない。
[10] 京都大學人文科學硏究所簡牘硏究班編『漢簡語彙――中國古代木簡辭典』(岩波書店、2015年)
[11] A.F.P. Hulsewe, Remnants of Ch’in Law, An annotated translation of the Ch’in legal and administrative rules of the 3rd century B.C. discovered in Yün-meng Prefecture, Hu-pei Province, in 1975, E.J.Brillは、「何論」を「How is he to be sentenced」と譯している。一方、松崎つね子『睡虎地秦簡』(明德出版社、2000年)は、「何論」を「何をか論ず?」と讀み下し、「何の罪になるか?」と和譯している。
[12] なお、王杖詔書册に見える「𤅊(讞)何」は、前記の「解何」や「論何」とは、文法構造が異なり、「何」字の意味も違う。廣瀨薰雄「王杖木簡新考」(同『秦漢律令硏究』、汲古書院、2010年。初出は東洋學報第89卷第3號、2007年)は、「𤅊(讞)何」を「何を讞しているのか」と和譯し、何も奏讞すべきことがないのにどうして奏讞するのかという文脈をある意味では正確に表現していると言えるが、文法的には誤解を招きやすい。つまり、「𤅊(讞)何」の「何」は、楊伯峻のいう「謂語」(述語)で、「𤅊(讞)」は主語であり、ただしくは「讞するは、何ぞや」と讀むべきように思われる。「何」は、傳統的漢文の世界でも理由を尋ねる疑問詞で、この文では、反語として奏讞すべきではなかったことを表す。
一方、詔書册には、また「問何」という二字が見えており、「𤅊(讞)何」と同樣に、制書の冒頭に位置するため、兩者は恰も對句を構成しているかのような觀を呈するが、前後の文脈を調べると、誰も「問」を發する者がいない。つまり、「問何」の下に文を區切ると、「問」という動詞の主語が、文脈上不明ということになる。奏讞の手續からしても、そこには、下級機關が上級機關に、もしくは臣下が皇帝に何かを「問う」という要素は本來存在しない。そこで、「問何」と後續の文章との續け具合を吟味してみると、この箇所は或は次のように讀めるように思われる。
實は、廣は上奏文の中で、「鄕吏」から受けた屈辱を、王杖を返上する理由とするが、「鄕吏」の名は明記していない。もちろん、第十五簡が缺けているので、その中で言及がないとも限らないが、目下これが最も文脈に則した讀み方ではないかと思う。
[13] 傳世文獻には、「何如」を「何」に作る異文史料がある。『莊子』人閒世篇に
鳳兮鳳兮,何如德之衰也。
鳳や鳳や、何如ぞ德の衰えたる。
というが、『論語』微子は、
鳳兮鳳兮,何德之衰。
鳳や鳳や、何ぞ德の衰えたる。
に作る。『論語』微子の「何德之衰」も「いかんぞ德の衰えたる」と讀むべきように思われる。この文は反語のため、「いかんぞ」と「なんぞ」との違いがあまり明瞭ではないが、どのようにして德がそこまで衰えたかというように、「何如」も「何」も狀態を尋ねる疑問詞と捉えた方が文意に適うのではないかと思う。
清朝の小学の中には、実は、この『論語』微子の「何」を「いかんせん」と読む説がある。吳昌瑩『經詞衍釋』補遺に、
何,猶奈也。或言何,或言奈,皆奈何義也。又或言何如,或言如何,亦奈何義也。『論語』「鳳兮鳳兮,何德之衰」,言奈德已衰也。(之,猶已也。莊子接輿歌,作何如德之衰。)常語。凡論、孟「何以報德」、「何晏也」、「小子何莫學夫詩」、「何必曰利」、「吾何愛一牛」、「何以待之」,皆言奈何也。
何、猶お奈のごとき也。或は何と言い、或は奈と言い、皆な奈何の義ない。又た或は何如と言い、或は如何と言い、亦た奈何の義なり。『論語』「鳳や鳳や,何(いかん)せん德の衰えたる」は、德の已に衰えたるを奈せんことを言う也。(之、猶お已のごとき也。『莊子』接輿が歌は、「何如德之衰」に作る。)常語なり。凡そ『論』・『孟』「何を以てか德に報ん」、「何ぞ晏也」(子路)、「小子何莫學夫詩」(陽貨)、「何ぞ必ず利と曰う」(梁惠王章句上・告子章句下)、「吾れ、何ぞ一牛を愛まん」(梁惠王章句上)、「何以待之」(梁惠王章句下)、皆な奈何せんことを言う也。
というのがそれであるが、『論語』を除けば、挙げている用例は何れも、「なぜ」と理解させる伝統的な反語の「なんぞ」の域を出ない。
なお、『莊子』人閒世篇については、(唐)成玄英『南華眞經注疏』(郭慶藩『莊子集釋』より引用)には、
何如,猶如何。適,之也。(中略)有道卽見,無道當隱,如何懷此聖德,往適衰亂之邦者耶!
何如、猶お如何せんがごとし。適は、之(ゆ)く也。(中略)道有らば卽ちれ、道無くんば當に隱るべきに、如何せん、此の聖德を懷きて衰亂の邦に往適する者や。
といい、劉武『莊子集解内篇補正』には、
如,往也。德指當世說,合下來世、往世爲三世。文言來世不可待,往世不可追,當世則德衰,鳳兮鳳兮,欲何往乎。
如は、往く也。德は、當世を指して說い、下の來世・往世と合わせて三世と爲す。文の言うこころは、來世、待つべからず、往世、追うべからず、當世則ち德衰え、鳳や鳳や、いずくに往かんと欲するか。
という。何れも後續文章の「來世不可待,往世不可追」を念頭に、「何如」もしくは「何」を、孔子がどうしようとするのか(=どうしようもない)という方向に捉えている。『莊子』の原文は、成玄英に從えば、
鳳や鳳や、何如せんや、德ありて衰えたる(邦)に之(ゆ)く。
と、劉武に從えば、
鳳や鳳や、何(いずこ)にや如(ゆ)く、德之れ衰えたるに。
と讀まなければならないことになるが、『論語』の異文とは整合性が取れない。
一方、俞樾『諸子平議』卷17莊子一は、
如、而古通用,此如字當讀爲而。而,卽爾也,蓋指鳳而言。郭注以何如連讀,非是。
如・而、古通用すれば、此の如字は當に讀みて而と爲すべし。而は、卽ち爾なり。蓋し鳳を指して言うなり。郭注、何如を以て連讀するは、是に非らず。
というように、「如」を「爾(なんじ)」と解釋する。