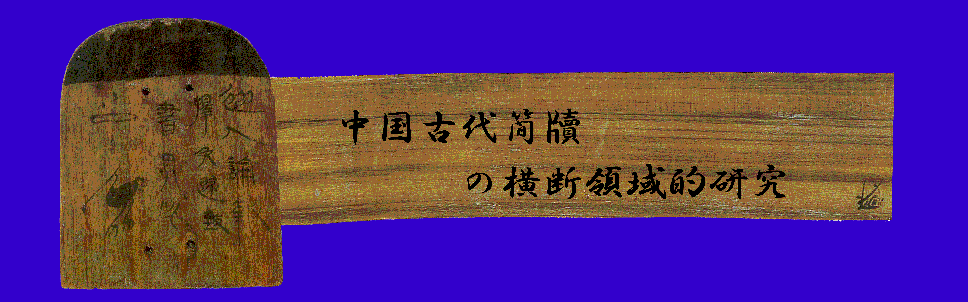湖南長沙五一廣場東漢簡牘J1③:129木牘譯注稿
飯田祥子(龍谷大學)
2010年、湖南省長沙市中心部でまたも大量の簡牘が發見された。現在(2015年4月)までに、長沙市文物考古研究所による「湖南長沙五一廣場東漢簡牘發掘簡報」(『文物』2013-6)に概略がのべられ、一部の簡牘の冩真・釋文が掲載されている。これによると出土した簡牘は一萬枚前後、後漢和帝から安帝期の紀年をもつものがみられ、地方官府にかかわるという。
既發表の簡牘では、形態が幅廣のいわゆる「牘」で、内容は文書であるとみられるものが目立つ。これらにも殘斷缺損や未釋字はあるが、簡牘一枚ごとの文字數・情報量は少なくなく、一枚で内容が完結しているとみられるものもある。
發表された簡牘はごくわずかにすぎず、資料羣全體の性質が把握できない現時點では、取り扱いに慎重であるべきではある。しかし、これらの牘が一枚で完結した文書であるとしたら、個別の既發表簡牘それぞれから引き出せる情報を確認しておくことは、今後公開される資料全體への準備として意味があるだろう。ここでは「簡報」が例九として冩真・釋文を掲載したJ1③:129木牘の譯注を試みたい。
この簡牘は、幅廣の牘(形狀分類〇三甲[1])で、表裏兩面に三行ずつ、行のバランスをとり、全89文字が書かれている。開封や傳達に關する情報は書き加えられておらず、全文が同筆であると考えられる。全體の釋文を示す。
(A面)
1昭陵待事掾逢延叩頭死罪白卽日得府决曹侯掾
2西部案獄涂掾田卒史書當考問縑會劉季興周豪
3許伯山等謹白見府掾卒史書期日已盡願得吏與并
(B面)
1力考問伯山等唯
2明廷財延愚戇惶恐叩頭死罪死罪
3七月八日壬申白(B)
A面1行目からB面2行目までは一續きの文章であるが、B面1行目は下に大きく空白をのこして改行し、「明廷」を行頭に配置する。B面3行目は日付でやや小さく下によせて書かれている。
まず語句に注釋を加える。
「昭陵」
「簡報」が指摘するように、「昭陵」は長沙郡の屬縣である。資水上流で、長沙郡内では西南端に位置する。この簡牘は昭陵縣の官吏が出土地の官府[2]に發信し、出土地で廢棄されたものと考えられる(なお既發表分のなかで發信者に縣名が冠されているのはJ1③:263-109「臨湘令丹丞□叩頭□☆」とこのJ1③:129のみである。J1③:263-109は上行文書の控えであろう)。
「待事掾逢延」
「待事」掾史は文獻にはみられない。ただし既發表五一廣場東漢簡牘J1③:169の發信者は「待事掾王純」であり、殺人犯・逃亡者の逮捕に從事している。これについて「簡報」は「縣曹掾の一つであり、『金石萃編』(中國書店、1985年)巻一四『蒼頡廟碑』に二例『待事掾』が見える。縣廷の雜務の責任を負うのであろうか」という。「蒼頡廟碑」碑陰は『金石萃編』(經訓堂藏板、嘉慶十年)巻十では「持事掾(下闕)」「持事掾髙(下闕)」とあり、『漢代石刻集成』(同朋舎出版、1994)では「持事史」「持事掾髙」、『漢碑集釋』(修訂本、河南大學出版社、1997)では「持事掾」「持事掾髙」とある。しかし『漢代石刻集成』および京都大學人文科學研究所データベース[3]の拓本畫像をみるかぎり、たしかに旁は「寺」だが、偏は闕いているものと「彳」のものの二例であるようにみえる。
また『隷釋』巻五張納碑陰には「待事掾宕渠(闕)訓」「待事掾充國(闕)直」「待事掾枳(闕)敏」「待事掾枳章(闕)」「待事掾安漢王業」、『隷續』巻二十一には「待事掾陰申定士則」「待事掾武當王宗長謀」がみえる。『蒼頡廟碑』の「持事掾」も「待事掾」であるかもしれない。
「叩頭死罪白」
書信に散見される用語であるが、公務にかかわる書信でも多用される[4]。
「卽日」
『史記』鴻門の會のくだりで「項王卽日因留沛公、與飲」(項羽本紀)とある。ここでも、「卽日」は「當日」「その日に」であり、この場合、發信の日付の七月八日を指す。
「得府决曹侯掾西部案獄涂掾田卒史書」
「府」は太守府のことである。五一廣場東漢簡牘は長沙郡治臨湘縣廷の文書であるとされ[5]、この「府」は長沙郡太守府であう。
決曹は『續漢書』百官志太尉條本注に「決曹主罪法事」とあり、嚴耕望は『漢書』『後漢書』にみえる郡國決曹掾史の例から、「この職は治獄をつかさどり、縣をめぐって囚徒を錄する。そのため文法にあかるいものを任じる」[6]とのべる。また「案獄」についても『續漢書』百官志州郡條注がひく『漢官』河南尹屬吏の中に「案獄仁恕三人」、また「張納碑陰」(『隷釋』巻五)に「中部案獄閬中趙應」がみえることを指摘し、「名称からすればおそらく決曹の分職であろう」という。
「西部」は、昭陵縣が長沙郡内では西部に位置するので、郡内西方諸縣の擔當を指すと考えられる。東牌樓東漢簡牘一〇〇一號木牘(2004.C.W.DJ7:1001整理番號五)では臨湘縣の案件について中部督郵掾からの指示がくだっていた[7]。
「侯掾」「涂掾」「田卒史」は郡の掾史を「姓+職」でよんだものである。エチナ漢簡に「府五官張掾召第十候史程竝」(99ES16ST1:11A)、「官移督蓬樊掾檄曰」(99ES17SH1:6A)、東牌樓東漢簡牘に「府朱掾家書」(2004.C.W.DJ7:1015二五)などの用例がみられる。書信などにみえる「姓+卿」と類似した敬稱であろう。
「當考問縑會劉季興周豪許伯山等」
「考問」は取り調べること(「鴻嘉三年、趙飛燕譖告許皇后・班倢伃挟媚道、祝詛後宮、詈及主上。許皇后坐廢。考問班倢伃、倢伃對曰『妾聞、死生有命、富貴在天。・・・』上善其對、憐憫之、賜黄金百斤」『漢書』外戚傳・班倢伃)。
「縑會」「劉季興」「周豪」「許伯山」は取り調べの対象者の姓名であろう。
「謹白見府掾卒史書期日已盡」
「見」は「現」。「卽日」に書を得た現時點を指す。「府掾卒史書」とは先の「府决曹侯掾西部案獄涂掾田卒史書」のことである。
「願得吏與并力考問伯山等」
「并力」は「勠力」、協力することである(『説文』「勠、并力也」)。既發表の五一廣場東漢簡牘J1③:264-294にも「盡力與亭長李徝幷力逐捕純必得爲故」とある。
「唯明廷財」
『後漢書』李賢注「明廷猶明府(黨錮列傳張儉傳)」とあるように、郡府に對する敬稱「明府」と相當する、縣廷に對する敬稱である。既發表五一廣場東漢簡牘では「明廷」は縣廷に用いられている(J1③:129、J1③:169)。陳偉はこれらに基づき、出土地つまり文書の廢棄地點は長沙郡治臨湘縣廷であるとみなしている[8]。
「財」はJ1③:325-1-140、J1③:169にみえ、前稿では「とりさばく」「差配する」と解した[9]。
「延愚戇惶恐叩頭死罪死罪」
「愚戇惶恐」「叩頭死罪死罪」は書信の常套的表現である。
「七月八日壬申白」
七月八日壬申、つまり乙丑朔の七月が存在するのは、『二十史朔閏表』によれば後漢では明帝永平十五年(72)、安帝永初二年(108)、順帝永和四年(139)である。「簡報」は五一廣場東漢簡牘には和帝・安帝期の紀年のものがみられるというが、安帝永初二年七月ならば該當する。既發表簡牘中ではJ1③:263-108が延平元年(106)、J1③:201-30、J1③:281-5Aが永初三年(109)正月の紀年を持ち、近接した時期のものである。
以上に基づき、全體を訓讀する。
【訓読】
昭陵待事掾逢延叩頭死罪して白す。卽日府の決曹の侯掾、西部案獄の涂掾・田卒史の書を得たるに、當に縑會・劉季興・周豪・許伯山等を考問すべし、と。謹みて白す。見に府の掾・卒史の書の期日已に盡きたり。願わくは、吏の與に并力して伯山等を考問するを得(え)ん。唯だ明廷財せられん/財(はか)られん。延は愚戇にして惶恐して叩頭死罪死罪す。
七月八日壬申白す。
續いて日本語譯を試みる。
【現代語譯】
昭陵縣の待事掾である逢延はつつしんで申し上げます。
本日、長沙太守府の決曹の侯掾、西部案獄の涂掾・田卒史からの文書を受領したところ、縑會・劉季興・周豪・許伯山等を取り調べよ、とのことでした。つつしんで申し上げます。現時点で太守府の掾・卒史の文書の期日は已に過ぎております。吏がともに協力して伯山等を取り調べることができますようおねがいします。どうか縣廷はご差配くださいませ。
私延はおろかものでおそれつつしんでおります。
七月八日壬申、申し上げます。
この文書は、昭陵縣待事掾が發信した公文書的書信である。某日までに縑會・劉季興・周豪・許伯山等を取り調べるように郡太守府より指示された。ところが指示文書を受領した時點で期日を過ぎていたために、あらためて臨湘縣(伯山等が拘束されているのであろう)に協力を要請したものと考えられる。
郡府の西部案獄から昭陵縣に取り調べの指示がくだっているのは、事件は昭陵縣でおこったか、關わりが深いためであると考えられる。
「簡報」は逢延が太守府掾史からの指令を受け取った時、期日を過ぎていたため執行を遲らせることを報告したものである、とする。しかし、この木牘文書自體は「明廷」に向けたものであり、期日に間に合わないことを郡太守府に報告・釋明する文書は別に發信されていたのであろう。
また陳偉[10]は、昭陵縣の掾が臨時に臨湘縣で公務にあたっており、臨湘縣廷に提出した報告ではないか、とする。しかし、臨湘縣で出張滞在する他縣の吏が臨湘縣に公務の協力要請をするのではあれば、口頭で陳情すればよく、書信の體裁をとるとはいえ文書をもちいるのであろうか、という疑問を感じる。むしろ逢延自身は昭陵縣にあり、配下の吏を臨湘縣に派遣するのに持參させた依頼狀であるように思われる。
いずれにせよ、この簡牘からは長沙郡内の事件を巡り、郡太守府と複數の縣が取り調べに關與しているさまがみられる。具體的には、郡府屬吏が文書により期日を指定して任務を指示し、縣廷屬吏はそれに從い實際の取り調べにあたっている。
後漢中期の時点での郡府−縣廷間の關係を示唆する興味深い史料であるということができよう。
編集者注記:2015年05月07日入稿
注
[1]髙村武幸「中國古代簡牘分類試論」『木簡研究』34、2012。
[2]陳偉「五一廣場東漢簡牘屬性芻議」(簡帛網2013-09-24)は臨湘縣の文書類であろうとする。
[3]京都大學人文科學研究所所藏石刻拓本資料(kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp)。
[4]鵜飼昌男「漢簡に見られる書信樣式簡の檢討」(大庭脩編『漢簡研究國際シンポジウム’92報告書 漢簡研究の現狀と展望』關西大學東西學術研究所、1993)。
髙村武幸「漢代文書行政における書信の位置づけ」『東洋學報』91-1、2009。
[5]陳偉「五一廣場東漢簡牘屬性芻議」簡帛網2013-09-24。
[6]嚴耕望『中國地方行政制度史 秦漢地方行政制度』(中央研究院歴史語言研究所、1961)
[7]籾山明「後漢後半期の訴訟と社会−長沙東牌樓出土一〇〇一號木牘を中心に−」(夫馬進編『中國訴訟社會史の研究』京都大學學術出版會、2011)。
[8]陳偉「五一廣場東漢簡牘屬性芻議」(簡帛網2013-09-24)。
[9]飯田祥子「長沙五一廣場東漢簡牘J1③:325-1-140木牘の初步的整理」(http://www.aa.tufs.ac.jp/users/Ejina/note/note08(Iida).html 2014)。
[10]陳偉「五一廣場東漢簡牘屬性芻議」(簡帛網2013-09-24)。