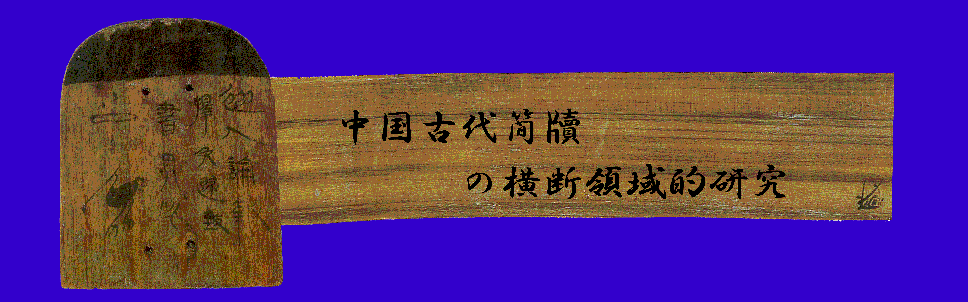榺形木簡窺管
籾山明(東洋文庫)
肩水金關遺址T23から、特徴的な形状をもった斷簡が二枚出土している。うち一枚73EJT23:1048は上下が殘缺し、圖版の計測による殘長は約80mm。下端近くに18×4mmほどの凸部が作り出され、正背兩面に同筆で「福祿日至」の文字がある(圖1。以下「簡1」と呼ぶ)。「福祿日至(福祿が日ごとに至る)」とは、幸福の到來を意味する語句に違いない [1]。もう一枚73EJT23:1056は下部が殘缺し、圖版の計測による殘長は約60mm。上端部分に15×5mmほどの凸部を作り出し、正背兩面に同筆で「官高遷」の文字が記される(圖2。以下「簡2」と呼ぶ)。上端には本來の切斷面が殘されているから、「官」より上に文字は無かったとみてよい。「官高遷」は高い官位に昇ること、官吏としての榮達を意味する語であろう。簡1・2とも文字はほぼ木簡の形に沿って配置されており、この形状に加工した上で書き付けられたものと判斷される。形状と記されている語句の内容とから、二枚は同じ機能をもった簡であったと思われる。
「高遷」の文字を記した木簡は、額濟納漢簡の中にも一例見出せる。99ES16SF4:1がそれで、兩端が廣く中央が狹い竪杵のような形状をもち、上部に「勝官」、下部に「高遷」の文字がある。圖版の計測による長さは235mm。上端の角を小さく缺くものの、ほぼ完形を保った簡である(圖3。以下「簡3」と呼ぶ)。「勝官」の「勝」字を「昇」の通假とみるか、あるいは「任(たえる)」の意味として「任務をしっかり引き受ける」ととらえるか、にわかには決め難いけれども、いずれにしても「高遷」と同樣、官吏としての理想を意味する語であろう。形状と記されている語句とからみて、簡3も簡1・簡2の同類であると言ってよい。
額濟納漢簡の譯註がすでに指摘している通り、簡3の特異な形状は織機の「榺」に由來する [2]。『説文解字』木部に「機持經者(織機の經を保持するものである)」と説くように、榺とは整經した經絲(たていと)を卷きつける経巻(たてまき)具(ぐ)、日本で「ちきり」と呼んでいる部材のことである [3]。榺が織機の部材であることは、次のような里耶秦簡からもうかがえる。
木具機四「—」 木織杼二「—」 木織榺三「—」〼 (J1⑥25)
各項に別筆でチェックマークが打たれているのは、點檢簿であることをものがたる。「杼」とは緯絲を入れる緯打(よこうち)具(ぐ)のことであるから、「織杼」と「織榺」は組立てていない部品の状態であり、組立てて使用可能となった織機が「具機」であろう。『里耶秦簡牘校釋』の注に「具機は織機の一種ではないか(疑是織機的一種)」と説くのは、やや正確さを缺いている [4]。榺はまた「勝」字に作る。『藝文類聚』卷65・織に引く王逸の「機賦」に「勝復廻轉」とある「勝復」は「榺と椱」、すなわち「ちきり」と織り上げた布を卷き取る布巻(ぬのまき)具(ぐ)である「ちまき」とを指す。織機の部位で「廻轉」運動をするのは、この二つに限られる。簡3にいう「勝官」は、官吏としての精勤ないし榮達と經卷具の名稱とを掛けた可能性が高い。
織機の部材としての榺の形状は、出土遺物から確認できる。圖4は廣西壯族自治區貴縣羅泊灣の一號墓から出土した三件の木製明器で、いずれも幅廣い方板状の兩端部分と細長い角材の軸部から成る [5]。この獨特の形状がもつ機能的意味については、東村純子の解説が簡にして要を得ている。
兩端を幅廣につくるのは、支柱にもたせかけるためである。これとは對照的に中央の軸部が細く削り出されるのは、卷き上げたときの經全體の徑が大きくなるからである。一般に經の配列が亂れ絡まるのを防ぐため、細竹などでできた「機(はた)草(くさ)」を挾み込みながら卷き上げる。
東村が紹介する滋賀縣斗(との)西(にし)遺跡出土の經卷具は、ヒノキの板目材を用いた實物で、軸部の長さは52.8cmを測る [6]。
支柱にもたせかけるためであるから、榺の兩端部の形にはさまざまな變種が見られる。簡1の下部先端が突出しているのは、そのような變種のひとつを模したのであろう。機草を挾み込んで經絲を卷き取る作業の樣子や、織機の支柱にもたせかけた裝着の状態などは、圖5に示した朝鮮時代の天秤腰機のスケッチが參考になる [7]。このような經卷具を備えた織機では、ある程度まで織りが進むと、經絲の張りをいったん緩め、榺を半回轉させて絲を繰り出し、織り上がった布を手前の椱に卷き取ったのち、再び張力をかけて織っていく。前田亮が説くように、「經卷具のない織機では、整經した經絲の端から織っていた。經卷具を設置すると、經絲を一旦經卷具に卷取ってから織る」 [8]。したがって、經絲は榺から織り手に向けて少しずつ供給されることになる。
ところで、四川省成都曾家包後漢墓の畫像磚に見える織機では、丸棒形の榺が機枠に取り付けられており、兩端に齒車のような部品が付いている(圖6)。この部品の機能については、R・ラドルフが圖版解説の中で的確に説明している [9]。
織機のフレーム上端部にある經卷具には、適切な状態にセットされた後で回轉するのを防ぐため、砂時計形の「止め具locknut」が二つ付いている。平行した經絲がフレーム下端の布卷具まで張られているが、その箇所は手前に座る婦人の陰になっている。
機能的には止め具であるが、あえて「砂時計形」—あまり適切な表現ではないが—が選ばれたのには理由があろう。廣く知られているように、この形は後漢時代の畫像石・畫像磚の中に描かれるほか、玉製や金製の飾具にも用いられている [10]。林巳奈夫によれば、その形状は圓と×とから成り、圓は「萬物の生産、生育の源泉となる陰と陽のエネルギーの未分裂の状態のエッセンス」である璧、×は不死・永遠と結び付く「桛(かせ)とり」の動作をあらわすという。このような象徴的意味を有する圖章に、漢人は子孫繁榮・五穀豐穰といった現實的願望を託した、というのが林の説である [11]。
この「砂時計形」が榺の止め具にも用いられているのは、兩者が同じ象徴的意味を有するためだろう。『列女傳』魯季敬姜の傳に、各種官職を織機の部位に喩えた話が見える。魯の敬姜は息子の文伯に向かい「國を治める樞要は、すべて經絲にある(治國之要、盡在經矣)」と語り出し、幅(伸子)や梱(杼)などの織機の部位ごとに對應する官職を列擧したのち、「ゆるゆると伸びて盡きることがない(舒而无窮)」のは「摘」であるから「摘は三公にするがよい(摘可以爲三公)」と言葉を結ぶ。「摘(樀)」とは榺の別稱であるが、そこから經絲が繰り出されるさまを「舒而无窮」と表現していることに注目したい [12]。卷き取られている經絲の量はもちろん有限であるが、緩慢な織りの速度に照らして見れば、「无窮」に繰り出されてくるとの感覺を抱いたとしても不思議ではない。その結果、經卷具である榺自體に、萬物の生産・生育や不死・永遠といった意味が付與されることになったのであろう。圖7に示した河南省南陽新野出土の畫像磚に見える西王母と思われる女性は、榺そのものを頭上に載せている。片手に持つのは不死・永遠を象徴する桛であるから、榺にも同樣の意味が込められているに相違ない[13]。
經卷具を模した形の木簡に幸福や榮達の獲得を意味する語句を書き付けるのは、經絲を永遠に繰り出す榺に人間の運命を左右する力が宿ると考えたからではあるまいか。この種の榺形木簡が具體的にどのように使用されたのか、現有資料からうかがうことはできないが、簡1・簡2が正背兩面に文字をもつのは、單獨で用いられたことを推測させる。あるいは願望を書くこと自體に意味があり、その達成を待つことなく短時日のうちに廢棄されたとも思われる。あくまで憶測の域を出ないけれども、現代人が七夕飾りの短册に願い事を書くような、風俗習慣の一端であったのかも知れない。
編集者注記:2014年07月25日入稿
【付 圖】



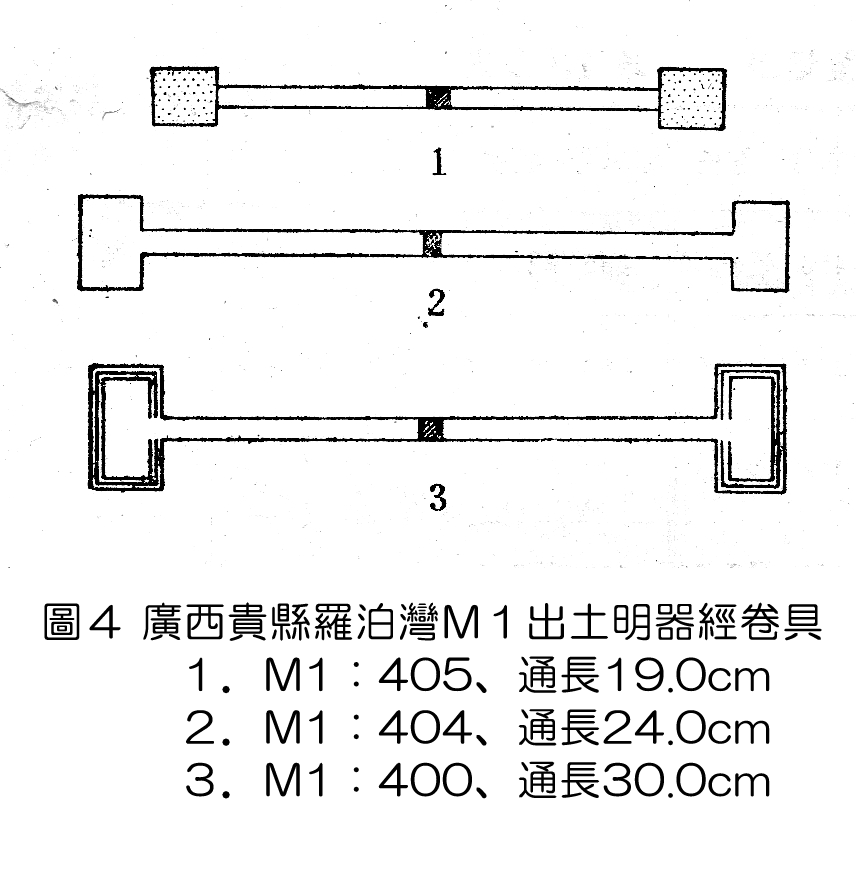
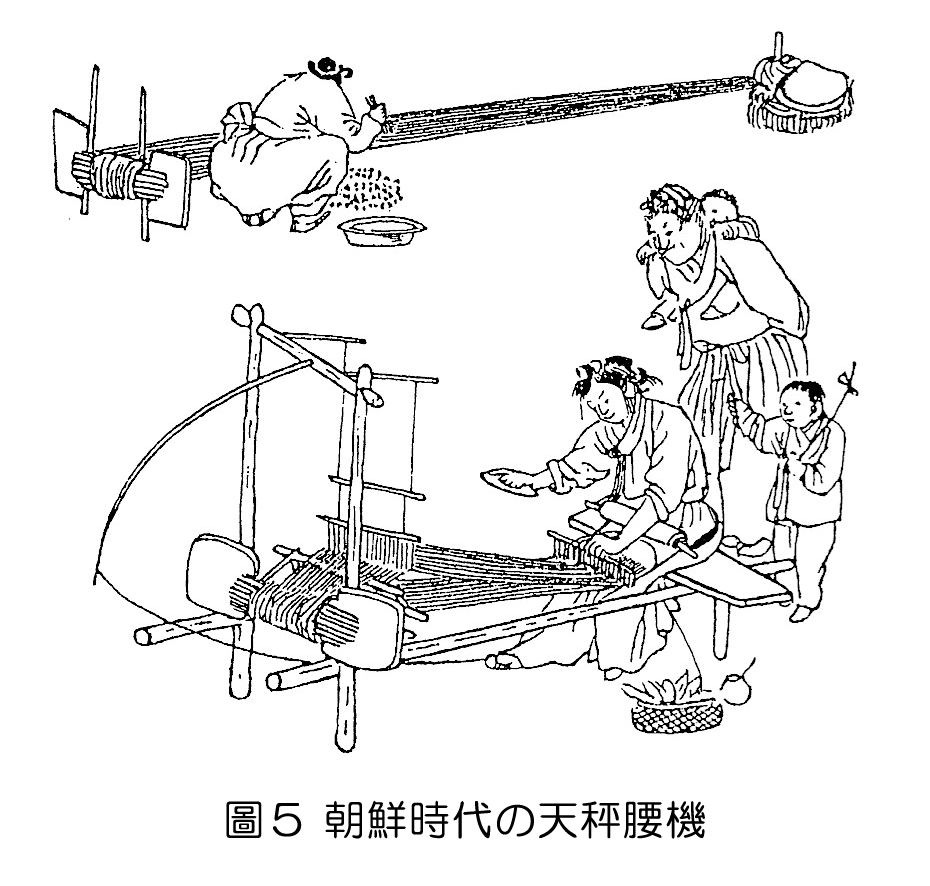
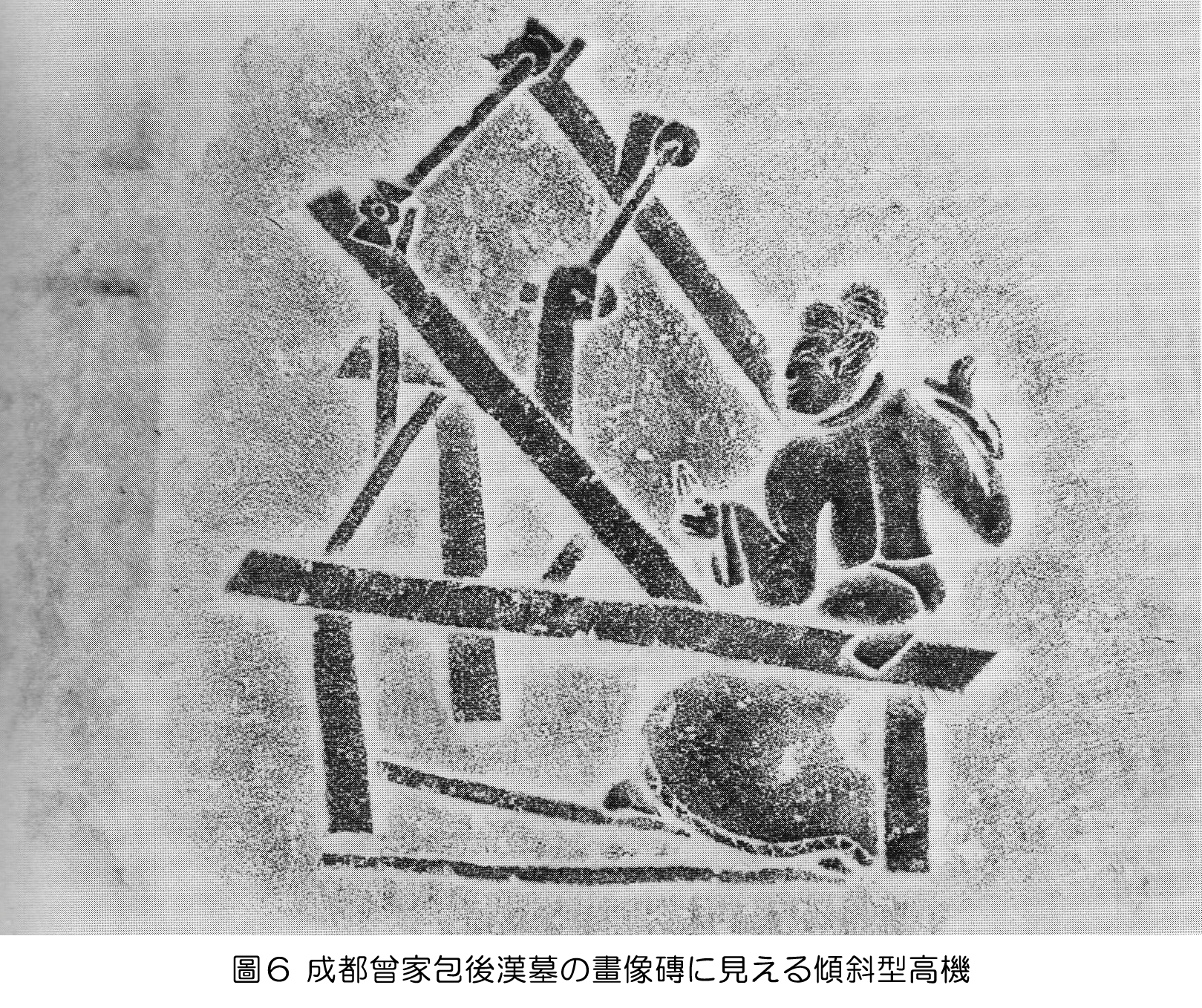
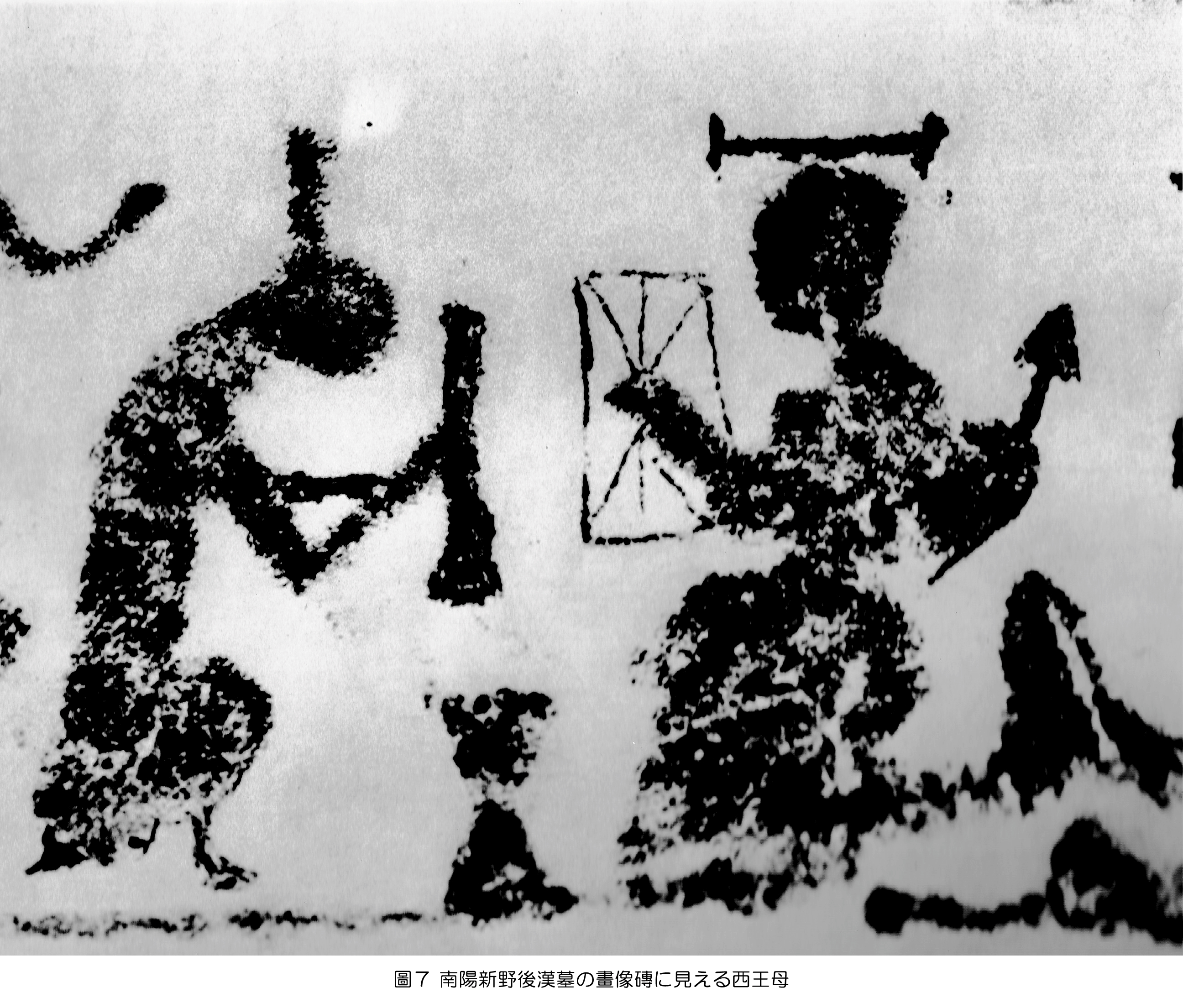
注
[1]「福祿」の語は本來「幸福と秩祿」を意味するのであろうが、廣く「さいわい」一般を指した用例も散見される。たとえば董仲舒の對策に「更化則可善治、善治則災害日去、福祿日來」(『漢書』董仲舒傳)と見える「福祿」は、明らかに「災害(わざわい)」の對語であろう。
[2]エチナ漢簡講讀會「エチナ漢簡選釋」(『中國出土資料研究』第10號、2006年)219頁。
[3]日本では一般に「ちきり」と呼ばれるが、他に「おまき」「まきぶし」などの別稱・地方名もある。角山幸洋「手織機(地機)の東西差—産業史の立場から—」(『民具が語る日本文化』、河出書房新社、1989年)參照。
[4]陳偉主編『里耶秦簡牘校釋』第一卷、武漢大學出版社、2012年、25頁。
[5]廣西壯族自治區博物館編『廣西貴縣羅泊灣漢墓』、文物出版社、1988年、67頁。
[6]東村純子『考古學からみた古代日本の紡織』、六一書房、2011年、91頁。
[7]前田亮『圖説手織機の研究』、京都書院、1992年、173頁。圖版キャプションには「200年前の朝鮮の天秤腰機(金弘道筆、織造圖)」とある。前田の指摘する通り、この圖は經の「開口状態と綜絖の關係がおかしい」。
[8]同前、176頁。
[9]Lucy Lim (ed.), Stories from China’s Past: Han Dynasty Pictorial Tomb Reliefs and Archaeological Objects from Sichuan Province, People’s Republic of China, San Francisco: Chinese Culture Center, 1987, p.96.
[10]八木春生「『勝』についての一考察—『勝』と昇仙思想の關係を中心として—」(『美學美術史論集』第9輯、1992年)に類例が集められている。ただしこの論考では、經卷具と西王母の頭飾り、および戴勝という鳥の羽冠の三者について、理解の混亂が見られるようである。昇仙思想との關連も論證されたとは言いがたい。
[11]林巳奈夫「漢代の永遠を象徴する圖柄」(『史林』第83卷第5號、2000年)。
[12]鄒景衡によれば、周の三公すなわち太師・大傅・大保の「坐して道を論じ、治國の政令を謀慮する、臣下の中で最も尊い者」であるという性質が、察知できないほど緩やかな動きであるにもかかわらず織物の良し惡しを決める「織機の重要工具」としての經卷具に喩えられたのであるという(「列女傳織具考—蠶桑絲織雜考之六—」、『大陸雜誌』第45卷5號、1972年、246頁)。
[13]趙成甫主編『南陽漢代畫像磚』、文物出版社、1990年、圖160。同書の解説は、もう片方の手に持っているのは「不死樹」であると説くが、むしろ桛とセットになった絲卷具とみるのがよいだろう(鈴木直美氏の敎示による)。