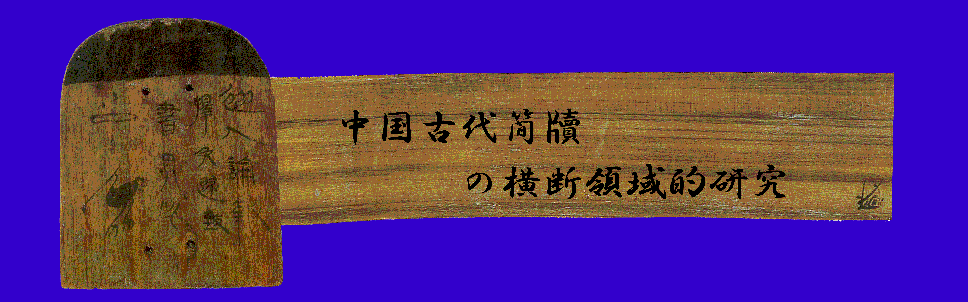始皇帝期の避諱
—里耶秦簡J1⑧461簡「更名扁書」A20・A21の解読—
渡邉英幸(愛知教育大学)
里耶秦簡J1⑧461簡は、遷陵県の官吏が統一前後の用語・用字の改訂を一覧にして掲示した「扁書」と考えられている[1]。以下、これを「更名扁書」と呼ぶことにしよう。公的な用語や用字の規定は、秦の国制や観念を反映している可能性が高く、類い稀な史料的価値を有する。すでに游逸飛氏の包括的研究をはじめ、張春龍・龍京沙、胡平生、邢義田ら諸氏がその内容に検討を加えており、解明された点は少なくないが、なお検討を要する部分も多い。ここで取り上げる条文も従来その意味が正確に解読されていない。以下に私見を提示し、大方の批正を仰ぐとともに、学界の注意を喚起したいと考える。
「更名扁書」は上下二段に分けて用語や用字の規定を箇条書きで示している。ここで取り挙げるのは、上段のA20「曰產曰族」[2]とA21「曰五午曰荆」の二条である。游逸飛氏はA21条につき、「曰A曰B」の構文を「故稱A、今稱B」の意味とし、「五午」を「楚」と通仮関係にある異体字と解釈して、「楚」から「荆」への改称(避諱)と理解している[3]。「荆」が荘襄王の諱「楚」の避諱字であったことは夙に知られている。しかし「五午」を「楚」の異体字とする解釈には疑問があり、さらにA20条の「產」から「族」への変更の実例は全く認められず、後述のように里耶秦簡ではむしろ「產」字の方が有意に用いられている。したがって「曰A曰B」を「故稱A、今稱B」の意とする解釈は誤りである。他の諸氏も概ね「A→B」の改称と解釈し、A21条に対して各自の解釈を提示しているが[4]、やはりA20条「曰產曰族」の方は全く説明できていない。これらは「曰A曰B」を「A→B」の更名規定と早合点したために陥った誤解であると考えられる。
ではこの両条はどのように解読すればよいのであろうか。実はこの「曰A曰B」構文は、ただ一つの想定を加えるだけで、驚くほど容易に解読することができる。それは、「A」・「B」両字以外の、第三の文字からの用語改訂の可能性である。
まずA20条「曰產曰族」を解読しよう。「產」とは何か。周知のように「產」は秦簡において「生」と通じ、「うむ・いきる」等の意味で使用されている。実際、里耶秦簡でも「產」字の使用例が既発表分で24例認められる[5]。ところが興味深いことに、里耶秦簡では、その同義字である「生」が今のところ一字も確認できない。この用字の特異さは、時期的に先行する睡虎地秦簡と比較することで一層明らかとなる。すなわち睡虎地秦簡では「うむ・いきる」等の意味で「生」・「產」両字が混用され、とくに「生」の用例が圧倒的に多かった[6]のに対し、里耶秦簡では、全て「產」字に統一されており、例えば人間の「生き死に」を表現する場合でも、「死産」なる一見奇妙な表現が使用されている(J1⑧534・894など)。こうした用字傾向の偏差は、戦国後期の秦では問題なく使用されていた「生」という文字が、統一前後を境に、少なくとも公文書の領域から消失し、代わって「產」字のみが専ら使用されるようになった事実を物語っている[7]。
次に「族」である。先の「生→產」を念頭に置けば、「產」ではなく、やはり何らかの別字からの呼び換えではないかと推定される。この推定に基づいて文献・出土文字資料を通覧すると、「族」とほぼ同義で、「生」と全く同音通仮関係にある字として、「姓」という字が浮かび上がってくる[8]。
この推定を導く根拠となるのは、やはり睡虎地秦簡で使用されていた「姓」が[9]、統一以後の秦簡で消失している事実である。周知のように統一秦は始皇二十六年、「たみ」を意味する呼称として「黔首」を採用したが、これは統一以前の用語の「百姓」を呼び変えたものである。実際、睡虎地秦簡では「百姓」(資料a.)、龍崗秦簡・里耶秦簡では「黔首」が使用されている(資料b.。張家山漢簡では「民」)。さらに漢代史料では人の姓を「姓○氏」と記載することが通例だが(資料e.・f.)が、興味深いことに里耶秦簡では同様の事例を「族王氏」(資料c.)と表記している。これは「姓」と書くべきところを「族」と表現した事例であろう。同様に『奏讞書』案例三「南、斉国族田氏」(資料d.)も、「姓田氏」の意味であり、秦の用字例を踏襲した表現であったことが判明する。
以上のようにA20「曰產曰族」は、「產と曰ひ、族と曰へ」と読み、「〔生を使用せずに〕產を使用し、族を使用せよ」の意味であったことが判明した。それでは次に、従来の研究で解釈の割れていたA21「曰五午曰荆」を改めて考えてみよう。A20の検討結果を踏まえれば、当該条も表記されていない何らか別の字からの呼び換えを定めたものであった可能性が高い。それは何か。やはり「楚」字以外にあり得ないと考える。まず「荆」は「楚」の避諱字として周知の文字であり、「荆と曰へ」とは「〔楚を使用せずに〕荆を使用せよ」の意味であること、ほとんど疑いを容れないであろう。
では「五午」とは何か。ここで想起すべきなのが、戦国・秦漢期の「楚」が、長江流域から淮水流域・泗水流域を含むきわめて広大な地域を指す概念であり、しかもその範囲が時期とともに転移していた事実である。例えば『史記』貨殖列伝には、「西楚・東楚・南楚」という地域概念が見えており、「東楚」には東海・呉・広陵が含まれている[10]。この事実と、先のA20の検討結果を踏まえるならば、「五午」は「楚」ではなく、陳偉氏や張春龍・龍京沙両氏が想定するように、やはり「呉」であったと考えるべきであろう[11]。言うまでもなく「呉」とは、戦国楚が最後に拠点とした長江下流域の地域的呼称である。つまり「五午と曰へ」とは、秦が戦国末に征服した長江下流域を、征服前の自称である「楚」とは呼ばずに「五午(呉)」と呼称せよ、と定めた条文であったと考えられる。おそらくは広大な旧楚領の中でも、淮水流域の陳を含む西部を「荆」、長江下流の東部を「五午(呉)」と呼称したのであろう。補うならば「〔敢えて楚と曰ふ毋れ。〕呉と曰ひ、荆と曰へ」となる。
以上のようにA21「曰五午曰荆」は「五午→荊」の呼称変更ではなく、簡文に現れていない「楚」という字の使用を禁止し、これに替えて「五午(呉)」・「荆」二字を使用を義務づけた規定であったと考えるべきである。
a. 上節(即)發委輸、百姓或之縣就(僦)及移輸者、以律論之。」49
(睡虎地秦簡『效律』第49簡)
b. 啓陵鄉廿七年黔首將□大男子一人 (里耶秦簡J1⑧233)
c. 宂佐上造臨漢都里曰援庫佐宂佐年卅七歲
為無陽衆陽鄉佐三月十二日 族王氏
凡為官佐三月十二日 (里耶秦簡J1⑧1555正第一欄)
d. ●今闌曰、南齊國族田氏、徙處長安、闌送行取(娶)為妻、與偕歸臨菑、未出關得。它如刻(劾)。 (張家山漢簡『奏讞書』案例三、第18−19簡)
e. ●状辭曰公乘居延中宿里年五十一歳姓陳氏 (居延新簡E.P.T68:68)
f. ●用神龜之法以月鼂以後左足而右行至今日之日止問」直右脅者可得姓朱氏名長正西(下略) (尹湾漢簡YM6D9A)
以上の考察に大過なければ、「更名扁書」A20条は「生」の使用禁止と「產・族」両字の使用を、A21条は「楚」の禁止と「呉・荊」の使用を定めた条文であったと考えられる。いずれも禁止対象の文字を表記しない、すなわち当該簡牘上でも忌避が徹底されている点に特徴がある。忌避の理由は何であろうか。それはやはり避諱であった可能性が高いと考える。とくに後者の「楚」の忌避は、疑いなく始皇帝の父親・荘襄王の諱を避けたものであっただろう。問題は前者である。現存する秦代史料には、始皇帝の周囲に「生」なる諱を持った近親者が確認できない。少なくとも、彼の祖父や曾祖父の諱でなかったことはほぼ確実である[12]。では一体、誰の名であったのか。
この疑問に答えることは難事だが、手がかりはある。それは里耶秦簡の文書史料から浮かび上がる避諱の原則である。里耶秦簡では、始皇帝在位中の年月表記では「正月」を使用し、二世皇帝治世では「端月」が使用されている。この事実は、始皇帝本人の諱「正」が生前は避けられず、死後に避けられていたこと—すなわち秦代の避諱は死後避諱が原則であった事実を示している[13]。この原則と、「生」の忌避が睡虎地秦簡では徹底せず、里耶秦簡に至り徹底して避けられている状況から推測すれば、「生」とは、
(1)荘襄王の死去よりも後、
(2)統一よりも前に死去していた、
(3)荘襄王と同じく始皇帝の尊属に当たる近親者の諱
となる。この条件に合致する人物は始皇帝の母親帝太后(秦王政十九年死去)だけである[14]]。然りとすれば、私たちはこの「更名扁書」の出現により、これまで不明であった始皇帝の母親の諱を、はじめて突き止めたことになる。
以上のように、始皇帝治世下における「生」・「楚」の忌避[15]という事実が判明した。「始皇、死を言ふを悪む」とは著名な説話だが、実際には「死」ではなく「生」が忌避されていたことになる。この事実は、文献資料の史料批判[16]や、重要語句の解釈にも影響を及ぼす可能性がある。なお本稿はA20・A21条のみを取り上げて概略を示したものだが、「更名扁書」全体および相関問題を含め、近日中に定稿を公表したいと考える。
編集者注記:2013年10月19日入稿
注
[1]張春龍・龍京沙[2009]、胡平生[2009]、游逸飛[2011]、邢義田[2012]参照。簡は幅広の木版上に上下二段に分けて箇条書きが並んでおり、Aは上段、Bは下段を示す。文字はあまり上手には見えない。胡平生氏は正式な詔令・文書ではなく、県吏が各種の詔令・文書から抄録・掲示した名称変更の彙編であり、「扁書」と称すべきものとする。なお簡牘番号は当初8-455号と報告されていたが、『里耶秦簡(壹)』の簡番号はJ1⑧461とされている。以下、本稿では『里耶秦簡(壹)』の番号に従う。
[2]「族」。原釈文は「疾」とするが、陳偉主編[2012]157頁の字釈に従い改める。
[3]游逸飛[2011]95頁参照。游氏は「“楚”与“五”、“午”皆属魚部韻、亦可通仮」とする。しかし「五」と「午」の同音通仮は確実としても、肝腎の「楚」との通仮事例が示されていない。韻が同じというだけで「楚」と見なすのは根拠が薄弱である。
[4]例えば張春龍・龍京沙[2009]は陳偉氏の意見を引きつつ「五午」を「呉」と解釈し、「秦以“荆”称“楚”、簡文意爲呉地亦称荆」と述べる。また邢義田[2012]は「五午」を「啎」と解釈し、顔師古の「逆也」という訓詁(『漢書』嚴延年伝注)を引き、戦国秦は楚国を貶めて「啎」と呼称していたが、統一後に楚を悪言する必要がなくなったため「荆」に呼び換えたのだと論じている。「五午」字の解釈は意見が分かれているが、当該条を「五午」から「荆」への呼び換えと理解する点では選ぶところが無い。
[5]里耶秦簡の既発表分では、「產」字が24例(J1⑧100、⑧461、⑧486、⑧490(3)、⑧495(4)、⑧501、⑧519、⑧534、⑧537、⑧793、⑧894、⑧918、⑧984、⑧1020、⑧1284、⑧1410、⑧1455、⑧1866、⑧2214)確認できる。これに対し、「生」字は今のところ一例も確認できない。同じ統一秦期の律令を含む龍崗秦簡でも、「生」は見えず「產」のみが1例用いられている(第38簡)。
[6]睡虎地秦簡における「生」・「產」両字の使用状況は下表の通り。
篇名
「生」 「產」
編年記 1 5
秦律十八種 6 —
法律答問 9 3
封診式 1 1
爲吏之道 — 1
日書甲種 132 3
日書乙種 117 —
合計
266 13
*語書・效律・秦律雑抄には用例確認できず
[7]最近公表された岳麓書院蔵秦簡(第三分冊)の裁判案例『為獄等狀』四種においてもやはり「生」ではなく「產」が用いられているようである。ちなみに張家山漢簡でも「產」の用例が多いが、『奏讞書』には「生」字が一例確認でき、漢が秦の用語を継承しつつも、再び「生」字を使用しはじめたことを示す。
[8]「生」と「姓」の通仮は先秦・秦漢期の文字資料にあまねく確認でき、ほぼ同字と言ってよい。秦の青銅器銘文では春秋中・後期の宋出秦公鐘(『殷周金文集成』270)に「萬生(姓)是敕」の用例があり、漢初のテキストでは馬王堆帛書『十六経』・『老子』乙本、銀雀山漢簡『孫子兵法』・『孫臏兵法』、張家山漢簡『蓋廬』などに「百生(姓)」の事例がある。白於藍[2012]746~747頁を参照。
[9]睡虎地秦簡の「姓」字は全部で14例、すべて「百姓」の熟語である。
[10]『史記』貨殖列伝に淮北・陳・汝南から江漢平原を「西楚」、彭城以東の東海・呉・広陵を「東楚」、衡山・九江・江南・豫章・長沙を「南楚」とする認識が見える。
[11]張春龍・龍京沙[2009]。案ずるに「五(吾)」と「呉」との通仮は金文資料に実例があり、攻敔王光剣(『殷周金文集成』11654・11666)は「呉」を「敔」に、攻敔王夫差剣(『集成』11637・11638・11639)も「敔」もしくは「五攵」に作る。「五」・「吾」は疑いなく同音通仮字である(白於藍[2012]239頁)。従って「五午」は「敔」と同音で、恐らく「呉」の別字体であった可能性が高い。ただし張春龍・龍京沙[2009]が「呉」から「荊」への呼び変えのごとく解釈している点には従えない。
[12]因みに始皇帝の祖父孝文王の諱は「柱」、その父昭襄王の諱は「則」もしくは「稷」と伝えられている。『史記索隠』秦本紀武王四年・昭襄王五十六年条を参照。
[13]秦~漢初の避諱については生前避諱説(李学勤[1981]・劉殿爵[1988]・影山輝国[2005]・来国龍[2008])と死後避諱説(龐樸[1977]・Mansvelt Beck[1987]・鶴間和幸[2001])とが対立している。既発表分の里耶秦簡では二種類の正月表記があり、「正月」が32例(確認紀年は「廿九年」~「丗五年」)、「端月」が3例(J1⑥3「元年」、ほか紀年不明2例)確認できる。前者は始皇帝の治世下、後者は二世皇帝の治世下のものと推定される。これは始皇帝の生前はその諱「正」が避けられていなかったことを示し、龐樸・Mansvelt Beck・鶴間和幸ら諸氏が論ずる「卒哭而諱」(生前は諱まず、死後に諱む)の原則に合致する。
[14]そもそも礼制では子が親の諱を避ける場合、亡父のみならず亡母の諱をも避けることが原則であった。『禮記』曲禮上に「卒哭乃諱。禮不諱嫌名、二名不偏諱。逮事父母則諱王父母、不逮事父母則不諱王父母。君所無私諱、大夫之所有公諱」とある「卒哭乃諱」が、父のみならず母の諱を含むことは文脈から明らかである。これに秦漢時代の女性(母親)の地位が後世に比べ相対的に高かったとする「母の原理」(山田勝芳[1997]・下倉渉[2001/2005])の指摘を合わせ考えるならば、後世の例とは異なるものの、秦代に皇帝の亡母の諱が避けられていた可能性は否定できないと考える。
[15]ただし関沮周家台秦簡の医学書に含まれる第344簡や、岳麓書院蔵秦簡『占夢書』第6・16簡などには「生」の使用例がある。また睡虎地秦簡でも、『日書』では「楚」字が避けられていない事実が早くから指摘されてきた。これらは、避諱が定められる(すなわち対象者が死去する)以前に書写された書物であったか、私的な蔵書のため書き換えが徹底されなかったものと考えられる。公的・私的な書物における避諱の別についてはMansvelt Beck[1987]、影山輝国[2005]、来国龍[2008]参照。
[16]例えば『史記』秦始皇本紀三十四年、李斯が焚書を進言した著名な言説中に「百姓」や「今諸生」などの語句が見える。こうした用字は、少なくとも当時の記録そのままではなかった可能性が高い。ただ、言うまでもなく用字例のみでこの言説自体の史料的価値を論ずるのは危険であろう。
【参考文献】
(日文)
・下倉渉「漢代の母と子」、『東北大学東洋史論集』第8集、2001年
同「秦漢姦淫罪雑考」、『東北学院大学論集(歴史学・地理学)』第39号、2005年
・鶴間和幸『秦の始皇帝—伝説と史実のはざま』(吉川弘文館、2001年)
・山田勝芳「中国古代の「家」と均分相続」、『東北アジア研究』第2号、1997年
(中文)
・白於藍編著『戦国秦漢簡帛古書通仮字彙纂』(福建人民出版社、2012年)
・陳松長「秦代避諱的新材料—岳麓書院藏秦簡中的一枚有関避諱令文略説」、武漢大学簡帛研究中心『簡帛罔』2009年10月20日
・陳偉主編『里耶秦簡牘校釈(第一巻)』(武漢大学出版、2012年)
・陳垣『史諱挙例』(中華書局、2012年版。初版1934年)
・胡平生「里耶秦簡8−455木方性質芻議」、『簡帛』第四輯、2009年
・邢義田「“手・半”・“曰啎曰荊”與“遷陵公”—里耶秦簡初讀之一」、武漢大学簡帛研究中心『簡帛罔』2012年5月7日
・来国龍「避諱字与出土秦漢簡帛的研究」、『簡帛研究2006』(廣西師範大学出版社、2008年)所収
・李学勤「秦簡的小文字学考察」、『雲夢秦簡研究』(中華書局、1981年)所収
・劉殿爵「秦諱初探—兼就諱字論古書中之重文」、『香港中文大学中国文化研究所学報』第19巻、1988年
・龐樸「馬王堆帛書解開了思孟五行説之謎—帛書《老子》甲本巻後古佚書之一的初歩研究」、『文物』1977年第10期
・王建『史諱辞典』(上海古籍出版社、2011年)
・影山輝国「関於漢代的避諱」、『簡帛研究2002、2003』(廣西師範大学出版社、2005年)所収
・游逸飛「里耶秦簡8−455號木方選釈」、『簡帛』第六輯、2011年
同「里耶秦簡8−455號木方補釈—《嶽麓書院藏秦簡[壹]》讀後」、武漢大学簡帛研究中心『簡帛罔』2012年2月15日
・張春龍・龍京沙「湘西里耶秦簡8−455號」、『簡帛』第四輯、2009年
(欧文)
・B.J. MANSVELT BECK, "The First Emperor's Taboo Character and The Three Day Reign of King Xiaowen: Two Moot Points raised by the Qin Chronicle unearthed in Shuihudi in 1975." T'oung Pao(通報)LXXIII, Leiden, 1987