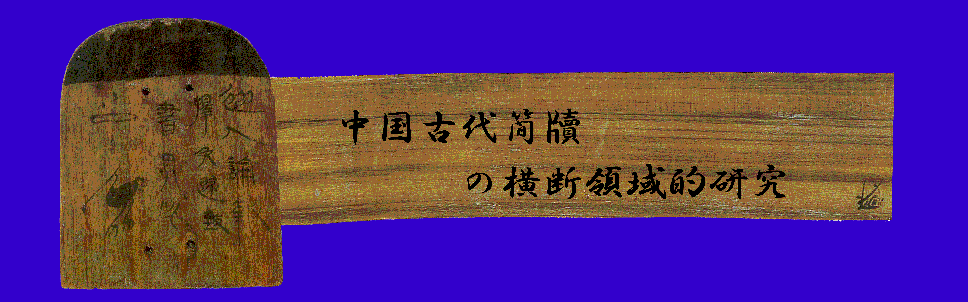「槎田歳更」小考
渡邉英幸(愛知教育大学)
里耶秦簡J1⑧355簡に次のような一文が見える。
・黔首習俗好本事不好末作其習俗槎田歲更以異中縣┃(8-355)
……黔首の習俗、本事を好みて末作を好まざるも、其の習俗は槎田歳更し、以て中県と異なれり。……
J1⑧1804にも「歲更以異中縣」と同文の一部が見えており、同じ内容の文章を記した簡牘が複数存在したことがうかがわれる。簡文はいずれかの土地の黔首の風俗習慣、とくに生業形態の地域的特質を論じており、恐らく中央ないし上級官府が特定地域の下級官府に与えた詔書や訓戒の一節であると考えられる。対象地域は不明であるが、当該簡が里耶から出土した事実は、洞庭郡がそこに含まれていた蓋然性の高いことを物語る。
簡文は、その某地の黔首(=百姓)が「本事」すなわち農耕を生業とする事実を肯定的に評価しつつも、それが「槎田歳更」なる形態をとり、「中縣」の地と異質であるとする。秦漢時代の地域的な生業形態に関する認識としては、著名な「火耕水耨」などを除けば、きわめて珍しい記述であるといえよう。当該簡は、画一的な「阡陌制」のイメージで捉えられがちな秦の農政が、ある程度の地域的特質を踏まえていたことを示している。
そこで問題となるのが「槎田歳更」という見慣れない表現である。農耕に関する何らかの習俗を意味した言葉であることは疑いないが、先秦・秦漢時代の伝世文献に確実な事例を認めることができない。陳偉主編[2012]は「一種耕作制度」と推定し、「槎田」を「斫木為田」、「歳更」を「毎年更替」の意味とする見解を提示している[1]。これは「槎」を「斫也」とする『国語』魯語上・韋昭注を根拠とした字義的解釈であり、「槎田」を切替畑の一種として理解したものと解されるが、具体的な根拠は示されていない。一方湖南省文物考古研究所が『簡帛網』に掲載した『里耶秦簡(壹)』出版の速報は、「槎田是當時使用較普遍的一種特殊耕作技術。“槎田”實際上是農田的休間制、“燔田(はでん)”是“槎田”之中不可缺少的一個歩驟、遷陵毎年春天有“燔田”活動」と、「槎田」が休閑地農法の一種であり、その中に「燔田」つまり焼畑耕作が含まれる、とする見解を載せている[2]。これは里耶現地の風土に通じた考古学者の認識であり、傾聴に値するが、やはり「槎田」と「燔田」との関連を示す明確な根拠が提示されていない。
では「槎田歳更」とは何を意味しているのであろうか。結論から言えば、「槎田」とは山地の斜面で毎年耕作地を替える伐採・焼畑農法であり、おもに唐宋時代の文献に見える「畬田(しゃでん)」に該当すると考える。「畬」には「よ・yu2、羊茹切」と「しゃ・she1、詩車切」の二音二義がある[3]。「畬(よ)」の方は『詩経』『易経』などの経書に見え、李根蟠氏によれば休閑地を設ける三圃制的農法の中で作付農地を指す呼称であったという。一方の「畬(しゃ)」は山地での焼畑を意味し、畬(シェ)族の呼称のもととなった概念である。このうち「槎田歳更」と関連が深いと考えられるのは後者の「畬(しゃ)」である。
「畬(しゃ)田」は毎歳移動しながら山の斜面の樹木を伐採し、雨期の直前に火を入れ、鎮火後に種を播き、余熱と灰の養分により作物の発育を促す焼畑農法である(史料d.)。こうした伐採を「刀耕」といい、火入れと播種を「火種」という。また毎年耕作地を新たに替える様を「毎歳易」「歳一易之」と称する(史料b.)。これらが「歳更」に相当する同義の表現であることは論を俟たない。すると「槎田」とはおそらく「刀耕」に相当する語句であり、火入れ前の樹木伐採に重きを置く表現であったと考えることができる。因みに日本の岐阜県白川郷では、同様の焼畑農法を「なぎ」「なぎ畑」と称するという[4]。
管見に入った焼き畑としての「畬田」の最古の事例は『華陽国志』南中志の記述であり(資料a.)、晉代の牂柯郡(現貴州省北部)の事例である。降って『旧唐書』にも東謝蛮の「畬田」の記事がある(史料b.)。また宋の范成大は巫山付近の三峡における「畬田」の有様を描写している(史料d.)。さらに『太平寰宇記』に瀘州(四川省瀘州市)や西高州(=珍州。貴州省正安県)で「畬田」が営まれていたとする記事がある(史料e.・f.)。いずれも長江以南、中国西南~東南部の山岳地方の事例[5]であり、秦代遷陵県においても、「刀耕火種」が行われていた可能性は高いのではないだろうか。
a. 牂柯郡。漢武帝元鼎六年開。屬縣、漢十七、戸六(二)萬。及晉、縣四、戸五千。去洛五千六百一十里。郡上値天井、故多雨潦。俗好鬼巫、多禁忌。畬(畲)山爲田、無蠶桑。頗尚學書、少威儀、多懦怯。寡畜産、雖有僮僕、方諸郡爲貧。
(『華陽国志』南中志・牂柯郡)
b. 土宜五穀、不以牛耕、但爲畬田、毎歳易。
(『旧唐書』南蛮西南蛮伝・東謝蛮。『新唐書』作「爲畬田、歳一易之」)。
c. 何處好畬田、團團縵山腹。 (劉禹錫「畬田行」)
d. 畬田、峽中刀耕火種之地也。春初斫山、衆木盡蹶、至當種時、伺有雨候、則前一夕火之、藉其灰以糞、明日雨作、乘熱土下種、即苗盛倍収。無雨反是。山多磽确、地力薄、則一再斫燒始可蓺。春種麥豆、作餅餌以度夏、秋則粟熟矣。官輸甚微、巫山民以収粟三百斛爲率、財用三四斛了二税、食三物以終年、雖平生不識秔稻、而未嘗苦飢。
(范成大「労畬耕」詩序。『范石湖集』巻十六)
e. 風俗。地無桑麻、毎歳畬田、刀耕火種。 (『太平寰宇記』劍南東道・瀘州)
f. 其縣並在州側近、或十里、或二十里、隨所畬田處爲寄理移轉、不定其所。
(同・江南西道・西高州)
編集者注記:2013年09月18日入稿
注
[1]陳偉主編[2012]136-137頁。
[2]湖南省文物考古研究所[2012]。
[3]大澤正昭[1987]が論ずるように「畬」には「よ(yu2)」・「しゃ(she1)」の二音二義があり、前者は『易』など儒家経典に記された開墾後数年の農地、後者はおもに唐宋期の文献に記された焼畑農法を指す。『説文』(十三下田部)は「畬、二歳治田也。『易』曰、不葘畬田。从田余聲。以諸切」と「よ」を解釈する。降って『廣韻』・『集韻』は「畬」の二音二義を載せる。『廣韻』は上平声魚部に「畬(よ)、田三歳也(一作二歳)」といい、同下平声麻部に「畬(しゃ)、燒榛種田。又音余」という。『集韻』も平声一魚部に「畬、説文、三歳治田也」、同平声三麻部に「畬、火種也」という。この二音二義につき、李根蟠[1982]は徐中舒[1955]の研究に基づき西周時代の「葘・新・畬」を論じ、三圃制的な休閑地を「葘」、作付一年目の農地を「新」、連作中の農地を「畬」といい、休閑・開墾に火を用いたことから後に「畬」が焼畑の意味を持つようになったとする。大澤正昭氏は「よ」と「しゃ」の二音二義を認めた上で、平地の開墾農地を意味する前者の先行性を指摘し、山地焼畑を意味する「しゃ」については「恐らく火を使って山地や荒地を切り開く開発方法と共通する形態をとるために、開墾して二(三)年目の田という意味の「畬」の字が自然に用いられたのだと思われる。(中略)開墾後の耕地の利用方式は当然異なっていた。繰り返し火を使い耕地を代えて移動する山地の焼畑方式と、定着して火を使わなくなる一般の農耕方式とでは、そのあり方に根本的な差異があることは言うまでもない。従って「畬(ヨ)」とは別の内容を示す語が必要となり、ここにシャの音が用いられるようになった」として、隋・唐代までに派生・定着したとする。一方、唐嘉弘[1983]・曾雄生[2005]・原田信男[2011]は、焼畑としての「畬」の事例を収集・整理している。また任乃強[1987]260頁は「畬」・「畲」が別字であったとし、焼畑を意味する『華陽国志』の本文を「畲」に作るべきとする。大澤氏が述べるように、山地焼畑「しゃ」は本来「畬(よ)」と別概念であり、後に同じ字で表現されるようになった可能性が高い。「槎」は『廣韻』では「畬(しゃ)」と同じく下平声麻部に分類されている。あるいは山地焼畑は本来「槎」で表現されていたものが、「畬(よ)」と混同され、「畬(しゃ)」という概念に落ち着いたのではないだろうか。
[4]江馬三枝子[1975]参照。
[5]大澤正昭[1987]では、文学作品を含めた唐宋時代の諸文献から「畬」の分布範囲と異民族(獠・蠻・氐・羌・山棚・山越)の分布とを図示・比較している。
【参考文献】(籾山明氏、村上陽子氏の教示を受けた):
・江馬三枝子「飛騨の焼畑」、『飛騨白川村〔新装版〕』(未来社、1975年)所収
・大澤正昭「唐宋時代の焼畑農業」、『唐宋変革期農業社会史研究』(汲古書院、1996年)、所収。初出1987年
・原田信男「中日火耕・焼畑史料考」、佐藤洋一郎監修、原田信男・鞍田崇編『焼畑の環境学—いま焼畑とは』(思文閣出版、2011年)所収
・フランチェスカ・ブレイ、古川久雄訳『中国農業史』(京都大学出版会、2007年)
・陳偉主編『里耶秦簡牘校釋(第一巻)』(武漢大学出版社、2012年)
・湖南省文物考古研究所「《里耶秦簡(壹)》出版」、武漢大学簡帛研究中心『簡帛網』「消息」2012年2月15日公表(http://www.bsm.org.cn/show_news.php?id=412)
・李根蟠「西周耕作制度簡論—兼評対“菑・新・畬”的各種解釈」、『文史』第15輯、1982年
・任乃強『華陽国志校補図注』(上海古籍出版社、1987年)
・唐嘉弘「“畬田制”及其社会形態初探」、『民族学研究』第5輯、1983年
・徐中舒「試論周代田制及其社会性質—並批判胡適井田辨観点和方法的錯誤」、『四川大学学報〔哲学社会科学版〕』1955年第2期。のち『徐中舒歴史論文選輯』上・下(中華書局、1998年)所収
・曾雄生「唐宋時期的畬田與畬田民族的歴史走向」、『古今農業』2005年第4期