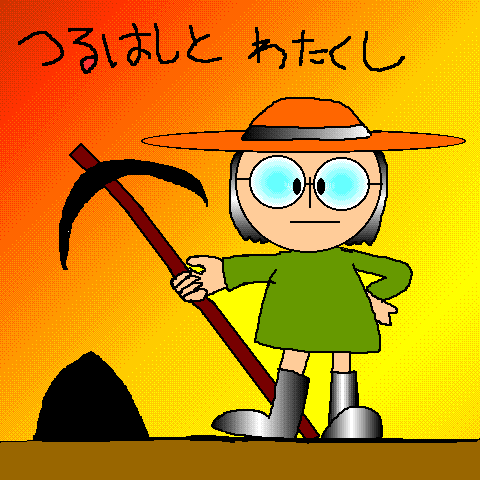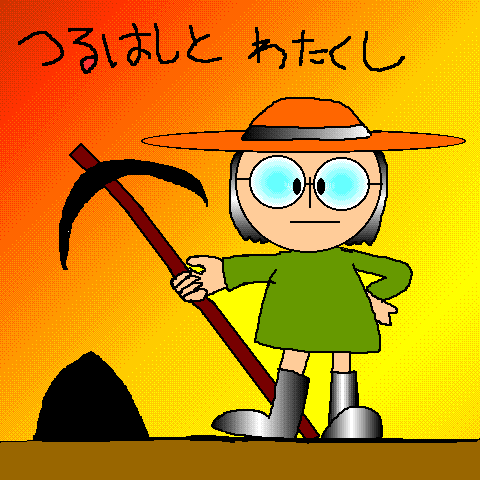平成10年度第1回研究会
日時:平成10年6月6日(土) 10:30〜17:00
6月7日(日) 11:00〜16:30
場所:AA研・セミナー室
プログラム;
第1日目(土)午前の部(10:30〜12:15)
この日の午後は、菊沢律子お姉さま率いる「統辞類型研究における他動態体系と能動態システム」というプロジェクトと共催で、次の2件の発表がありました。
- Mamadou Cisse:"Grammar and Grammaticalization"
- J. L. Diouf:"Predicate and Complemention in Wolof"
その後、懇親会があったらしいんですが...みんなそのことに関してはどういう訳か口をつぐむのでした。
第2日目(日)
- 砂野 幸稔:セネガルにおける「統一公用語」問題について:ダカールとジガンショールでの調査結果から
- 宮本 律子:トゥルカナ語(ケニヤ)調査報告
- 若狭 基道:ウォライタ語動詞の受身・相互動作を表す派生形
- 中野 曉雄:アフラジア語の疑問を示す形態・構文
- ロバート・ラトクリフ:What do 'phonemic' writing systems represent? Arabic, Kana, Roman and the Moraic Principle
- 榮谷 温子:
アラビア語ブハラ方言の限定名詞句のさわり(←アフリカ言語の研究会でウズベキスタンの発表をしたお姐さんの巻)
- 小森 淳子:ケレウェ語の女性語(しゅうと語)
平成10年度第2回研究会
- 日時:平成10年10月17日(土曜日)13:30から
- 場所:東京外国語大学AA研4Fセミナー室
- 発表者
中野暁雄「セム語における数としての文字」
- 文字に数値を振り当てるシステムは、世界中の人間がすぐに
考え付く、普遍的な現象。一般的なセム語の文字と、アラビア語の文字・数値との対比
で、その奇妙なビヘイビャーを観察。
松下周二「10進法 vs. 12進法」
- ナイジェリアのミドルベルトには、10進法と12進法をいったり
きたりする言語グループがある。その数値構造から、数と言語の関係を概観。
砂野幸稔「言語NGOの活動と言語政策;セネガルの言語数が増える」
- セネガルで活動するスーパーNGO、SIL (Summer Institute of
Linguistics) の、プライオリティー選択の矛盾を、傍目八目的に論ずる。
参加者(敬称略):中野、松下、砂野、柘植、ラトクリフ、フィリップス、塩田、米田、神谷、榮谷。
平成10年度第3回研究会
- 日時:平成11年2月20日(土)13:30から
- 場所:東京外国語大学AA研4Fセミナー室
- 発表者
1)宮本律子(秋田大学)
2)ロバート・ラトクリフ(東京外国語大学)
3)中野暁雄(所員)
4)小森淳子(大阪外国語大学)
5)塩田勝彦(無所属・元)
6)若狭基道(東京大学大学院)
その他参加者(敬称略):阿久津、岩本、加賀谷、神谷、榮谷、中村、日野、 松下、米田。
苦難と栄光の歴史のページにもどります
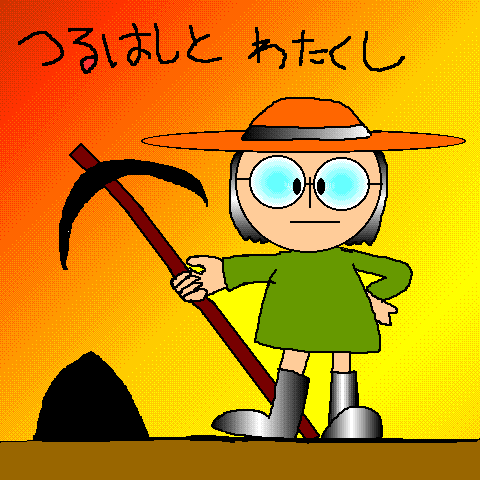
tkamiya@aa.tufs.ac.jp