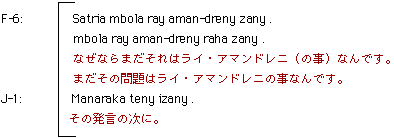
F-6:Mbola rizareo tsi'sy akeo eh . Tsi'sy akeo maloha rizareo eh .
Dady dia akao . Lôsoñô aby zoky re .
まだそこに彼等は居ないんです。彼等はそこに居ないんです。<祖母>はそこに居ます。
<姉>のところはみんな出かけているんです。
K-1: Avy raiky , mitikiny(1) aminahy ny teny .
Avy raiky , mitikiny aminahy ny teny .
ひとつ現れちゃあ、発言がわたしたちに積み重なる。
ひとつ現れちゃあ、発言がわたしたちに積み重なる。
Amboaronareo ka mbola hirana zany fô aleoko fa ・・・(2)・・・zany .
おまえたちでやりくりしてくれ。だってその(問題)はまだこじれているんだろ。だけど私は・・・(二語不明)・・・のほうがいい。
(1) 「跨る」・「乗る」の意のツィミヘティ方言( Faridanonana 1977 p.109 )。
|
L-1: Haibe, hitan'ny oloña manana marina sahala aminy
tsy marina , misy raiky voa foana eky(1) , misy raiky voa foana .
あれあれ、真実であっても真実ではないように人は見るだろう。一人は負けてばかり、一人は負けてばかり。
Na dikan'zany ? Avy nilefa , mitikiny aminahy , avy nilefa , mitikiny aminahy .
Sahala aminazy . Amboaronareo akao eh .
そういうことじゃないのかね?片づけりゃ私たちに積み重なり、片づけりゃ私たちに積み重なる。そういうことだ。そっちで何とかしとくれ。
(1) メリナ方言のreやlahyに相当する前後の語の意を強めるツィミヘティ方言の間投詞( Faridanonana 1977 p.27 )。
ヴリアの当初から恐らく参加者が共通に抱いていたにもかかわらず公然とは言い出しかねたこと、「おまえたち<家族>や<親族>の間のもめ事にすぎない事柄にわれわれを巻き込むのはいいかげんにしてくれ」の思いが、先の訴人の発話をきっかけに噴出した感がある。
|
G-7:Mbola manon-fo . Saingy anareo akeo zany tsy mitovy .
Saingy na mañao hafahafa .
依然として手に負えない。だが、おまえたちは、一緒ではない。(おまえたちは)べつべつのことをする。
Saingy mamaha akanjo rizareo roa lahy aroho(1) .
Saingy mitovy roa lahy izy roa .
(家でおまえたち)二人の男は服を脱ぐ。けれども、(おまえたち)二人の男は、一緒だ。
Izikoa raha amboaro na mety voalany hoana .
もし問題を(おまえたちが)やりくりすれば、解決するだろう。
(1) arohoもしくはaroy。メリナ方言のaryないしarikatraに相当するツィミヘティ方言で「向こうに」・「向こうで」の意の副詞( Faridanonana 1977 p.14 )。
|
| ここまでも何回も訴人とその弟や姉を含めた<家族>ないし<親族>同士での話し合いによる解決を主張してきた、ライ・アマンドレニの一人の発話である。訴人と弟との外に表れた違いを指摘した上で、それでも同母キョーダイとしての一体性を揺り動かすことは出来ない故に、一体性に基づいた話し合いによる解決を再度提唱している。
|
A-5: Anao mbola tsy tany mañao iny tsy tao Iadan'iPopy(1) iny ?
おまえは、まだ<ポーピのおやじ>のところでそのことをしていないだろ?
(1) テクノニームによる個人名。
|
G-8:Mo amboaro izikoa ambo- . Aleo olana teo hitatra
manamboatra raha io . Izy olon'draiky ?
ああ、できるならやりくりしてくれ。そのことをやりくりすることで先の問題が大きくなる方がまだいい。彼は、(おまえと)一体の人間だろう?
|
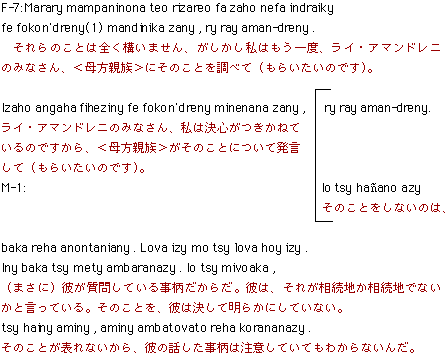
(1) fokon'drenyとは<母の親族>の意であり、これに対する<父の親族>はfokon'drayである。この訴人とその姉は母の母の出身村に住んでおり、したがって、この村のライ・アマンドレニは彼等から見て、<母方親族>に相当する。
|
| 訴人が繰り返し問題の土地が相続地であるのか否かについてのムラによる裁定を求めるのに対し、M-1で初めて<村長>がたまりかねたように訴人の発話が終わるのを待たずに発話している。水田や畑が相続地であるのか否かあるいは誰が拓いたものであり誰にその相続継承権があるのかという問題が、ムラないしヴリアの討議事項として馴染まないわけでは決してない。否、土地登記制度が完備されていない農村ではこのような土地問題を第一に討議し採決を与えるのは、多数の証人と目撃者としてのムラないしヴリアなのである。しかしその場合、一方の当事者ないし訴人の申し立てだけに基づいてムラやヴリアが採決を下すことはなく、必ずその土地に係わる当事者全員に意見陳述の機会が与えられ、両当事者や関係者全員の話を聴取した上で初めて採決となるのである。したがって、この事例に即して言えば、訴人のみならずその姉・<祖母>そして村内に住む弟、少なくともこの三人がヴリアの場に出席し問題についての意見を述べない限り、訴人の強い要請にも係わらずムラとして何かを決めるというわけにはゆかないことは当然である。<村長>の発話は、この点の原則を指摘している。
|
F-8: Mazava ho azy ny teny chef zany .
その<村長>の言は、当然です。
M-2: Ia . Ary koa fanontaniako leha(1) raha atolotranareo
leha ・・・(2)・・・tsy mety azony .
ああ。それから私の質問は、おまえたちが持ち出した事は・・・(二語不明)・・・彼女は決して承知していない。
Iny tsy ahazoana azy . Tokony ho azony .
それを、彼女は承知していない。彼女が承知するべきであろう。
Faharoa refirery aroy . Aroy tiany handalo hely
aminy sofinazy , lova na tsy lova . Io izy eh .
第二にはむこう側のことだ。向こう側では、相続地か相続地でないかについて彼女の耳にちょっといれてもらいたがっている。以上である。
(1) lehaは、メリナ方言aleha「行かせられる」のツィミへティ方言形( Richardson 1967(1885) p.387)。ここでは、fanontaniako lehaで「私が質問する」の意。
<村長>が、自己の役職の立場からこの件について知り得たことをここで、訴人に確認を求めている。すなわち、この相続地問題が当の訴人の姉には知らされずにムラとヴリアの場に訴人によって持ち出されているらしいとの点である。
|
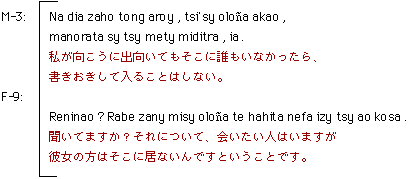
<村長>と訴人との同時発話になってしまっているが、両者の言い分は全く食い違ったままである。<村長>は、訴人以外の当事者に会っていないため姉たちがこの提訴の件を承知しているのかどうかいぶかしんでいるのに対し、訴人は<祖母>はこの件でいつでも証言することにやぶさかではないが今は村にいないと述べるだけで、提訴が当事者間の合意のもとになされたのかどうかについては言及していない。
|
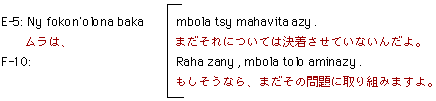
この会話の脈絡の中では、「相続地か否かはまだ討議中だ」と訴人に対し助け船を出すようなライ・アマンドレニの最年長者の発話を遮ってまで「私はまだやりますよ」と公言する訴人は、この後のヴリアの進行の中でさらに孤立無援となってゆく。
|
M-4: Ajano baka , tsy mifanaraka volañiny anareo ?
Sarotra baka zany .
止めてくれ、あなたたちは相互に喋れないのか?
本当に厄介なんだから。
Karaha dikany toy izy io . Hitanao , olon'draiky dia aroy , ry zoky .
それはまるでこの(問題の)意味のようだ。<兄さん>、
一人の人間が向こう側にいるのがおわかりでしょう。
<村長>が「あなた達は相互に喋れないのか」と発話した時、その非難の矛先が先に発話をしていたライ・アマンドレニの最年長男性に向けられていないことは明らかであり、人の発話が終わるのを待って喋るというツィミヘティ族の人々自身が認めている集会における「発話取りの順番」の初歩的規則さえ守ることのできない訴人の態度に、同じ<家族>や<親族>内での話し合いも尽くさずさらにはそのムラへの提訴も知らせずにきたことの問題の根源を求める発話が導き出される結果となっている。このことから<村長>は、この提訴が訴人以外の当事者の同意や周知なしに行われたことを、ヴリアの聴衆に納得させている。
|