G-2:Ambony zany karaha(1) eh . Aza atao sosotra be zany .
Mety ho biraiñy(2) izikoa raha ohatra mandamina .
その上にこんなことか。その問題をめちゃくちゃにしないでくれ。
たとえばよく調べれば、分割されるかもしれない。
Zandrinareo zareo roa lahy(3) . Tsi'sy hafa aminareo .
おまえのキョーダイは男一人だろ。
おまえの所には他にはいないじゃないか。
Mbola mamintana(4) izy akao.
(それに)弟はまだ釣りしている(ような年齢)じゃないか。
Amboaro raha tsy feno zavatra ,
miada:::adana mpaka sokon-tany(5) afa-baraka(6) tsika aketo
十分(話し合われていない)問題をやりくりしてくれ。
ここでわれわれが散会した後で、土地への接近をゆっくりと決めてくれ。
(1) 「〜と同じ」・「〜のような」の意のツィミヘティ方言で、メリナ方言のsahala・mitovy・tahaka・hoatra・toaに相当する( Faridanonana 1977 p.51 )。
(2) 「分ける」の意で、もともとは西に隣接するサカラヴァ方言に由来する( Faridanonana 1977 p.18 )。
(3) 訴人には、6人の年少同母キョーダイがいたが、この当時村内に居住していたのはその内の弟一人であった。この弟は、<祖母>であるMMFDの部屋に住んでいた。
(4) 実際には弟は17才くらいであり、「釣りをしている」年齢よりは上であったが、自分の土地を持って独立した生計を営んでいない中学生という点ではこの表現も不適切ではない。
(5) sokoは、「少しずつ近づく行為」の意( N.Rajaonarimanana 1995 p.266 )。したがって、sokon-tanyは、「土地に接近する(権利)」のこと。
(6) 「だめになった」・「死んだ」・「失敗した」の意のツィミヘティ方言( Faridanonana 1977 p.16 )。afa-barakaは、afaka baraka すなわち「だめになった後で」の意だが、ここの文脈では「散会した後で」の意である。
|
E-3:Tsika koraña teña efa baraka amin'izao .
私たちの話し合いも、ここですっかりだめになってしまった。
|
| ライ・アマンドレニ層の最年長男性の発言である。先の訴人の発話の呼応したものであり、口調は穏やかであるが、穏和な性格と村人に評せられるこの男性にしては厳しい内容の指摘である。
|
G-3:Amboarinareo aiza zany . Izany na dia tsy mañao kitrola(1)
tsy miakatra zany fa ia tara(2) mba amboaro . (4秒) Rabe zany -
しょうがないな、あなたたちでやりくりしてくれ。
争いや上訴にしないとしても、そう、時間かかっても
やりくりしてくれ。(4秒)そのことは−
(1) 「争い」や「衝突」を意味するツィミヘティ方言( Faridanonanan 1977 p.55 )。
(2) フランス語のtardに由来する単語。「遅れる」・「時間がかかる」の意。
|
F-4:Zaho-
私は−
G-4:Hainao ? Aza beky(1) maloha .
おわかりか?まだ待ってくれ。
Fanampiaña zany teny zany . Ekenao mo ny zandrinao
meñatra aminy tsary(2) nataony ao ny fitenenana zany ?
前に言ったことに言い足す(ことがある)。その問題について
おまえの弟が一度も発言していないことを
恥ずかしく思っていてもおまえは認めるのだな?
Ekehinao izany ataonao ny tsary miharo aminazy ?
Samby(3) tokony baka hiaro aminazy .
弟と一度も(話し)合っていないことでおまえはいいんだな?
Anao mbola tsary miharo aminazy .
Ekehinao zany fahatongavanao ?
みんな弟と(話し)合うべきだろ。
これまでのおまえのやったことでいいんだな?
(1) aza bekyで「まだ待って」・「待って」・「まだ止めて」の意のツィミヘティ方言( Faridanonana 1977 p.16 )。
(2) 「まだ〜していない」・「いまだかつて〜したことがない」の意のツィミヘティ方言( Faridanonana 1977 p.115 )。
(3) メリナ方言で「おのおの」・「めいめい」・「それぞれ」を意味するsamyのツィミヘティ方言における訛音形(Faridanonana 1977 p.98)。
|
| 訴人の発話を遮るように始められた先のライ・アマンドレニ層の一人の発話は、ここで訴人の同母弟とのこれまでの話し合いの経緯について向けられる。訴人は、件の土地争いがあたかも自分と姉との間だけの問題であるかのようにこれまで陳述してきたが、実は訴人にはまだ同母の年少キョーダイが当時少なくとも6人おり、その内の1人の弟が同じ村内それも同じ屋根の下に暮らしていたのである。仮にこの土地争いが、訴人の同母姉が耕作している土地が相続地であるのか否かという事柄であるならば、問題の当事者はひとり姉と訴人のみならず訴人の弟達も当然その内に加わってくることとなる。この発話者は、このことに言及することによって、<家族>ないし<親族>内での話し合いを尽くしもせずムラに事を提訴した訴人の手続きの性急さと身勝手さを、なじっているのである。
|
F-4:Izikoa raha tahakan'ny ampandaminana ,
tsi'sy zany hono zany . Safe nefa indraiky , miala tsiny hely zaho .
もし裁定者のみなさんの(言う)通りなら、(今まで)言った(問題)はないですよ。すなわち、もう一度お詫び申し上げます。
Zaho zany mbola tsy mahareñy teña na hely .
私はまだいささかの中身も聞いていません。
Tsy mahareñy teña zaho . Na lamba sikiniko tsy azoko .
[Oa lahe , hahaha(笑い)]Oa niny , oa::niny(1) ,
ry mandiniky miantoko .
私は中身を聞いていないんです。纏う布ほどにも得たものはないんです。(聴衆の笑い)ああ、<お母さん>・<お母さん>、裁定を司るみなさん。
Mbola misy ray aman-dreny zaho misy zoky
tsy mandidy manapaka raha zaho .
私にはまだ問題を決定してくれるライ・アマンドレニと<兄>がいるはずです。
Natao tanimboako ? Aza mandeha anao .
私の行き場はどうなったんです?みなさんそうしないでください。
Aza mandeha any anao niany(2) fa izany tsamboina
niany tô(3) mandeha anao . Tsy afaka aketo .
みなさんが今日ここで扱ったようにはしないでください。ここでは不可能です。
Ahan , teña fiheziñy . Safe zaho mbola tsy mahaleo tenany
hely aby(4) zaho.[hahaha(笑い)] Izaho tsy hiala dady eh .
いや、とても迷っています。すなわち、私はまだいささかも自立していないんですよ(聴衆の笑い)。<お父さん>、私は(提訴から)降りませんよ。
(1) メリナ方言のreny<母>もしくはneny<お母さん>に相当するツィミヘティ方言( Faridanonana 1977 p.83 )。この時のヴリアには女性は参加していなかったため奇異な感じを与える呼びかけであるが、ライ・アマンドレニとは<チチとハハ>が直接の意味であること、ツィミヘティ族にあっては強い依頼や請願を相手に込める際には<お母さん>と呼びかけること、訴人にとってこの村のライ・アマンドレニは大半が母方親族にあたること、この三点から、訴人が男性ばかりの聴衆に対してもこの呼称を用いたものと考えることができる。
(2) 「今日」の意のツィミヘティ方言( Faridanonana 1977 p.83 )。
(3) 「本当に」・「嘘偽りなく」の意のツィミヘティ方言 ( Faridanonana 1977 p.110 )。したがって、niany toとは、「まさに本日」の意。
(4) 「全て」・「みんな」の意のツィミヘティ方言( Faridanonana 1977 p.8 )。
|
| ここでも、<お父さん>・<お母さん>・<兄>というライ・アマンドレニの年長者に対し年少者である自分の位置づけを確認する関係名称の多用、あるいは「裁定する(人)」・「決定する(人)」・「調停する(人)」というライ・アマンドレニたちの役割と権限を承認する単語の汎用が訴人によって行われる一方、それらの事柄を真っ向から否定する訴人の「私はこの提訴を取り下げない」との意志表明が行われるという矛盾した構図が繰り返されている。そのことがこのヴリアの場にどのような反応をもたらしていたかは、訴人が自己の窮状を訴えるレトリックを用いた時、その場の聴衆が(笑い)をもって応えたことに集約されている。さらに訴人は、「もう一度姉や弟たちを交え自分たちで話し合いなさい」との「裁定」や「調停」を「それは自分がムラに求めた裁定の内容ではない」とはねつけており、訴人の言う「裁定」や「調停」の中身や実質とは姉が耕作している土地は相続地であり自分に対して分割されなければならないとの「勝訴」に他ならないことは明白である。ここに、ムラが成立する共同性の余地はいささかもない。
|
G-5:Reninao ? Tandrenesa hely indraiky eh .
聞いているかい?もう一度ちょっと聞いてくれ。
Ary dady baka milaza hoe , “ ny zokinao mbola tsy akeo ”.
じゃあ、<おばあさん>が「おまえの姉はまだそこにはいない」と言っているのかね?
E-4:Ia , mandeha miasa izy . Avy zany avakeo na mandeha atoy ,
mangataka . Te hanao avelao toy izikeo .
そうだ、彼女は仕事に出ているんだね。(彼女が)戻ったらあるいはここに来たら、頼んでみたらどうかね。(私は)それからこのことを処置して欲しい。
Ankiraiñy (1) dadinao akeo zany , izy mangataka aminao .
Anao zany olona tsary angahoaña .
おまえの<祖母>がそこに残されたままだが、彼女はおまえにお願いする(かもしれない)。おまえという人間は一度だってお願いされたことがないじゃないか。
Afaka zany , izy anatony sa tsy afaka , hoy zaho .
それで終わりだ、彼女を加えるのかいそれともそうはできないのかい、そう私は訊ねる。
(1) 「終わっていない」・「尽くされていない」・「残す」の意のツィミヘティ方言( Faridanonana 1977 p.12 )。語根は、「食事の残り」を意味するankera。ここを直訳すれば、「おまえの<祖母>はそこでは残されている」である。
<祖母>の言をこの土地問題に対する最大の拠り所とする訴人に、ライ・アマンドレニの最年長者が、その<祖母>が何と言うかに委ねることを訴人に迫っている。
|
(4秒)
F-5:Afaka . Nefa indraiky [ee , ee (1)(非難の間投詞)]
mbola tsy akeo hely , ray aman-dreny ,
できます。けれどもう一度[ee , ee (非難の間投詞詞)]
ライ・アマンドレニのみなさん、まだそこには(<祖母>は)いないのです、
fa fa・fanontaniaña amba・anontaniako fokon'olona maloha .
Lova vilono fô(2) tsy lova ?
それでし・質問、ムラに先ず私はし・質問します。
畑は相続地なのですかそれとも相続地ではないのですか?
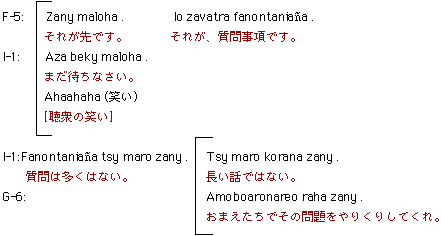
Tsy afaka hamakafaka raha zany maloha .
先にその問題について質問することはできない。
Amboaronareo oh mbola zany .
まだ、おまえたちでそれをやりくりしなさい。
Satria re tsi'sy sôsotra manamboatra sôsotra izay toy andro
hafa na dia toy mbola hikajina ahidin'manamboatra .
なぜなら、争いが無いすなわち争いをやりくりすれば、
また他の日にもまだやりくりの鍵は手にあるからだ。
Amboaronareo maloha raha zany .
先ず、おまえたちでその問題をやりくりしなさい。
(1) 例えば、赤ん坊や幼児が禁止されるような事柄や危険なことに手を出そうとした時に、親がその行動を制止するために発する間投詞。ここでは、訴人の発話そのものを制するような、非難の意味が強い。
(2) メリナ方言の逆接の接続詞faのツィミヘティ方言における訛音形( Faridanonana 1977 p.32 )。
|
| 4秒の沈黙の後、訴人が口を開き、先の年長者の質問に対して「それはできます」と答えた時、ヴリアの聴衆には「これでこの一件も落着したな」との思いが脳裏をかすめたことであろう。しかし訴人は、すぐさま逆接の接続詞を用いて言葉を接いだのである。4秒の沈黙の間が、訴人によるライ・アマンドレニとムラの「裁定」ないし「助言」を受け入れ決心するための準備時間であったとの聴衆の期待と安堵は、続く二語によって簡単に覆されたわけであり、その覆された思いが、ee , ee という人の行動を制する時に発する間投詞の期せざる唱和となって表れている。それにもかかわらずその後の訴人の発話内容は、それまでに述べられたこととなんら変わるものではなく、ライ・アマンドレニからも再び同じ忠告、すなわち「自分たちでこの問題を何とかしなさい」が発せられることとなったことは当然の成り行きである。
|