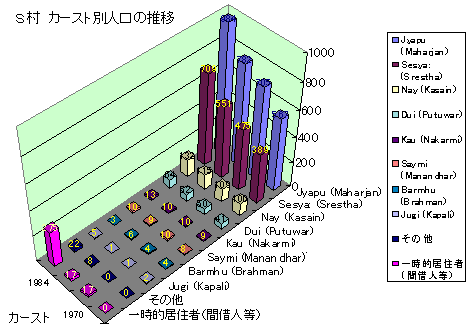
| 2.3. カースト別人口 |
| 2.3.1ネワール調査村(S村) |
|
|
|
|
|
|
| Barmhu (Brahman) |
|
|
|
|
| Sesya: (Srestha) |
|
|
|
|
| Jyapu (Maharjan) |
|
|
|
|
| Dui (Putuwar) |
|
|
|
|
| Kau (Nakarmi) |
|
|
|
|
| Saymi (Manandhar) |
|
|
|
|
| Nay (Kasain) |
|
|
|
|
| Jugi (Kapali) |
|
|
|
|
| その他 |
|
|
|
|
| 一時的居住者(間借人等) |
|
|
|
|
| 合計 |
|
|
|
|
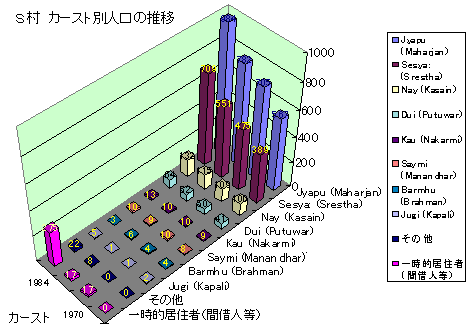
| このグラフで見るように、シェショ、ジャプなど人口の多い上中位カーストは人口の増加が著しい。一方でカウやサェミといった人数の少ない(10人以下の)中位以下のカーストの人口はあまり変化していない。カースト社会においては、階級社会と異なり、一握りの上層部が他の大多数の人々を支配するのではなく、上位カーストがかなりの人数を占めるということは、すでに指摘されてきているところであるが、ここで扱う3村落もその例に漏れない。ただしS村では、最上位のバルム(Brahman)は儀礼を行うために他村から招かれて住み着くようになったものであり、村内では人口から見ても社会的影響力の面でも力はごく限られ、上位カーストのシェショ、および中位カーストのジャプが拮抗する形で村社会を牛耳っている。それらのカーストは人口において卓越するのみならず人口増加面でも他をしのいでいることがここに見てとれる。この状態はマイノリティ・カーストと彼らの間の懸隔を(少なくとも人口面においては)広げていく効果を持つものである。しかも、近年において人口が大きな要素となる選挙の重要性がますます高まってきていることを考えれば、これは単に人口面での差異にとどまらず、政治社会面での力の差に直結するものであるといえる。その意味で、ここに見るような人口動態は、マイノリティ・カーストにとって不利な方向を示していると考えられる。
1984年から1996年に至る間には一時的居住者の急激な増加があったことが示されている。これは村内に出稼ぎ労働者が流入してきたためであるが、労働者を引きつける要素となっている工場の進出などについては別の場所で詳述する。なお、これらの人々は従来の住民の住居に間借りしたり、村人が出稼ぎ労働者に部屋を貸すために新しく建てた建物に住み、近くの工場などに勤めている。一般的に、村民との交流は少なく、また人口の出入りも頻繁である。 |
| 2.3.2 B村(パルバテ・ヒンドゥー) |
|
||||||||||||||||||
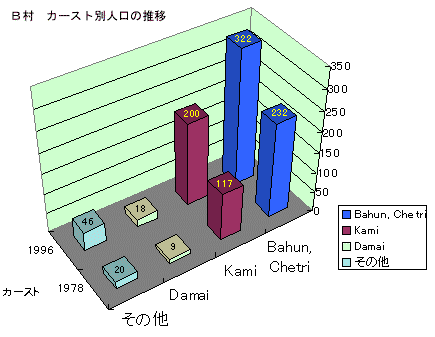 |
| ここでは、上で述べたように最上位カーストのバウンが圧倒的に多い。一方、下位カーストで従来不可触とされたカミもかなりの人口をもち、2時点間でのその増加の程度はバウンのそれをしのいでいる。これはカミの人々がそのカースト的職業の枠内で新しい技術(銅器製作・修理技術)を習得し、しかもその仕事を村内において行うという可能性が1980年代中葉から出てきたことに関連すると解釈される。その職業面での動きや顧客側の需要に関しては、別のところで詳述する。
(なお、バウン−チェトリとひとまとめにしたのは、カースト間婚などを理由として同じ一族でありながらバウンからチェトリに降下した人の子孫であるチェトリの人口が少数あり、ここではそれらの例を一括して扱うのが適当と考えたからである。) 人数の少ない下位カースト(やはり従来不可触とされていた)ダマイの人口もかなりの程度の増加を見ている。これも、上位カーストの農業生産の増大を含むB村全体の経済状態の上昇と関連すると考えられる。雑多なカーストを含む「その他」は、18年の間に2倍半程度増えている。これは流入人口によるところが多いが、それもまた農業生産の増大に関わっている。 |
| 2.3.3 G村(ミティラー) |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
| Brahman |
|
|
|
|
| Bhumihar |
|
|
|
|
| Kayastha |
|
|
|
|
| Dhanuk |
|
|
|
|
| Sudi |
|
|
|
|
| Haluwai |
|
|
|
|
| Hazam |
|
|
|
|
| Lohar |
|
|
|
|
| Bin |
|
|
|
|
| Tatma |
|
|
|
|
| 計 |
|
|
|
|
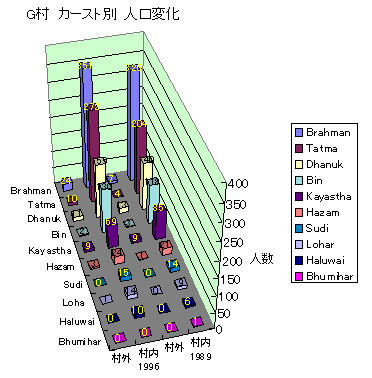
| G村では村外で就業したり、学校に通うために一時的に村の外に居住している人口がかなり見られる。ここでは、それらの人々を「世帯内村外者」として扱い、表やグラフでは「村外」として表示することにする。
最上位カーストのブラーマンでは、村内居住者の人口増加はそれほど顕著ではないが、世帯内村外者の割合が高くなっている。これは学校に通っている人口よりもむしろ村外で職を見つけてそこに住んでいる人が多いことによる。これらの人々には、家計を担う男子(日本の場合の世帯主に相当するような人)が単身赴任している例がかなり多い。 上位カーストであってもカーヤスタの場合は、上記2村と異なり、村内居住者人口も「村外」人口も減少している。カーヤスタには比較的高学歴の人が多いが、そのような人が村外に職を見つけ帰ってこない例がかなりあることがこの現象の原因となっている。 他方、スンディ、ハルワーイー、ロハール、ハザームといった人口の少ないカーストでは、上記2村と同じような傾向が見られるが、下位カーストであっても人数の多いタトマーは、村内居住者人口が著しく伸びている。一方で、タトマーの次に人口の多いビーンは人口全体の増加もそれほどなく、「村外」人口は減少している。 このような人口の動きは部分的には村人にも意識されており、ブラーマンの男性が近頃タトマーが力を得てきたと警戒するような口調で話しているのを聞いたことがある。このような点についてはさらに職業、教育、村内社会関係等々を検討するところで考察することとし、ここでは傾向の指摘にとどめておきたい。 |
copyright (C)
石井 溥:hishii@aa.tufs.ac.jp
1999-
All Rights Reserved.