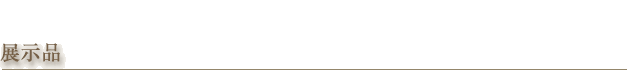 |
||||||
 [作品28]
[作品28]■カンダハール市――大バーザールと城塞 City of Candahar: Its princilpal Bazar and Citadel (英語原文をよむ) この絵が描かれたのはナッカーラ・ハーナのテラスからであるが、これは国王の楽隊が演奏をする部屋のことである。この部屋は町のちょうど中央、チャールスーと呼ばれるドームを持った建物の中に位置しており、その下には布告や公式な命令書が読み上げられる屋根付きの空間がある。そこでは、武器や本、カラムダーン (筆入れ)などあらゆる種類のペルシアの品物や商品にできる最高の店々がある。またそこは罪人の四肢や首、胴体を衆目にさらすために吊り下げられる場所でもある。町のこの一角よりその音色を響かせる、荒々しい、耳をつんざくような、この世のものとは思えない陛下の楽隊を凌ぎうるものはないだろう。演奏者たちは、ただ三つか四つの音色を決まった順序で繰り返し、12もの耳をつんざくような太鼓や、不協和音を奏でる角笛、耳障りなラッパで、聞くに堪えない低音からがなりたてるような高音まで演奏するのみである。そのメロディーはすべて「シャー・シュジャー、シャーー・シュジャー」という繰り返しである。 ■ナッカーラとの出会い 最初に私の耳をこの野蛮な旋律で楽しませたのは、シャーの冬宮のあるジャラーラーバードの、雪深い朝まだきであった。それは突然、不愉快なほど近くで鳴り響いたため(雪やテント、毛皮や寝具などでいくらか和らげられはしたものの)、私は朝の1杯の紅茶の前に宿主を起こさざるを得なくなったが、彼は私を慰めるつもりで最悪のことを言った。彼は、あれが王の唯一の一流のオーケストラであると述べ、さらに、私が十分長生きすれはああいったものにたくさん出くわすであろうと言って私を慰めたのである。まことにアフガン人たちの精神には音楽というものがない。いくら彼らがその喋るラッパの音に、音楽があると思いこんでいてもである。とはいえ、私は1度、11人のアフガン人がジャグダラクの木立の中でギターをかなりうまく弾いていたのを聞いたことはあるが。シャー自身も、楽器のそろった軍楽隊の一つの演奏を鑑賞すべく招待された際、すばらしかった(フーブ・ブード )が、音楽を「話す」彼自身の楽隊とはとても比較にならないと述べた。ナッカーラの発する音の響きは周囲何マイルにもわたって君主や貴人の入場・退場を伝えるが、同時に1日のうちの区切りを知らせる役割も果たしている。夜明け、正午、真夜中に演奏が行われる。最後の演奏の時間かから朝の演奏まで、投獄や罰金刑の覚悟がなければ、何者も街路に出ることはできない。 ■カンダハールのバーザール チャールスーのこちら側から城砦に向かって延びているバーザールは、常に陽気で、込み合っており、絶えず違う光景を見せている。正午からは野性的な部族や人々によって窒息するほどに混雑する。彼らは、彼らが買い込んでいる商品と同じくらい種々雑多で風変わりである。高みから見下ろすと、巨大なターバンや絹や亜麻を巻いたもので覆われた幾千もの頭、「また、武器の煌く輝き」(東洋におけるすべての武器がある)「蝶のように鮮やかな、染色された衣装のさまざまな染め色」[Byron, Don Juan, Canto III]が、華麗で珍しい印象を作り出していた。砂糖菓子、氷、青い陶器、土器、刃物、毛皮、髭剃りの店の間に、珍しい種類の美味しそうな果実が、よく熟れて、家々の天井から吊り下げられたり、通りの露台に積み上げられたりしているのが見られた。ザクロ、メロン、イチジクや「バッカス神の贅沢さで地面に垂れ、紫色にほとばしる、瑞々しいブドウ」[Byron, Don Juan, Canto I]が、東洋のバーザールにしては幅広で立派な通りの両側、考えうる限りの多種多様さを持つ品物の間を、注意深く層状にして並べてあった。 ■「聖遺物」のモスク 我々がチャールスーから城砦へ通り抜けていく間、我々の左手に連なる建物は高くそびえ広々としており、その磨かれた丸屋根と「太陽に輝く白壁」[Byron, Don Juan, Canto III]は、木枠に赤い生の粘土で建てられた家々と心地よい対照を成している。これはモスクであり、なかには預言者の衣服を安置しているために、神聖視されている。この聖遺物は我々が大いに注意を払って警護している。なぜかというと、ドゥッラーニー部の位の高い貴人であるアター・ムハンマドが、ファランギー[ヨーロッパ人]との聖戦のため、みずからの狂信的な軍隊を鼓舞するための旗印として利用すべく、それを盗もうとしてほとんど成功しかけたからである。建物の内部はほかのマスジドのそれといくらか似ている。その壁はクルアーンの章句によって覆われている――「柔らかきペルシアの文は薄紫色の文字にして、秀でたる詩人や道学者より」[Byron, Don Juan, Canto III] 。城砦と塁壁の向こう側は山並みによって仕切られた平原である。その山々のごつごつとした輪郭は城壁の上から顔を出している。その名前はコータレ・ムールチャ、すなわち蟻の通路というが、実に適切な名である。この名前は山々の中を通る隘路から来ているが、この隘路は非常に狭くて切り立っているため、この直立した山腹の間をつぶされずに通り、向こう側の渓谷へ抜けようと望む騎手たちは下馬する必要がある。この城塞の前面には我々の軍需品置き場の区画がある。もし3月10日夜、攻め手のよく計画された攻撃が成功していたならば、我々はチャールスーからヘラート門に通じる街路を掃討するために18ポンド砲2門をチャールスーの入り口に引いて行き、最後の抗戦を試みるためにここで整列することになったであろう。ここではまた、ドゥッラーニー部の長であったアクラム・ハーンが大砲の砲口から吹き飛ばされた。この無実の、少なくとも自身の国と守護神のために戦ったという以外にいかなる罪も犯していないこの男に対してなされたこの残虐な刑罰を思い起こす時、我々は心にむかつきを覚えるのである。 ■ディームール・ミールザー カンダハールは王家の居住地であり、シャー・シュジャーの長子であるティームールが名目上の総督として居住していた。私はしばしば、彼を表敬訪問したものである。殿下は堂々としており、厳粛な顔つきをした非常に尊敬に値する人物で、内向的で学問を好み、厳格なマホメット[イスラ−ム]教徒らしい性質を備えていた。さらに彼は1人の妻しか持たず、王家の華やかさや気苦労よりも静寂と隠遁を好んだ。彼の挨拶の言葉は快く王侯にふさわしいもので、それを語る深く豊かな声は、オリーブ色の肌を持つ容貌や長く黒い顎髭同様にその父によく似ている(その軽蔑に満ちた表情は受け継いでいないが)。彼こそ王家の貴人の典型である。彼が庭園の中、さまざまな野鳥に囲まれた水源から水を引いた泉の傍らに座っているのを、我々はよく見たものである。庭園の周囲には歩道や花壇が、こぎれいながらも古風な趣のある仕方で配置されていた。私が最後に彼を訪問したとき、彼は書物を手にお気に入りの場所に座っており、その周りでは彼の息子たち、鮮やかな赤い頬と黒い目をした2人の美しい少年たち(彼は我々に、我々には至極当然のことに思われたが、彼らが学問的探求よりも乗馬や野外の運動を好むと不平をもらしていた)が遊んでいた。小さな腕白小僧たちは剣と短刀で完全武装していた。無論、彼らも父のミニチュアの服装を身に着けていたが、冠の代わりに成人用のターバンを身に付けている点が違っていた。王子は、薄紫色のサテン製の上着と、白いカシミールのショールの帯で盛装していた。頭には、マルタゴン・ユリの形をした黒いビロードの帽子をかぶっていたが、それには宝石のはめ込まれた黄金の帯がついており、また冠から垂れ下がる4枚の葉にエメラルドの下飾りが付いていた。彼は落ち着きを払いつつも悲痛な面持ちで、変わってしまった彼の運勢について語った。彼は父の殺害の報と、我々がこの国を退去する予定であるという報告を聞いたばかりであった。我々が御前から退出する時、彼のナッカーラが演奏した。その太鼓は、失墜する権力への弔鐘であった。 ■王立第40連隊 カンダハールの話題に別れを告げるに当たり、私はかの地の兵舎での生活に関するたくさんの幸せな記憶の中の一つを語らないわけにはいかない―私は、この出来事については、きっと全軍の人が私と同じように喜んで反応するであろうと思う。それは、我々の小規模な兵力に、王立第40歩兵連隊が加わったことである。この連隊は閲兵場でも戦場でも、また私的な生活におけるより社会的な務めにおいても、よい連隊といえるものであった。連隊としては常にすばらしい秩序と規律を保っていたが、将校たちは1人1人がもてなし好きで紳士的で愛想がよかった。食堂や露営地での我々の会合は実に楽しかった。あの興奮した時代から、多くの者がこの世を去ってしまったと付け加えなければならないことを、私は大変残念に思う。その仲でも特に私は自らの2人の友人、ヒバート大佐とセイモア中尉の死を悼むものである。しかしながら、私は勇敢なる生存者たちが、彼らのあまたの美点に対する私の拙い賛辞をそのまま親切に受け止めてくれるであろうことを信じる。 ■アフガン人のヘブライ起源説 この章の最後は、アフガン人が民族的に主張しているヘブライ人との血統的つながりについて、2、3の言及を適当に取り上げて締めくくろうと思う。私の立場でこのような難解かつ複雑な分野にあえて立ち入ることは、非常に僭越であろうとは承知している。当世の最も学識深い学者たちの何人かによって繰り返し議論されている事柄に触れるなどというのは、なおのことである。しかも、彼らの本当の起源や、彼らが自称するところの、失われた10部族に遡ると主張するその血筋に基づくバニー・イスラーイール、イスラエルの子らという称号について、疑いもなく確証されていることは何もないのである。このような仮説を押し進める新しい何かを私が持っているわけでもない。ただ私は、アフガン人たち自身や私の類まれな友人であるブリュー大尉(学識深い東洋学者であり、インドの生活を描いた『あるグリフィン[新参者]の回想』という題名の魅力的な作品[1843年刊]の才能ある著者)から自分が聞き取ったことについて述べたい。そして、私自身の個人的観察から、アフガン人の風俗、習慣のいくつかが、彼らの想定されている先祖と似通っている点を述べてみようと思うだけである。 ■ヘブライとの共通性 アフガン人(ところで、この呼称は彼ら自身によって承認されているものではなく、ペルシア語に起源を持つものである――パシュトゥーンというのが彼らの国に対する彼ら自身の名称である)の容貌、伝承、系譜すべてが、ぼんやりとあいまいにではあるが、彼らが古代イスラエル人に起源を持つ者たちであるということを証明している。しかしながら、アッシリア王シャルマネセル によって連れ去られ、我々の知っているところではそのまま東方に留まった10部族に直接起源をもっているのか、バビロンにおいて捕囚[紀元前597もしくは586年]となっていたユダヤ人に起源をもっているのかというのは、容易に確定できる点ではない。アッシリアの王によって打倒されたのがイスラエルの王国であり、またアフガン人が自分たち自身をバニー・イスラーイールと呼んでいることから、私は前者の仮説を採用したい気がする。しかし、それに対する反証として、彼らの伝承のうち一つが、彼らをソロモンの宰相アーサフのいとこであるアフガーナの子孫であると記述し、彼の後裔はバビロン捕囚後、一部がアフガニスタンのゴールの山々(パロパミサス山脈の境界線の内側)へ、一部がアラビアのメッカへと落ち延びたとしていることに触れておこう。(しかしながら、彼らがアフガーナまでみずからの起源をたどっておきながら、アフガンという名前を認めないのは奇妙である)。しかし彼らは、致命的な侮辱とみなされている呼称であるヤフーディー 、すなわちユダヤ人という名前が自分たちに当てられるということを承知の上で、自らのヘブライの血統だと認めようとしているのだ。なぜなら彼らは、もっと新しい時代のユダヤ人や、未だにアブラハムの信仰を保持している者たちを、この上ない軽蔑と憎悪とを持って遇しているからである。これは、次の二つの理由のうち一つに由来するのであろう。彼らが救世主イエス・キリストを十字架に掛けた者たちの子孫であるということ。偉大なる預言者として、そして(彼らの主張するところによれば)聖霊もしくは助け主であるマホメット[ムハンマド]の先達者として、彼らは彼をハズラト・イーサーと呼んで大いに尊崇している。あるいは、こちらの方がずっとありうることであるが、メッカのユダヤ人たちの多くが勃興しつつあったイスラームの宗教に対する頑強な抵抗者であり、その創設者の憎き敵であったという事実。最後の事柄に関する伝承は失われてしまったかもしれないが、その伝承に基づく敵意は生き残っているのである。 ■アフガン人の言語 アフガン人たちの言語は周辺の民族のものと本質的に異なっており、パシュトゥーン[パシュトー]と呼ばれる。おそらく、インドにおいて知られている彼らの名であるパターンは、これに由来しているのであろう。また、パシュトーというのがシリア語の古代方言のひとつに由来する名前であると信じるに足る強い根拠も存在する。聖書に記されている族長時代に特有の奇妙な慣行の多くは、長きにわたって、稀に発見されるが、未だに探し求められているイスラエルの10部族の子孫を自称するこれらの人々の間に広く行き渡っている。彼らの牧畜的生活習慣は、聖書にアブラハムとその子孫のものとして叙述されているものと同じである。口輪をはずされた雄牛が穀物を踏みしだいて穀粒に脱穀するのである。彼らは血統を誇りとしている。そして、もし1人の男に誰の息子か尋ねたら、彼はノアに至る家系を指折り数えるのである。ところで、ノアの父レメクの霊廟はジャラーラーバードの郊外にあり、彼らはお気に入りの参詣場所として足繁く通っている。モーセの法に従い、兄の未亡人を弟が娶るということも、彼らによって守られている慣習である。このことの確証となる事実として、ドースト・ムハンマド・ハーン自身がA・バーンズ士爵とのアフガン人の血統に関する会話のなかで述べた言葉を挙げておこう(バーンズの1836−38年のカーブル旅行記[1842年刊]を見よ)。「我々は兄弟の妻を娶り、娘に財産を残さない。これでも我々はイスラエルの子ではないというのか。」 ■投石による処刑 アフガン人は神への冒涜に対しては投石による処刑を行なう。預言者に対するこの不信心の廉で有罪とされた者はバーラー・ヒサールの外、シャーの牧草地にある丘に連れて行かれる。最近、ここであるユダヤ人がイエスの名を冒涜したために処刑された。アフガン人はノアの箱舟が大洪水の間ジャラーラーバードの北方クナルの山並みの中にある高い丘と、サフィードコーフ(白い山、万年雪に覆われていることから)の近くにあるスライマーン山脈の最高峰に載っていたと信じており、彼らはそこをタフテ・スライマーン(ソロモンの玉座)と呼んでいる。 |


