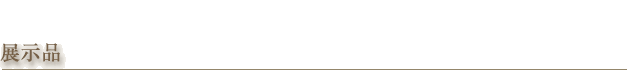 |
||||||
 [作品19]
[作品19]■ドースト・ムハンマドの四男グラーム・ハイダル・ハーン Ghoolaum Hyder Khaun, fourth son of Dost Mahommed Khaun (英語原文をよむ) 1839年7月のガズニー占領に続く最も重要な出来事の一つで、ガズニーの降服以後最も望まれたことは、カーブルのアミール・ドースト・ムハンマド4番目の息子である、ガズニー総督の王子グラーム・ハイダル・ハーンの拘束であった。報告によれば、豪華な衣装をまとった男が、我々の見せかけの攻撃の砲火の音を城塞の南側から聞いて、馬に乗ってそちらに向かったところが見られている。我々が都市のカーブル門から入ってきたことに気がつくと、バーラー・ヒサールに(逃げる際にカマルバンド[腰帯]に弾を受けながら)駆け上がったという。この時点から彼は行方不明になった。後で、1600人ほどここで捕えられた捕虜の何人かを尋問したが、全員が一致して殿下は逃走したのだと主張した。この話は本部では完全に信じられ、それ以上のことは状況からみても考えられていなかった。しかし、ガズニーの占領後直ちにその司令官となったロバーツ准将は、捕虜の告白の信憑性に疑問を感じた。また、当然のことながら、総督としてこれほど価値のある獲物を確保したいと熱望していたので、最も厳しい尋問に取りかかった。彼は、すぐあとで、彼の副官であるテイラー大尉の登場を喜んだ。彼は、1頭の美しい馬が、刺繍を施された覆いで豪華に飾られ、ホルスターときれいなピストルを積んでいることに准将の注意を向け、城塞から外へ出る許可を求められている(許可を求めているのは誰でしょうか)と言ったのである。このことが、ますます、准将の獲物は逃げ出していないのではないかという疑いを増した。彼はこの許可をあたえなかったばかりか、ただちに、彼の副官を第16精鋭歩兵部隊とともに派遣し、その馬が連れ出された家を包囲した。それから、彼は何人かのアフガン人にその件について尋ねたが、彼らの答えはさらにハイダルが城壁内にいるという確信を強めるものだった。マクグレガー少佐はたまたま居合わせたが、部隊に同行することを申し出た。彼は熟達したペルシア学者だったので、彼の申し出はすぐに受け入れられた。 ■王子の発見 建物内は捜索され、そして王子は発見された。彼は忠実な支持者たちによる強力な小部隊に囲まれていたが、彼らは降伏よりも先に手にした剣で死ぬと誓っていた。というのは、彼らは、シャー・シュジャーが彼らに対して慈悲を示さないことを確信していたのである。マクグレガーの投降の説得は困難を極めた。彼は、コーランにかけた最も厳粛な誓い(カサム・クルアーン)によって、彼らの命が助けられることを保証したが、彼らは信じようとはしなかった。小部隊のなかには声をあらげるものもいた。「我々はあなたたちがコーランを信じていないことを知っている。じゃあ、あなたたちの誓いにどんな価値があるのかね」「あなたたちの預言者、救世主イエス・キリストにかけて誓いなさい。そうすれば我々はあなたたちを信じよう」。これは受け入れられ、勇敢な小部隊は直ちに投降した。不幸なグラーム・ハイダルは悲しみと落胆のさなかにあり、彼が安全であるとは信じなかった。准将は、彼の努力の完全な成功に、この喜ばしい知らせを持って総司令官のテントに駆け込んだ。しかし、総司令官閣下は、その若い総督は逃げ出してからかなり経っているという、最も確実な情報を公使から得ていたので、疑い続けた。この雄々しい捕獲者が、閣下の配下の誰がどれほど勇敢でも、わざわざ彼のような危険な立場に身をおこうとすることが、そもそもありえるだろうか、と述べたので、総司令官の不信は消え、准将に丁重に感謝の言葉を述べたのち、この知らせをもって公使のキャンプへまっすぐ馬で向かった。グラーム・ハイダルはシャーにえつ謁けん見を賜り、「彼と彼の家族はこれまで反逆者だったが、喜んで彼らを許し、すべてを忘れる」という保証を与えた。ロバーツ准将は彼の任務に戻り、この件についてはこれ以上何も聞かなかったし、彼の功績に関する公的なおよび(握手以上の)私的な謝意を受けることはなかった。 ■グラーム・ハイダルの経歴 グラーム・ハイダルは現在32歳で、カーブルの宰相であり、この地位を兄のアクバルから継承した。この「ウィザーラト」[宰相位]への就任は、彼がドースト・ムハンマドの後継者になる可能性を示しており、当然、(脇へ押しやられた)2人の兄は、この君主と宰相に非常に憤慨した。このサルダール(説明を)はとても才能があって、野心家であり、その兄弟たちとともに、常に父親の不安と心配の種であると伝えられている。というのは、父の権威を支持し、人々をある種の平和と満足のなか置くのではなく、彼らは結束して、不和と反乱を起こそうとしているのである。アミールは、いまやとても彼のワズィール(説明を)に対してたいへん疑い深く、疑心暗鬼になっていて、自分の兄弟であるナッワーブに、ワズィールの不法行為を見張り、これを妨げるよう命じた。彼は、大柄で外見もよく、そしてとても頑丈な若者で、他の兄弟たちと同様に、そして最もアミールに似ている。私は、1841年に彼が父親とともにペシャーワルの駐屯地にいたとき、彼の似顔絵を描く機会をもてなかったことを残念に思っている。しかし、私は、キーン卿夫人のご親切とご厚意により、この殿下を友人たちに引き合わせる見せることができ、このすばらしい肖像画を描くにあたってはについて、このお方に私は恩義がある。元の絵は亡きキーン卿閣下の希望によって描かれたが、キーン卿夫人は私にこの絵を複写し、この本において出版することを許されたのみならず、私がお願いすると、全く惜しげもなく、他の貴重な絵の使用も認めてくださった。この栄誉に対して、私は心からの謝辞を申し上げたい。 ■キズィルバーシュの招待 私は、アフガニスタンのこれらの短く無原則な回想において、その人々に関して、その時私に風変わりな、驚くべきものとして強い印象を与えたものを、記憶によりすべて描こうと努めてきた。それに(トル?)自分が遭遇したのが、行軍や戦場においてであり、宮殿や牢獄、寺院(OK?)においてであれ、宿営や狩猟、裁判においてであれ。しかし、私は、温かいもてなしを受けたキズィルバーシュの族長(私の兄の大の友人)の食卓を、読者にまだ紹介していないことに気づく。彼は、「すてきな年老いた田舎の紳士であり」、カーブルの近くの「自分の地所に住んでおり」、私は非常に楽しい時間をそこで過ごした。特に述べたいある訪問は、彼の家族の結婚のときであり、そのとき、お祝いの祝宴と歓待が続いていた。私が、これらの祝宴に出席したいと述べたところ、ある日、千ものサラーム(説明を)と4本(OK?)のバラ水、そしてその紳士自身(ミールザー・ジャアファル・ハーンという名のその部族の中ではかなり重要な人物)からの要請を受け取った。それは、翌日の夜に彼の城を訪れて、アフガンの衣装を着て彼に敬意を表してほしいということだった。 ■城の訪問 その夜、私は10名の部族長の騎兵とともに、カーブルから4マイル[約6.4キロ]のサル・チャシュマ(水源)近くの彼の城まで馬で出かけた。到着すると、彼の従者が門の外で私を待っているのが分かった。そのうちの1人が私の鐙を持ち、2人目がば馬ろく勒を持ち、3人目は片手を私のひじに置き、もう一方の手を私の肩に置いて、私は下馬した。中に入ると、私は、数々の挨拶と質問とお世辞に圧倒された。「ご機嫌いかがですか。いい知らせはありますかですか。騎乗は快適でしたか。お疲れではないですか。よくいらっしゃいました。本当によくおいでくださいました」。数え切れない広間と廊下を通り抜け、ありうる限り最も低い扉を通るために、前かがみになって背中をぶつけながら進んだ。危険で不規則な階段を、手助けをえて上り、トルコの絨毯とヘラートのフェルト、もしくはナマドを敷いてある細長い部屋に入った。部屋の奥には深いくぼみがあり、刺し子縫いされた繻子の敷き布団で覆われており、その中央には白いモスリンの大きな枕が載っており、房のついた大きな絹の4つのクッションで支えられていた。「それぞれが異なった色で、厚く絹のバラ色の花がちりばめられていた。青で細かくに刺繍されていた」[Byron, Don Juan, Canto III] 。城の召使いたちから普通の歓迎を受けたのち、驚いたことに、私は枕のある場所に連れて行かれた。私が脚を組んで座るまでには、その部屋は族長達で速やかに一杯になった。彼らは応接間のどちらの側にも長い1列を作っており、自分が座る際に、それぞれ私にホシュ・アーマド(よいこそ)を言って挨拶した。客は、自分の地位が許す場所に座っていた。たとえば、より偉い人が到着すると、30人の列は即座に彼によって取って代わられた。この人物は、敬服すべきずうずうしさで、少なくとも今夜の出し物のために快適な場所に座ったと思っていた人達の、間か、さらには上席に座ったのである。より高い地位の人が加わったことによって、[地位の]下の人たちは、見るに非常に滑稽なやり方で、腕と踵で皆下の方へ擦り動いた。このように、たとえ話の正しさを証明しながら。「婚宴に招待されたら、上席に着いてはならない。あなたよりも身分の高い人が招かれており、そのとき、あなたは恥をかいて末席に着くことになる」[『新約聖書』ルカによる福音書14:8-9]。 ■主人の登場 状況が定まり、というか落ち着き、ミールザー・ジャアファル・ハーンが「アーマダ・アスト」(来た)という囁き声が聞こえ、主人(恰幅がよくて男前)が、通り過ぎながら、客に非常にゆったりと挨拶し、優雅にしなやかに歩き、部屋の中央を私に向かって進んできた。私は立ち上がって、彼に挨拶し、それに対して彼は手を伸ばして、私にメロンを渡し、私の両手を彼の両手で握り締めて、彼の唇と額に押し付けた。それから私に座るように請い、彼は自分が座る際に、私のキルトの座を拒んで「どうして私が座れるでしょう。あなたの家が栄えますように」と腕を自分の胸に当て、より低い段に座って言った。彼の習慣で私の気分を害さないで欲しい、と述べてから、私の宗教について尋ねた。ロンドン(彼らはイングランドというが)では、我々がユダヤ教徒、英国教反対者、非国教徒などに寛容であるのかどうかとか、その他の面白い質問であった。 ■歌と踊り すると、部屋中で大きな変化が起こった。部屋の中央の下にあった背の高いろうそくが、壁のくぼみに移された。これらのろうそくは、4フィートから5フィート[約1メートル22から約1メートル52]の高さがあり、周囲は、厚さが大人の腕ぐらいあって、獣脂でできていて、大きさによってそれぞれ違う匂いがした。そのうちの2本は、私への敬意のため、私が座っているキルトの中央に置かれ、私は、芳醇な香りで息が詰まりそうになったばかりでなく、すっかり目がくらんで、長い部屋が「狼の口と同じぐらい黒く」見えた。視力が戻ると、装飾品と宝石の輝きが目に留まり、リュートやヴァイオリンの音に合わせて(オルフェウスのではないが「誰の金色の演奏が鉄と石を軟らかくするのか。虎たちを馴らし、巨大なリバイアサンに底の知れない深みを捨てさせ、砂の上で踊らせるのは」[Shakespeare, メTwo Gentleman of Veronaモ])、パンジャーブの踊り子たちは、「彼らのリーダーが歌って、その歌に合わせて飛び跳ねて」「合わせたステップと声をもった妖精の一群であり」[Byron, Don Juan, Canto III]、吟遊詩人の一団とともに、我々の啓発のための心構えをした。最初の歌が終わるまでには真夜中になっていた。 ■食事の準備 それから、アーフターバ(水差し)や口広の水差しが登場すると(図15を参照)、お客たちはみんな袖をまくり、ターバンを後ろに押しやって、パンを食べる前に、手とひげ(どのひげ)を清める準備をした。豪華なナプキンとともに、私に最初に一式が渡された。使った後に、それをハーン(説明を)に渡した。彼は立派なターバンの折目で顔を乾かしているところだった。彼は上品にひざまずいて、額をタオルにつけて、かかとで立ち上がり、それを使わずにもとに戻し、代わりに自分のショールを顔に使って、少年のペーシュヘドマト[小姓]の長い黒い巻き毛で手を乾かした。私は、しばしばこんなことが行われるのを見た。特に、油の多い、ねばねばした食べ物に手を入れたあとに、小姓が、その巻き毛をきれいに生やしていた場合、その巻き毛が、もしくは、彼の長衣やターバンが用いられるのである。グル・アーブ(バラ水)の入った壷の形をしたガラスの瓶が私の前に慌てて運ばれてきた。すべての客は、自分の分を受け取り、手を差し出して、それが器から出るとそれを飲み、残りを自分の鬚と顔につけた。ここちよい香りの中で洗いながら「アッラー、アッラー、アイ、アッラー」(神の名前で、喜びを表す)の言葉がそれぞれから漏れた。ペシャーワルの「ルンギー」(シルクと綿のショール)が今や、主要な客たちの前で床の上に広げられた。ドアの近くに、音楽家やダンサーと一緒に座っている目下の者たちは、ターバンや腰帯をはずし、これらをテーブルの代わりに、ランチョンマットとして用いた。 ■食事の開始 ようやくご馳走が到着し、長い列になった接客係によって運ばれ、それぞれが、12枚から14枚くらいの見事な磁器といろとりどりの陶器の皿をのせた、彩色した一つのお盆を持ってきた。これらは、鉢とともに床に輪のように並べられ、中央には、「皮ごと絞った――これが一番いいやり方だが――レーズン、オレンジ、ザクロのジュースなどのさまざまな飲み物」[Byron, Don Juan, Canto III]が置かれた。「夕食には約100種類の料理が出された。子羊肉やピスタチオ――要するにすべての食べ物が、贅沢なシュリバス市民の非常に甘やかされた望みに相応しいほど」 [Don Juan, Canto III] 。そこには、子山羊を焼いて葡萄の葉でくるんだカバーブ、カレーに野菜、お米とアプリコット、丁子、それにアーモンドと混ぜ合わせた、甘いシチューと酸っぱいシチューがあった。ゼリー、凝乳、乳清、ラワーシュ(ルバーブ)、「溶けるような甘味で一杯のザクロ、梨、カーブルの1000もの果樹園で採れた真っ赤なリンゴ、ブハラのプルーン、サマルカンドの遠い果樹園で採れた甘い木の実、バスラのナツメヤシとアプリコット、イランの土地から来たひまわりの種」[T. R. Swinburne, メA Holiday in the Happy Valley with Pen and Pencilモ]やメロン、桃、コーヒスターン産の金色や紫色の葡萄、ガズニーのミナレットのある渓谷から採れた、有名なプラムとサクランボ、カンダハールの暑い平原で採れたクルミとイチジクもあった。平らで丸いおいしいパンがそれぞれの前に置かれ、食事の間に食べられるよう、皿とナプキンが添えられた。食事の前後には主人が祈りの言葉を唱え、皆、顎鬚と顎を撫でていた。その後、ビスミッラー(説明を)が続き、あるいは「神の名において」もりもり食べ始めるのに任せ、私がそれを繰り返したところ、集まり全体で、唱えられた。次に綱引きが始まった。重々しい感じの部族長たちがその列を崩して、互いに招き合って、小さな社交の会を作り、脚を組んで食欲をそそるお盆の前に集まった。いまや皆、静かで、ただ、大勢の大食家たちの歯で(トル)噛む音と忙しい召使いたちの足音だけが響いた。召使いたちは、水差し、砂糖を入れた雪の(OK?)コップ、凍らせたシャーベット、「ほとばしるイスターリフの葡萄園からの輝く滴」[Thomas Moore, メThe Complete Poemsモ]などを持ってあちこちに運んでいた。 ■ドゥーナ その間に、私はドゥーナと呼ばれるものを食べた。それは、その家の偉大な男が取り分ける料理の一部分で、宴席において彼が喜んで名誉を与えたいと思う誰にでも、自分の自身の手で渡すことになっていた。私は、ヨーロッパ的な偏見から、隣人の手(大きいかもしれない)が自分の喉に押し込まれ、私を特に喜ばせようとすることに関して、お世辞を言うことはできない。ハーンの指が塩漬けを、塩味と甘味、肉と果物、砂糖煮と漬物など、20の違った料理に入れた。彼はそれを捏ねて、小さな味付け肉の(私にはそうだった)ボールのような物を作り、彼の手から、親指の巧妙な動きで、私の開いた、しかし(告白するが)望まぬ口に落とした。すべての貴族の人々はお世辞で私に祝福を言い、その偉大な男の胸の悪くなる見本にしたがった。 ■プリマドンナ 彼の身近な模倣者である踊り子のプリマドンナのことを述べるのを忘れてはならない。彼女は美しい小柄な人で、ミールザー・ジャアファルによって私たちのパーティーに加わるよう招かれた。私が彼に言ったように、踊りの中でつま先回転するときの彼女のもの悲しそうな表情が私は気に入った。彼女は夕方にジャスミンとバラの花束を私に贈ってくれ、お返しに私はイギリス製の絹のハンカチを贈った。このとき、彼女は私の名前を聞き、彼女の詩の最後にそれを読み込んだが、私の贈り物の方は踊りの間中、大活躍だった。一時は、彼女はターバンのように身に付けていたが、それから、手首の周りに巻きつけた。またある時には、怒りっぽい年老いた部族長の突き出た鷲のような鼻のすぐ前で、ハンカチを指ではじき、前後に振った。部族長がそれを、なんとか掴もうとすると、皆の大爆笑のなか、非常になまめかしく、上手に引いてしまうのだった。このパントマイムの間ずっと、彼女は踊るのも歌うのをやめなかった。私は、彼女の美しさに相応しく、彼女を描写できるほどの紙面を持っていない。 そこで、彼女の美しさを繰り返し褒めることと、彼女のドレスについて述べることで、当分は、彼女を放念しなければならない。高価な帽子はブハラの金の刺繍で縁取られており、彼女の髪は編まれており、ゴムで巻き上げ、お下げにしていた。彼女の耳から金の葡萄の葉が下がっており、金の輪が、色とりどりの腕輪とともに、手首にはまっていた。彼女の上衣は緋色と銀色で、彼女の青いズボンは足首で襞を取っていた。それは、彼女の妖精のような足を際立たせた上に、足首から鈴を下げた鈴が明るく楽しげに鳴ることを許している。彼女の瞳は、ソルマ[眉墨]で色をつけた長いまつげの影で、黒く明るく輝いていた。もう十分だ! 私は脱線したようだ。彼女は主催者の範に従っていたと私は述べた。もし私が世界中で最も気むずかしい人間だとしても、どのように彼女に抵抗できただろう。「とても美しく、まさにその形が魅力的な」[Byron, Don Juan, Canto III]小さな手で、彼女は私たちの前に広げられた皿から、一番おいしい物を選び、ヘンナ(説明を)で染められた小さな指から、私を満腹になるまで料理で満たしてくれたのに。 ■アリーの魚池 「私たちの話の最後――ご馳走は終わり、魅惑的な美人も去り、召使いと踊り子たちも皆、下がってしまい」[Byron, Don Juan, Canto III]、大掛かりな花火のショーが宴会を締めくくった。そして私は寝室に朝の4時にたどり着いた。私をもてなすために、高く積まれた枕が部屋の床の上に置かれていて、喉が渇いたときのために、見事な花で飾られたお盆の上にフルーツと冷水が載っていた。私が目覚めたとき、とても贅沢でおいしいお茶が私を待っていた。それは、阿魏をたっぷり入れた、ミルクなしのシロップ状のものだった。1人の伝令がまたハーンのもとからやって来て、彼が、私をアリーの聖なる魚池――このためにサル・チャシュマ[地名]は国中で有名なのであるが――に案内する用意があると述べた。その池は、美しい庭のなかにあり、最初は空に見えた。しかし、パンの大きな固まりが投げ込まれると、すぐに大量の巨大な鯉が水面に押し合いへし合い上がってきて、えさを争って互いに闘った。ついに、池の水面は豆スープの厚さになってしまい、彼らと一緒にいることで私は気分がわるくなってしまった。私は、預言者が泥をさらうためにこの場所を訪れた証拠である、これらの太った泥だらけの者たちと、そして、彼らに付き添っている司祭(OK?)の保護者とたくさんのアフガンの崇拝者たちの献身と、別れることができて幸福だった。 |


