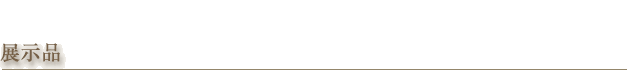 |
||||||
 [作品20]
[作品20]■トゥルキスターンのクンドゥーズのウズベク人たち Oosbegs of Koondooz, Toorkistaun(英語原文をよむ) 1841年8月、私はコーヒスターンのラグマーニー要塞における会議の席上、このスケッチの主題となっている人物たちに紹介された。彼らの名前はミールザー・アブドゥル・ハック? とルスタム・ベグといい、トルキスタンで最も有力な家系であるウズベクの大部族であるカッタガーン族の出身で、彼らの族長ムラード・ベグはクンドゥーズのミール、すなわち君侯であった。彼の領地はブハラとカーブルの間に位置しており、ヒンドゥークシュないしコーフ、すなわち月の山脈の北方で、オクサスもしくはアム河の南方であった。ミールは、彼を無理に従わせるにはあまりに遠いところにあるブハラに対して忠誠を誓うことをせず、手始めは独立状態であったものが、ついにはみずからをアミール・アル=ムウミニーン、すなわち信徒たちの司令官と称するかの地の王の最も有力な敵となっている。 ウズベク人の性格 何人かの旅行者によれば、これらのトゥルクたち、ウズベクたち、ないしトゥルクマーンたちは穏やかで優しい人種であるという。しばしば青い色をしている彼らの小さな目(彼らのゴートもしくはゲタイ起源の徴(しるし))、色白の肌、そして顎鬚や頬髯の欠如にしばしば起因する彼らの女性的な外貌などから、いい加減な観察者は同じ結論を出すであろう。彼らは、広く半円形をしているが引っ込んでいる額、頭部に傾いてついている深くくぼんだ目、そして、顔の毛の少なさといった、タタール的特徴をすべて備えている。普通ならばマホメット[イスラーム]教徒の顔を堂々と装飾する顎鬚が、彼らの場合、2、3本の毛ですべてとなるのである。彼らは絹と木綿を織り交ぜた外套チャパーンを重ね着している。彼らに好まれ、流行しているスタイルは、アドラースと呼ばれる非常にけばけばしい色をした大きな斑点模様を持つ図柄で、聖典におけるヨセフの「たくさんの色の外套」と非常に似通っている。彼らの民族の頭飾りは白いモスリン製のカルパークと呼ばれる染色された絹製の高く尖ったふちなし帽の周りに巻きつけられているが、それは左耳の下のところで一折りされて結ばれている。この結び目はこの民族に特徴的な徴となっている。靴下の代わりに、トルクマーンたちは布や亜麻を足に巻きつけ、その上からムフスィー(細長い粒起皮製の長靴)を履いている。屋外では、爪先が上向きになり、3インチ[約7.6センチ]の鋭く尖った鉄製のかかとのついたより分厚い素材の靴をムフスィーの上から重ね履きする。 ウズベク人の戦争 彼らは戦闘へと突入して行く際、長めの短剣、火縄銃、剣、戦斧、そして15フィートから20フィート[約4メートル57から約6メートル10]のも長さがある木製の重い槍を持って、叫び声を上げつつ進む。追撃者たちによって激しく追い立てられると、彼らはその槍を肩越しに投げつけ、そのようにして古のパルティア人のように戦いつつ逃げるのである。彼らの民族が得意とする戦争の様式はチャパーワァルである。これはすなわち、騎兵の一隊が先発して通過するキャラバンや村、あるいは陣営などを急襲し、不運な獲物を惨めな虜囚にしてしまうのである。彼らは、(彼らと交わった者たちの言によれば)世界で最悪の悪党であり、強盗、殺し屋、奴隷狩りなどを職業としている。最後のものは大いに尊敬される生業であり、最初の二つは皆に非難されているが、裏では皆手を結んでいる。 人身売買 彼らの人身売買は公然と行なわれているので、あなたがあるウズベク人に対しミール[長]にどんな税を支払っているのかと尋ねたら、馬2頭、牛3頭、男5人、女12人と教えてくれるであろう。これらの不運な境遇にある者たちには、神聖なるブハラ・シャリーフや諸都市の母であるバルフにおいて十分すぎるほどの売れ口が見つかる。収入に対してかけられた税をうまいこと現金で支払えなかった族長は、良心の呵責など感じることなしに、最も近いところにある村の住人(おそらく彼自身の部族の者たち)を奴隷市場へと追い立てていくのである。尊敬の印として、ウズベク人たちは目上の者に話しかけるとき広袖の中に自分の手を隠す。この同じ入れ物[袖]を、彼らは会話の最中に痰壷にしてしまうことをためらいもしないのだが。このことに加え、これらのアーダムフォルーシュ(人間売り)たち――アフガン人たちは非難をこめて彼らをそう呼ぶのであるが――は他の非道な行為にも手を染めている。一つの慣習とは、これについてはより穏やかな名前はほとんどふさわしくないが、かぎタバコをやる際の新奇な方法である。真っ当な人間がこの刺激性の強い珍味を鼻で楽しむところ、彼らはその口を大きく開けて一方の手で上唇をひっくり返すと、もう一方の手でこの興奮作用のある粉末を歯茎にこすり付けるのである。パーミヤーンチーやその他のトルキスタン(タタール地方)の住民の間でも流行しているこのむかつくような習癖を見た後、このような人々について一体何に驚嘆しろというだろうか。 テントと馬 トゥルクマーンの黒い天幕はハルガーフと呼ばれ、暗色のフェルト、ナマドで出来ており、それがぴんと張って広げられ、裂いた枝を木製の枠の中で組んだ格子の上に、革を芯にした紐でしっかりと固定されている。天幕には同じ素材で出来たドーム状の屋根があり、その中央には煙を逃がすための穴が開いている。天幕はすべて、杭もロープも柱も使わずに張られる。内部にはより明るい色の羊毛製のフェルトがかけられ、壁から屋根まで至る所が数え切れない派手な色の飾り紐や房で装飾されている。これらすべてが、暑さも寒さも湿気も通さない住居を形作っているのである。これらの天幕のある野営地はどちらかといえば蜂の巣に似ているが、オバと呼ばれている。これらの襲撃と掠奪を好む人々の日常的な飲み物は茶であり、彼らはこれを極端なまでに好む。茶にそれにはドンバの尾(この地方に特有の羊であり、その尾はそれ自体の半分もの大きさがある)の脂肪を混ぜて始終飲んでいる。彼らはその後、湿った茶葉に塩を付けて回すが、彼らはこれを大変な贅沢だと思っている。彼らは雌馬の乳を飲み、またその乳で酔いをもたらす強い酒を作る。また馬の肉を食べるが、彼らはこれを牛肉よりも好んでいる。彼らの馬は、危険や労苦の中で忠実で信頼の置ける仲間であるというだけでなく、掠奪目的での遠征において成功を収めるための主要な道具である。ゆえに、トゥルクたちはその俊足の頑健な駿馬を愛し、「娘のように」かわいがるのである。 ウズベクとの戦い 彼らの戦闘方法を批評する機会は幾度もあったが、その一つの見本として私は、我々がこれらの人々と交流する際に重要な役割を果たしたある将校の手紙から、以下の例を挙げることとする。「1839年、我々は彼らの勝負法のチャパーワァルにおいて彼らを撃退した。サイガーンの要塞を占領した後、彼らは、程なく我々の許を訪れるであろうという脅迫文を持った使者をバーミヤーンに送ってよこした。その場を離れるべきとの警告を彼らが折よく受け取れるように、その使者を20時間早く送り返すと、我々は最も困難な地へ進軍を開始した。ヤーブー、すなわち荷駄用のポニーに乗った歩兵200名が後に残されたが、これはそれらの駄獣がくたくたに疲れきっていたからであった。しかし、騎乗した騎馬砲兵60名とアフガン騎兵300騎からなる残りの兵力は行軍を急いだ。早朝の薄闇の中で要塞にたどり着こうとしていたがそうはならず、夜の暗闇に加えて我々が越えたほぼ通行不可能危険な道のせいで我々の前進は妨げられ、その要塞が見えるところにきたのは午前9時になってからであった。 戦闘の経過 我々は渓谷に侵入すると、ウズベク人の黒いオバに突進した。彼らの兵力は700名ほどであり、大半が騎兵であった。彼らは我々が遠くから接近して来るのを見、人々は要塞の防壁上から大きな悲鳴と叫び声を上げて彼らに警告した。陣営の中央部に参集し、騎乗したウズベク人の軍勢は確固たる隊列を保ったまま方向を転換し、交戦する意図を持っているように見えた。しかし、我々が近づいていくと彼らの気が変わり、彼らは馬首を帰して個々に逃げ散った。あまりにまっしぐらに逃げていったので、止まるつもりなど全くないように見えた。彼らが高い丘を真っ直ぐに駆け上っていく様は非常に美しい光景であり(彼らの馬はまるで猫のように上って行った)、何騎かは、壁や小川、湿地帯、水路などが交錯して障害物の多い谷間を駆け下りていった。しかしながら、彼らは渓谷を降りて少しいったところにある高台で隊列を組みなおし、再び我々に向けて発砲した。しかし彼らは、兵士たちとラットレー指揮下のアフガン人によって速やかに追い散らされた。200頭の馬が捕獲され、常設の陣営(ハーキムの騎兵隊の大部分が、掠奪を求める熱に浮かされてここに留まっていた。略奪はこうした連中の変えることの出来ない慣習であり、勝利を証明する正統的な方法であると彼らは見なしている)とその他の物資が接収されたが、これらはそれだけで1万ルピー[銀貨1万枚]の値打ちがあった。我々は同日の夜8時にバーミヤーンに帰還したが、27時間も騎乗していたことになる。 戦闘の成果 この卑怯な戦いの結果はすばらしいものであり、我々はもう少しのところでウズベク人の指導者グラーム・ベグの捕縛に成功するところであった。彼はクルムのミール・ワリーの長子であり、我々の突き止めたところによれば、彼の父の宮廷で非常に厚く遇されているドースト・ムハンマドのためにサイガーンの要塞を封鎖したということであった。我々が突然現れたことに対する彼の驚きは一方ならぬものがあり、みずからの陣営の品々一式を置き去りにして逃亡したほどであった。彼のパラウ[ピラフ]がまだ火にくべられ調理されているのが発見されたところからして、我々は彼に朝食をとる暇すら与えなかったようである。その連中は後に、我々が早くやって来すぎたのだと告白した――彼らは我々をゆっくりと移動する象だと勘違いしていたのであり――彼らは1度たりとて、チャパーワァルを行なう抜け目なさの半分ほども異教徒たちが持ち合わせているとは考えなかったのである。
|


