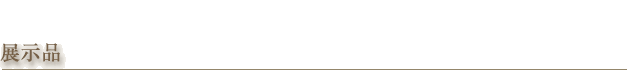 |
||||||
 [作品10]
[作品10]■ガズナ朝の君主スルターン・マフムードのモスクと墓廟 Mosque and Tomb of the Emperor Sooltaun Mahmood of Ghuznee (英語原文をよむ) 西暦1026年(ヒジュラ暦、すなわちマホメット[イスラーム]教の暦で416年)にインドの征服者となったガズニーの皇帝マフムードの霊廟を含むモスクでつとに有名なラウザの村は、私がアフガニスタンで訪れた最も興味深く、また心地よい場所のひとつであった。それはカーブルからガズニーへの主要道路沿いで、ガズニーからは2マイル[約3.2キロ]離れたところにある。神聖なる建築物が建つ庭園に入る前に、旅人は清流の流れるかなりの広さの中庭に導き入れられる。その流れは、村とすばらしく手入れの行き届いた果樹園を通り、礼拝所の中を、ふんだんに装飾の施された水路によって、水盤や非常に古くグロテスクな彫刻の施されたたくさんの崩れかけた大理石の厚板―象、野兎、イノシシその他の動物があしらわれ、その間には渦巻きや花柄の図像がちりばめられていた―の間をぬって、曲がりくねりながら流れている。中庭を通り過ぎると、修道院の回廊に似た屋根付きの通路を持つ建物に入る。その通路はシャー・トゥート すなわち王の桑(このすばらしい果実のうち、二つの種類がこの国の至るところにあり、一つは長いアーモンドのような形で透き通った白い色のもの、もう一つは大きくて丸く、たいへん深い血の色をしたものであった)や西洋スモモ、桃、アプリコット、西洋梨、サクランボ、薔薇の並木で造られた美しい庭園に向かって開いている。その生い茂った葉は、精巧に彫刻の施された大理石の墓の群れに影を投げかけている。その磨かれた墓石は、選りすぐりのイングランドの花々に七宝焼きのように飾られた豊かな芝の花壇のなかでそび聳え立ち、そこには葉と果実の花輪を彫刻が施され、死者の名と称号がアラビアとペルシアの文字で刻まれている。 ■マフムードの墓廟 このような眺めの中心に、英雄たるスルターンの神聖なる廟がそびえ立っている。このスルターンの神聖さと名声ゆえに、その霊廟は何世代にもわたって参詣の地であり続けている。東方のマホメット[イスラーム]教の諸部族はみな畏敬と尊崇の念を持ってその廟に近づき、その場に祈りと称賛を捧げ、供え物をし、神聖なるちり塵を集める。参詣者たちはそのちり塵で手や頭をこすり、そのいくらかを死すべき運命を持つ人間が受け継いできたあらゆる病を癒す聖遺物として、はるか遠い国々へと持ち去るのである。ムッラーたちすなわち聖職者たちは、このはかり知れない価値を持つ薬を霊廟の前部のところにある穴の中に個人的に蓄えており、迷信深い買い手に分け与えている。石棺は長い三角形で、装飾の施された大理石の厚板の上に置かれ、銘文がクーフィー書体で刻まれている。その文字には、果実や花の模様がぞうがん象嵌されている。石棺は、メッカにある預言者の霊廟に似せて、種々の色のビロード、サテン、 [模様入りの光沢のある]木綿更紗で作られ、竹により支えられた天蓋の下に安置されている。[この石棺と天蓋]は、毎日摘みたての花束や、王権の象徴たる孔雀の羽によって飾られている。最近まで、皇帝が戦争の際に携えていたのとまったく同じ鉄の鎚矛も霊廟近くに横たえられていたが、それは今ではなくなってしまっている。私はただ、かつて彼の玉座であったと伝えられる彫刻の施された椅子の残骸を発見したのみである。表玄関からは法螺貝とダチョウの卵がつるされ、外に向かって張り出したポーチの梁からは、アブガニスタンの諸聖地を飾る三つの菱形ないし木の葉型をした赤煉瓦製のつり飾りが、付属物である野生の羊の頭蓋骨や角とともに提げられていた。 ■ソームナートの門 世に知られたソームナートの白檀製の門――それは今や(亡き総督が「彼の兄弟であり友である、インドのすべての諸侯、族長と人々」に対し、ノット将軍指揮下の軍隊による奪還により「800年にわたる侮辱に対する報復がついになされた」と告げた、あのき奇きょう矯なギリシア古典詩のような宣言のせいで)イングランドにおいては、かつてヒンドゥスターン全域で崇め奉られていたのと同じくらい悪名高いものとなっているが――が、この絵の中においてはモスクの折り畳み式の扉となっている。モスクの入口は、相争う獅子と龍をかたどった大理石製の一対の巨像と、うずくまった獅子の像によって護られている。この像は完全に中空になっており、側面には円形の穴がある。もしかしたらこの像は、秘密の財宝の隠し場所となっていたかもしれない。ちょうど、ソームナートの巨大な偶像のように。あの偶像が(マフムードとその兵士たちがグジャラートにある偶像寺院を略奪しているとき)、マフムードの戦鎚の一撃で真二つにされると、中から神官たちの隠した大量の黄金と宝石が発見されたのであった。破壊された神像に関するこうした記憶を呼び起こすと、私は、霊廟の中にいる間じゅうずっと私に付き従い、コーランの一節を詠唱するようにつぶやきながら、読誦にあわせて体を前後にゆすっていたムッラーたちに説明を求めた。彼らが私の質問に対して答えて言うには、像の周りに敷かれていた絨毯や白檀製の扉、大理石の動物たちは、800年前にソームナートの寺院からの戦利品として象に載せてガズニーへと運ばれてきたのである。マホメット教のマリク[王]にしてムスリムたちのアミール、信仰を託されたる者スルターン・マフムードによって。アッラーの慈悲が彼の上にありますように! ■門に関する報告書 私は、1842年11月8日にペシャーワルに近い軍営にてノット将軍により召集された委員会のソームナートの門に関する報告書から、いくつかの興味深い見解を要約して付記しておきたいと思う。「ガズニーのマフムードの霊廟は何世代もにわたりマホメット教徒にとってほとんど崇拝の地といってもよいような参詣の地となっており、その門扉は特に注目される対象となってきた。であるから、下部の人の手の届く範囲が非常に損傷していること、何ヵ所か彫刻が失われ、時として細かく砕かれて聖遺物として持ち去られていることなどは驚くにあたらない。そこここで、模様の似つかない彫刻された木片が、構造の修復のために用いられてきている。門の上部は本来の彫刻のほとんどを保っているが、それは非常に美しい出来栄えで、なおかつ保存の状態もすばらしい高浮彫りの彫刻である。もともとは貴金属製の延べ板が鉄の継ぎで木製の部分に取り付けられ、それを飾っていたものと思われる。そうした継ぎの多くはまだ、規則正しいパターンを示して、門の上部に残っている。下部に行くにつれてそれらはなくなってしまう。門の構造は二つ折りになっており、折り目の部分が蝶つがいで動くようになっていた。高さは11フィート[約3メートル35]、幅は9.5フィート[約2メートル90]である。門を取り巻く枠組みの外側の寸法は高さ16.5フィート[約5メートル3]、幅13.5フィート[約4メートル11]である。この枠組みはまずまずの保存状態であるが、地面に近い部分は例外であり、このあたりには門の両側に台座が存在したと思われるが、その部分は人の肩の高さにいたるまで相当程度持ち去られてしまっている。これらの扉の大変な古さと、ソームナートの寺院からの撤去とガズニーへの輸送によって被ったであろう損傷、そして、チンギース・ハーンのアフガニスタン侵攻 の際に破壊から護るためにそれらを取り外して埋め、その後掘り出して再び取り付けたというような状況を考慮に入れれば、それらはよい保存状態にあるといってよいであろう」。門を囲う枠組みを調査して、委員会(上述の文書をさらに詳細に整えた工兵隊のサンダース少佐が議長となった)は木材部分にクーフィー体の銘文を確認し、それはローリンソン少佐により翻訳された。この銘文を、委員会が同じくこの著名な東洋学者の恩恵を受けることになったマフムードの霊廟の銘文とともに、私は勝手ながら『アジアティック・ジャーナル』のページより転載した。かの才能ある翻訳者がもしこのつまらない書物を目にする機会があったとしても、彼は私を許してくれると信じている。 ■アラビア語銘文 ソームナート門のアラビア語銘文の写しと翻訳。同じものが現代アラビア語に直されている。――「最も慈悲深き神の御名において(おそらくこの語があったと思われる)、最も高貴なるアミール、偉大なる王、諸国の主、信仰の主となるべく生まれた(者である)、サブクタギーンの息子アブル=カーシム・ マフムードに神の寛大さ(があらんことを)。神の慈悲が彼の上にありますように(判読不可能な語句)」。 ソームナート門扉のクーフィー体銘文のスルス書体による翻訳――「最も慈悲深き神の御名において。(建立された。)国家の護持者にしてイブラーヒームの父、信仰の擁護者、ムスリムたちのアミール、支配の正しき腕、信仰を託されたる者、諸民族の首の支配者、高貴にして威厳あるスルターン、アラビアとペルシアの国々の主であるマフムードの息子、強大なるスルターン、イスラームのマリク、支配と富の御旗、威厳あるマスウードの命により。偉大なる神が彼の玉座と王国を永続させ給い、彼の善行が記念されんことを。神が彼自身とその父祖とすべてのムスリムの罪を許し給わんことを」。 スルターン・マフムードの霊廟の石棺上のクーフィー書体銘文の翻訳――「神の寛大さが、彼、サブクタギーンの息子、偉大なる主にして高貴なるニザーム・アッディーン・アブル=カースィム・マフムードの上にあらんことを。神が彼の上に慈悲を垂れ給わんことを」。追記――石棺の裏面にはナスフ書体の銘文があり、亡きスルターン・ マフムードの[死の]日付、すなわちヒジュラ暦421年、ラビーウ・アル=アーヒラ月の[月末まで] 7日を残した日(つまり22日か23日)、木曜日を記録している。(署名)J・A・ローリンソン。 ■イギリス軍による門の強奪 私は1842年9月4日にあらゆる階層の人々を捕えた戦慄(せんりつ)と驚愕(きょうがく)をたやすく忘れることは出来ない。その日、ガズニーを破壊した後その手前に駐屯していたノットの軍から、第2精鋭歩兵連隊の1個中隊が、アフガン人たちがインドを屈服させた記念碑であるその白檀製の門をラウザの寺院から引き倒して持ち去るために、派遣されてきた。ムッラーたちは取り乱した様子で喚き散らし、顎鬚を引き抜き、数珠を握り締め、頭や衣服に塵をかけた。男も女も小さな子どもも喚き、嘆き悲しみ、略奪者にその門、彼らの美しき門を見逃してくれるように懇願した。彼らの慨嘆が容赦ない兵士たちに対して何の効き目もないことを見て取るや、嘆願と諫言(かんげん)の哀れっぽい声は、「大声の嘆きと激烈な怒り」[Milton, Paradise Lost, VIII]ミルトンの引用]に取って代わられた。数々の呪いと脅迫、さらには予言までもがはっきりと浴びせかけられた。いわく、我々は我々の不信心な手によってその種が蒔かれた果実を摘み取るであろうということ、そして、ブトハーク(カーブルへの通路上にある場所、他所で言及する)に到着する前のしかるべき日に、きっとガーズィー[聖戦士]が超自然的な力によって、民族的栄光の象徴を異教徒の略奪者の手から救い出すよう導かれるであろうということであった。 ■門の運搬 しかしながらその日は来たらず、我々の勝利の巨大な戦利品は各々が42ポンド砲の砲車に載せられ、半分餓死したような眠たげな水牛の群れにのろのろと引きずられ、警護する疲労困憊した兵士や将校の真心こもった祝福を従えて、不快なギーギーとした音を立てながらゆっくりと、しかしはるかな距離を、ああ! アフガニスタンのとてつもなく険しい山道と、パンジャーブの砂の多い平原と北インドの焼け付くような大地を通り、確実にガズニーからアーグラーの要塞まで運ばれたのであった。それは疲労を誘う旅であった。その門はいまだにそこにある。これらの門は、自信に満ちた、挑戦するような銘文を帯びている。スルターン・マフムードはそこで、通俗的な自慢屋のような言葉で「これらの長靴を持ち去る者は、ボンバスタ に正面から向き合うことになろう」と語っている。実際は「これらの扉を持ち去る者は私より強大な者に違いない」という意味である。しかし、2人のファランギーの英雄、すなわち霊廟の破壊を命令した者と、その偉業を達成した者のうちのどちらが、剛勇さにおいて、輝けるガズナ朝をしのぐ栄誉を主張したのか、はっきりと確かめられていないというのは奇妙なことである。 |


