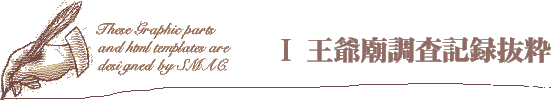
| 17. 青山宮 |
| 17-1. |  四大総巡の祭壇 96'1/8 |
| 地点:泉州市恵安県山霞郷下坂村 |
|
| 17-2. | |
| 創廟年代:北宋太平興国年間(976‐984年)、恵安古県の第一代の県令崔知節による創建。 「太平興国間古県改恵安 若逢崔知節 送吾到青山」という墓碑が残っている。 崔知節が県令として赴任したとき、当地の風俗に従って張悃の墓を参拝したところ、墓碑が突然前に倒れ、墓碑の裏側に上記の詩が刻まれているのを発見した。 そこで、張悃を青山山麓に祀ることになった。明洪武十六年(1383年)「重建青山廟寝宮記」及び成化元年(1465)「重修敕誠応廟碑記」が残っているという。 1982年にも修復し、84年に竣工(泉州市区道教文化研究会 1993:50-51)。 |
|
| 17-3. | |
| 主祀神明:張悃即ち青山王(10月23日)。 |
|
| 17-4. | |
| 配祀神明及び同祀神明:四大総巡、崔知節、文昌、土地公、朱衣神帝君、魁星爺、呂洞賓、関帝、七宮皇母、慶安尊妃、昭順夫人、王船。 |
|
| 17-5. | |
| 祭祀圏:最も狭い意味では山霞下坂村:1400人あまり。大部分が李姓。他に辛姓も。 しかし、最も広い意味では、青山王は「青峰埔」と「青山埔」の「埔主」。 「青峰埔」は下坂、東坑、下坑(以上”三李”村)、山前(陳姓)、 |
|
| 17-6. | |
| 王爺の起源:四大総巡は、張悃と同時代の人だろうが、死体を祭ったのか、木片を祭ったのかはわからない。李姓の人と一緒にやってきたわけでもない。また、四大総巡とはいっても、その四人が固定しているわけでもない。 子供は、青山王は怖くないが、四大総巡は怖いので、廟に入りたがらない。 四大総巡は船に乗っていることが多いので、いつも廟にいるわけではない。かつては、廟の大門の前に池があって、海へ出られるようになっていた。四大総巡の船が出入りしていたと考えられていた。生日には自分で帰ってくる。 廟には乞食の来訪、宿泊してもよい。 |
|
| 17-7. | |
| 送王船儀礼:不明。 |
|
| 17-8. | |
| 巡境(有無及び範囲):有。郭(1994)によれば、正月に行われる「添香日」では、青山王の副駕(本尊の分身)が下坂を巡境する。 また、10月23日の青山王の「神誕」では、青山王の副駕が三李、九蘇の村を巡境したが、1951年以降廃止。 |
|
| 17-9. | |
| 分霊:全部で18座(郭(1994) によれば、13座とも23座ともいわれている。)多くが恵安県内(張坂、崇武、百崎、螺陽、東峰、 台湾では、萬華青山宮、板橋青山宮、台北青山宮、新竹青山宮など。この他、マレーシアにも2座、シンガポールにも2座、香港に2座、マカオに1座あり。 |
|
| 17-10. | |
| 管理組織:1982年に董事会が成立。 |
|
東京外国語大学 アジアアフリカ言語文化研究所 |
| Copyright (C)1999 Yuko Mio All Right Reserved |