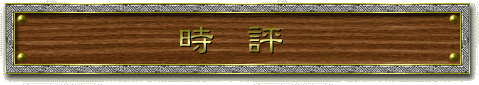
| 1300の屍の果て。暴走したイスラーム集団 |
| -----1997年11月、ルクソールでの虐殺事件によせて----- |
| I |
| 古代エジプト最初の女王、新王国第18王朝のハトシェプスト(在位:前1479頃〜1457頃)が建立した葬祭殿は、19世紀半ばに発掘・再建されて以来、世界有数の美しい建物として、たくさんの人々を魅了し続けている。 1997年11月17日。古都テーベ(現ルクソール)の対岸「ネクロポリス・テーベ」にある、この壮大な遺構を見学に訪れていた外国人観光客一行は、突如現れた「イスラーム集団(al‐Gama‘a al-Islamiya)」の武装グループに襲われ、日本人9人を含む外国人58人、エジプト人4人が凶弾に倒れた。ちょうどこの前日、苦闘のすえ悲願のワールドカップ本大会初出場を決めたサッカー日本代表の快挙に酔いしれていた日本は、官民そろってこの突然の悲報に驚き、唖然とし、“罪のない”観光客を残忍に薙ぎ倒した「イスラム原理主義者」への怒りに満ち満ちたのである。実際、エジプトのイスラーム運動を専門にする筆者のような研究者でさえ、これほどの大惨事をイスラーム集団が引き起こすとは考えておらず、最初このニュースを聞いた時はわが耳を疑った。いずれ日本人もこういった騒ぎに巻き込まれるに違いないと思ってはいたものの、日本人の場合、せいぜいが人質に捕られるくらいで済むだろうと、たかをくくっていたからである。 もちろん、イスラーム集団の暴走を危惧する声がエジプトの内外から聞こえてこなかったわけではない。元来が中央集権的な階層構造を持つイスラーム集団の場合、その活動は最高指導部の方針に大きく左右される。しかるに、近年のムバーラク政権による大弾圧の結果、これまで指導的立場にあった有力・有能な幹部は次々に逮捕、または国外逃亡を余儀なくされ、国内の主導権は軍事部門の手に移ってしまった。軍事部門が組織を握った以上、イスラーム集団がいつ暴走してもおかしくはない.... こうした形の危惧は数年前からあちこちで囁かれるようになっていたし、年春に社団法人日本イスラム協会が外務省に提出した委託調査研究報告書の中でも、すでに指摘されてはいた(注1)。さらにまた、日本政府が「イスラム原理主義」諸派と泥沼の殺し合いを続けるムバーラク政権を支援する格好になっている以上、いずれは日本人に対する報復もあり得ると警告した論考も、ほぼ同時期に発表されてはいたのである(注2)。しかし、にもかかわらず、筆者にはこれほどまでに残忍な殺戮をイスラーム集団が行うとは考えられなかった。だいたい、これだけの暴挙に出れば世界の世論を敵に回し、彼らにとって文字どおり「仇敵」であるムバーラク政権に、これ以上ない恰好の弾圧の口実を与えることになる。イスラーム集団の指導者たちはそれがわからぬほど馬鹿ではない。筆者はそう信じていたのである。 けれども事実として、イスラーム集団に残された“質の低い”指導者たちは、この暴挙に出てしまった。筆者としては、いまやエジプト情勢が自分の予想をはるかに越える迷路の中に入り込んでしまった感なきにしもあらずだが、以下本稿では、現代エジプトのイスラーム運動を研究する立場から、イスラーム集団による武装闘争の性格と、「イスラーム国家」の旗を降ろすことができないエジプト政府のジレンマなどについて、若干の考察を試みてみたい。 |
| II |
| 日本人が犠牲になった時の常として、国中の報道機関が例外なくこの事件を大きく取り上げたから、11月17日に起きた事件そのものの経過についてはもはや説明の必要もないと思う。情報源がエジプト政府の公式発表である以上、犯人グループが射殺されたのか、逃げおおせたのかといった、些細な事の真相はわからずじまいで終わらざるを得ないが、当初この事件の原因をめぐって、「外国人観光客の肌を見せる服装がいけない」だの「元来、原理主義者は外国人に嫌悪感を抱いている」だのと、信じられないほど馬鹿げた言説(注3)をはびこらせていたマスコミも、時が経つに連れ、イスラーム集団内部の指揮系統の乱れが産んだ惨劇、という事件の真相を報じるようになっていった。 もっとも、事件の直接の原因が報じられたとはいえ、この事件の背後にあるエジプト内政上の諸問題や、イスラーム集団の「テロ」とされてきたものの実態が、日本人に正しく理解されるようになったとは言いがたい。イスラーム集団がイスラーム法によって統治される「イスラーム国家」の建設を目指しており、目的のためには武装闘争も厭わない、といった類の知識をなまじ得てしまったために、かえって事の本質がわかりにくくなっている面もある。たとえば事件の翌日、橋本首相が発表した談話などはその好例であろう。いわく「観光客を無差別に攻撃することが、その国の抱える問題の解決に何の役に立つのか。こういう行為は許されない。どこの国であれテロに屈することはない」。 この談話をかなり的外れなものに感じてしまうのは、ルクソールで虐殺を行った犯人グループそのものが、自国の「抱える問題の解決に」役立てようとして、観光客を襲った気などさらさらなかっただろうと容易に想像できてしまうからである。彼らは確かに「イスラーム国家」の建設を夢見ているし、目的のためには反政府テロも辞さないという思想も持ってはいる。しかし、現実の歴史に目を向ければ、エジプト政府とマスコミによって「テロリスト」呼ばわりされ続けてきたイスラーム集団が、「イスラーム国家」建設のために武器を取った例は、過去たったの一度、1981年10月のアシュート武装蜂起事件以外ないのである。この時を唯一の例外として、イスラーム集団が「世直し」のために反政府テロを行ったことは一度もない。 だが、もしそうだとすれば、今回の事件を含め、イスラーム集団による「テロ」として報じられてきた事件の中身はいったい何だったのか。その答の大部分は、上エジプト(カイロ以南の地域)に今も残るイスラーム以前からの慣習「タアル(血の復讐)」に求められる(注4)。 イスラーム集団という組織はもともと、1970年代に上エジプトで生まれた学生運動組織である。その後着々と勢力を伸ばし、1981年10月のサダト大統領暗殺時には、暗殺を実行したジハード団と共闘してアシュート市で蜂起した。しかし、彼らが期待した民衆の一斉蜂起(「人民革命」)は起こらず、精鋭を投入した軍の前にわずか2日で敗れ去る。以後、彼らは秘密警察の監視下に置かれたが、86年以降強硬派の内務大臣が就任すると、警察による弾圧は度を越したものとなり、多くの団員が拷問を受けたり、殺害されたりするようになっていった。 日本におけるオウム真理教団がそうであるように、反政府テロを行った団体が治安当局の監視下に置かれるのは当然のことかもしれない。ただエジプトが日本と違ったのは、公安当局が単に監視するばかりでなく、イスラーム集団の団員を予備拘束したり、拷問にかけたりもできることだった。サダト暗殺以来施行され続けている緊急事態法(治安維持法)の賜物である。そして重要なことに、誰がイスラーム集団の団員かを識別し、逮捕・拘束することは、警察にとってそれほど難しい仕事ではなかった。 イスラーム集団を武装闘争にのみ従事する地下組織と見る誤解は、マスコミのみならず学界でもしばしば目にするが、事実はまったく違う。彼らは公然と自身の主義主張を説き、時には大掛かりな反政府デモを組織したりもする、驚くほどオープンな宗教団体なのである。確かに彼らは反政府テロを否定しないけれども、彼らにとって武装闘争は本来最後の手段に過ぎない。したがって、軍事部門を除くイスラーム集団の団員には、自分が法を犯しているという意識など微塵もなく、逃げも隠れもしないのである。警察にしてみれば、軍事部門を除くイスラーム集団員の「メン」は最初から割れているのであって、彼らの逮捕・拘束など造作もないことであった。かくて、イスラーム集団の団員は簡単に拘束され、拷問を受け、被害は甚大なものに昇っていく。 90年初頭にくだんの内務大臣が解任されても、警察による過酷な弾圧は終わらなかった。そして同年9月、イスラーム集団のスポークスマンが白昼堂々路上で射殺されるに及び(犯人は不明)、遂にイスラーム集団も公式に復讐を宣言することになる。翌10月には軍事部門が現職の人民議会議長を暗殺。現在まで続く警察とイスラーム集団との、果てしない殺し合いの幕が切って落とされたのであった。 さて、ここでこの殺し合いを複雑・激化させたものこそ、先に述べた「タアル」の論理にほかならない。もちろん今日、すべての上エジプト住民がこの慣習に従っているわけではないが、特に非都市部にあっては、現在でも“家族の一員が殺された場合、その仇は一族の誰かがとらなければならない”と考える男子が少なくないとされる。つまりここでは、イスラーム集団の団員が殺された場合、組織とはまったく関係のない親類縁者が警官に復讐するといった事態がごくふつうに起きてしまうのであった。一方、同僚を殺された警察もまた、イスラーム集団の団員に対する報復を重ねていく。要するに、今日までエジプト政府と官製のメディアがイスラーム集団による「テロ」として非難してきた事件の大半は、この「タアル」の限りない連鎖なのであった。 92年以降アルジェリアが事実上の内戦に突入すると、「アルジェリア化」を恐れたエジプト政府はいよいよ本格的なイスラーム集団の掃討に乗り出す。最新兵器を装備した警察軍の攻勢にさらされたイスラーム集団は、ムバーラク政権の財政基盤を揺るがすべく、この時点ですでに外国人観光客を襲撃する旨の警告を発していたが、実際には列車などを散発的に銃撃するだけで数年が経過していた。90年代前半の段階ではイスラーム集団の側にもなお余裕があり、冷静な判断力を持った指導者も残っていたため、外国人観光客を殺害した場合のマイナス面を十分計算できていたものと思われる。しかし冒頭に述べたとおり、やがてイスラーム集団の有力幹部は次々に逮捕あるいは国外逃亡を余儀なくされ、国内組織の主導権は軍事部門に移っていった。 1300人に及ぶ死者をうんだ復讐戦に疲れてか、97年7月には獄中のイスラーム集団創設メンバーが政府との「停戦」を提案。アメリカで服役する同組織の精神的指導者ウマル・アブドゥッラフマーン師もこれを支持したが、エジプト政府は9月、「テロリスト」との対話は断固拒否する旨の声明を発表した。これによって「停戦」交渉は暗礁に乗り上げ、10月13日にはミニヤで警官など11名が殺害される。警察も直ちに応戦し、イスラーム集団軍事部門の暴走が心配されていた矢先の今回の事件であった。 もちろん、ルクソールで犯行に及んだ武装グループの真の動機が何であったのかは知るよしもない。だが、これだけの暴挙に出ざるを得なかった点から見て、イスラーム集団の軍事部門が相当追い込まれていることだけは確かなように思える。指導部の質が低下しているとはいえ、実際に外国人観光客を殺戮し、ムバーラク政権の屋台骨を揺さぶる以外生き残る道がないと考えたからこそ、先の見えない暴挙に出たと見るのが最も自然だと思われるからである。 なお最後に、イスラーム法に照らして、こういった殺戮が容認されるかどうかについても考えておきたい。イスラーム法は、アマーン(安全保障)を得た異教徒に対する攻撃を禁じている。このため、イスラーム集団は長くエジプト政府発給のヴィザをアマーンと認めない方針を採ってきた。これを認めれば、観光客襲撃がイスラーム法上の犯罪となってしまうからである。だが、精神的指導者ウマル・アブドゥッラフマーン師によれば、97年夏の「停戦」提案の結果、イスラーム集団は当該ヴィザをアマーンと認めたことになった。つまり今回の殺戮は、イスラーム集団自身が奉ずるイスラーム法の観点からみても、暴挙、愚挙以外の何物でもなかったのである。 |
| III |
| 以上、今回の事件を引き起こすに至ったイスラーム集団内部の事情を見てきたが、以下では視点を変えて、イスラーム集団が根絶されない理由、言い換えれば、ムバーラク政権が抱える弱点について検討してみたい。 エジプトに限らず、イスラーム運動興隆の背後に深刻な経済危機があったことはよく知られている(注5)。1970年代以降、中東のいくつかの国々では爆発的に人口が増加し、失業問題と住宅難が一挙に表面化した。そしてエジプトの場合、とりわけ大きな被害を受けた(と感じていた)のは、理系を中心とする高学歴者たちだったのである。工業化が事実上の失敗に終わったことも手伝って、彼らのほとんどは大学を出ても就職することができず、失業者同然の立場に置かれた。 このようにして生まれた失業者や学生たちは、やがて自身の窮状を政治に裏切られた結果と見なすようになり、ジハード団やイスラーム集団など、武装闘争をも厭わぬ「過激な」イスラーム運動組織に参入していく。むろん彼らに他の選択肢がなかったわけではないが、左翼でもなく、穏健イスラーム運動を代表するムスリム同胞団でもなく、イスラーム集団のような「より過激な」イスラーム運動に彼らは吸収されていった。(1)真の「イスラーム国家」建設こそ理想であり、(2)ムスリム同胞団など穏健派のやり方では真の「イスラーム国家」を建設することはできない、と考えた結果である。 ところで、上に述べた二つの考え方――青年層がイスラーム集団を選んだ理由――は、いったいどこから来るものなのだろうか。この問いを突き詰めていくと、実は二つが二つともムバーラク政権の政策と密接に関連していることに気づく。実際、この二つの点に関わる政策こそ、青年層にイスラーム集団を選ばせる直接の原因になっていると言っても過言ではないのである。 いったい、政治に不満を持つ青年層はなぜ他のイデオロギーでなく、広い意味でのイスラーム運動を選び続けるのだろう。イスラーム教徒だから、という回答はナイーブに過ぎて、説得力に欠ける。現に、国民の大半がイスラーム教徒でありながら「世俗主義」を採用しているトルコの例があるし、エジプトでも70年代にサダトがイスラーム運動を称揚するまでは左翼が学生運動の中心だったからである。 実際、エジプトのイスラーム運動にとって決定的な転機となったのは、70年代にサダトが進めたイスラーム称揚政策であった。急死したカリスマ、ナセルの後を受けて70年に大統領となったサダトは、政権内部に依然強い力を持っていた左派に対するカウンターバランスとしてイスラーム運動を利用する一方、自身の統治の正当性を確立するため「イスラーム政治」の理念を国家経営の前面に据えた。その結果、新聞やラジオなどのメディアでも、エジプトをより一層「イスラーム国家」化する必要が日々論じられるようになり、「イスラーム国家」建設は徐々に明確な国是となっていったのである(注6)。 サダト自身はやがて、自ら育てたイスラーム運動に手をかまれた形で暗殺されるが、この暗殺事件を処理した軍事法廷においてすら「イスラーム国家」建設が明白な国是として確認されていたことは、一般に政教分離国家と考えられているエジプト国家の本質を理解するうえで極めて重要なことのように思う。そして、サダト政権を継いだムバーラク政権も、当然のことのようにこの国家原則を維持してきた。 つまり、言ってしまえば、エジプトは過去30年近くにわたって「イスラーム国家」の建設を国是としてきたのであり、イスラーム集団とエジプト政府との間に思想的に大きな対立が存在するわけではないのである。両者の間にあるのは、現行法がイスラーム法であるかどうかについての認識の違い――政府は、現行法の大半はすでにイスラーム法であって、エジプトは十分に「イスラーム国家」であると主張するが、イスラーム運動はこれを詭弁として斥ける――だけであり、これに、大統領を初めとする特権階級が利益を独占しているという批判が加わって、現在の対立が成立していると言えよう。 エジプト政府が形だけでも「イスラーム国家」の建設を理想とし、自身の「イスラーム国家」性を主張し続けているという事実。この事実はいくら強調しても強調し過ぎることはない。政権による「イスラーム政治」論の称揚は、直接・間接にイスラーム運動の隆盛を支える契機になっていると考えられるからである。「イスラーム国家」の建設が国是であり、エジプト人一般に浸透した考え方である以上、政治的不満を持った青年層がイスラーム運動に結集するのはおかしなことではない。そして、政治的不満を持つ青年は失業者に留まらず、経済的に恵まれていても政治に不満を感じる青年もいる。彼らもまたイスラーム運動に参加し、かくてイスラーム運動は日々成長し続けることになるのである。 だが、ではなぜムバーラク政権は「イスラーム国家」の旗を降ろさないのだろうか。答は、現実問題としてそれがほとんど不可能だからである。エジプトにはイスラーム教学の総本山とも言うべきアズハル機構があり、その存在を無視できないし、ここまでイスラーム政治論を浸透させてしまった以上、いまさら政教分離を言い出せば「背教者」扱いすらされかねない。現実には、政府自身が「政教分離」につながる主張を検閲で取り締まっているような状況であり(注7)、政教分離思想を唱えてイスラーム運動を根幹から揺さぶるなど、ほとんど夢物語でしかないのである。イスラーム運動の追い風になるとわかってはいても、「イスラーム国家」の旗を降ろしてより大きな危険に直面するくらいなら、現状のままでいく。ムバーラク政権にはこれ以外に残された道はほとんどないと言っていい。 とはいえ、イスラーム運動すなわちイスラーム集団を意味するわけではない。現実に巨大な勢力を誇っているのは、反政府武装闘争を否定する穏健派のムスリム同胞団であり、ここにどれだけ支持が集まろうと現状では政府にとって痛くも痒くもない。この国では、選挙による政権交代などまず100パーセント起こり得ないからである。選挙制度そのものに大きな問題があって、選挙民の大半は投票できないし、選挙結果自体、集票段階における操作等によって完全にねじ曲げられてしまう。 政治に不満を持つ青年層がイスラーム集団などの、より「過激な」組織に参入していく二つ目の理由は、まさにこうした状況によっている。選挙による政権交代があり得ない以上、ムスリム同胞団が掲げる「イスラーム国家」建設の夢は欺瞞に過ぎない、と彼らは考える。事実上軍が支配するエジプト政治に不満を持つ「まじめな」高学歴者たちは、こうしてイスラーム集団などの周囲に結集していくのである。政府による弾圧がここまで強化されているにもかかわらず、アメリカ文化の権化とも言うべきアメリカン大学の教授や学生を含む多くのインテリがイスラーム集団を離れない背景には、エジプト内政の抱える以上のような問題が存在している(注8)。 |
| IV |
| 91年の湾岸戦争後、多額の対外債務が帳消しになって、エジプト経済は危機的状況を脱した。しかし、それに続く「開放経済」の導入は国民の間の貧富の差をいよいよ拡大しつつある。もちろん、国民全体の生活水準も向上してはいるものの、公正な富の分配を求めるイスラーム運動の主張が説得力を失うような状況ではないと言えよう。こうした中では、いかにエジプト政府がイスラーム集団を追い詰めたところで、イスラーム集団が完全に滅びてしまうことはないように思う。彼らの目標そのものはエジプト人一般にとって奇異なものではないし、言論・出版の自由が制限され、選挙による政権交代が起こり得ない以上、真に改革を目指す若者に残された道はイスラーム集団のような組織に参加することしかないからである。エジプト人はふつう血を見るのが嫌いと言われるが、先に述べたとおり、イスラーム集団は最後の手段として反政府テロを認めているに過ぎず、破壊活動だけを重視する組織ではないため、ここに加入すること自体はそれほど大きな精神的抵抗をともなわない。イスラーム集団内部の指揮系統が回復に向かっているという情報もあり、今回のような外国人襲撃がそう頻繁に起こるとは思われないが、ムバーラク政権がより一層の民主化を進めないかぎり、イスラーム集団への参入が止むことはないだろう。政権にいま求められているのは、弾圧ではなく民主化であり、真に国民に支持される政権に自らが変っていくことであると切に思う。 |
| 注: |
|