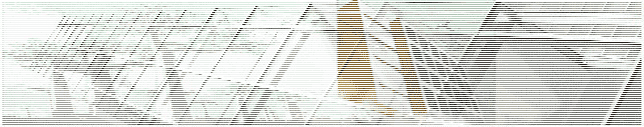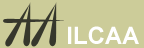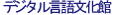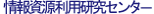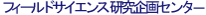|
講師報告:
1. 期間と時間
モンゴル語研修は、2009年8月3日から9月2日までの、5週間近くにわたって行われた(そのうち土日、及び8月13日、14日は休日)。
授業は、通常一日6時間で、1時限10:00~11:00,2時限11:05~12:05、3時限12:45~13:45、4時限13:50~14:50、
5時限14:55~15:55、6時限16:00~17:00(12:05~12:45は昼食休憩)で行われ(ただし、最終日9月2日のみ15:55まで)、
研修の総時間数は125時間であった。
2. 講師
モンゴル語研修の講師は、以下のようである。
| 主任講師 |
塩谷茂樹(大阪大学世界言語研究センター教授)
中嶋善輝(大阪大学世界言語研究センター講師)
|
| ネイティヴ講師 | ヤマーフー バダムハンド(大阪大学大学院博士後期課程) |
| 文化講演講師 |
山口周子(大阪大学外国語学部非常勤講師) |
3. 会場
研修期間中すべてにわたって、大阪大学箕面キャンパスを研修会場として使用した。具体的には、お盆前の8月3日から12日までを、
管理棟4階402会議室を、お盆後の8月17日から9月2日までを、E棟2階の206号室を、また文化講演日の8月21日のみ、
パワーポイントの使えるA棟2階の203号室を終日使用した。
4. 受講生
受講生は11名で、大学在籍者が5名(うち学部生3名、修士課程1名、博士課程1名)、その他、開業医、大学の事務職員、
会長秘書、書籍販売業、派遣社員、アルバイト等、職種は様々で、また、受講動機もモンゴル語学、アルタイ言語学、考古学、
仏教学等、語学や他の分野の研究を主な目的とする者や、モンゴルでの植林等のボランティアや将来モンゴルでの生活を志す者等、
まさに十人十色であった。
5. 教材とそのねらい
今回の研修に際し、三人の講師で下記の5冊のテキスト、及び音声教材CD2枚を、研修前にあらかじめ準備した。
| テキスト1. |
『モンゴル語文法問題集―初級・中級編―』
( 塩谷茂樹、ヤマーフー バダムハンド著 pp.137 ) |
| テキスト2. | 『モンゴル語会話―初級・中級編―』
( ヤマーフー バダムハンド著 pp.182 ) |
| テキスト3. | 『モンゴル語読解―初級・中級編―』
( ヤマーフー バダムハンド著 pp.103 ) |
| テキスト4. | 『モンゴル語基礎例文1000』
( 中嶋善輝著pp.60 ) |
| テキスト5. | 『モンゴル語・日本語小辞典』
( 中嶋善輝著pp.249 ) |
| 音声教材 | 『モンゴル語会話―初級・中級編―』
DISK-1 初級編、DISK-2 中級編( 吹込者:ヤマーフー バダムハンド ) |
上記のテキスト5冊のねらいは、次のようである。
テキスト1は、モンゴル語文法の初級・中級レベルをカバーする、「文法」と「練習問題」の二つから成っている。
まず、序では、Ⅰ. モンゴル語のアルファベット、Ⅱ. 発音、Ⅲ. モンゴル語の語形式の内部構造を概説する。
また、本文となる第1課から第20課までの20課は、それぞれ少なくとも二つの文法事項から構成され、各課は、
初級の平易な問題から、中級のかなり高度な問題を含む練習問題によって、当該の文法事項を正しく理解できたかどうかを
確認できるように工夫されている。最後に、付録として、人称代名詞の格変化や動詞の連体、連用、終止、命令願望語尾を
一覧表にまとめ、学習者の理解の手助けとした。
テキスト2は、モンゴル語会話の初級・中級レベルをカバーするために、「初級編」と「中級編」に分け、
それぞれ計20課(合わせて40課)から構成されている。まず、初級編は、各課すべてA、Б二つの会話から成り、身の回りの平易な
日常会話だけでなく、モンゴル語初級文法の習得までも考慮に入れた内容となっている。次に、中級編では、第1課から第20課までを
通して、モンゴル人女性Цэцгээと日本人女性 花子という二人の登場人物を中心としたストーリー性のある話になっており、
そこにはモンゴル人と日本人の文化的背景の違いから生ずる風俗習慣や考え方の違い等が反映するような内容となっている。また、
初級・中級ともに、各課の直後に「新出語句」の項目を設け、学習者がモンゴル語会話を勉強する際に、できるだけ理解の助けと
なるよう最大の便宜を図った。さらに、巻末には「語彙編」として、「新出語句」をひとまとめにして提示した。なお、
このテキストには、音声教材として、ネイティヴ講師バダムハンドの録音により、『モンゴル語会話―初級・中級編―』
DISK-1 初級編、DISK-2 中級編という2枚のCDを作成した。
テキスト3は、モンゴル語読解の初級・中級をカバーするように、各課は、2つから4つほどの小テキストから成り、
合計20課で構成されている。まず、「読解・初級」では、モンゴルの小学校低学年の教科書を一部利用した他、現在インターネットで
公開しているモンゴル語による様々な情報も大いに活用した。また、「読解・中級」では、形式的には、できるだけモンゴル語文法に
とらわれずに、しかも内容的には、モンゴル民族古来の伝統的文化や風俗習慣を紹介する目的から、主に「口承文芸」のジャンルの
テーマを数多く取り入れるよう工夫した。例えば、「舌慣らし言葉」、「世界の三つ」、「なぞなぞ」、「民話」、「子守歌」、
「タブー」、「ことわざ」である。さらに、各課の直後に、「新出語句」の項目を設け、学習者がモンゴル語の読解力をつける際に、
できるだけ理解の助けとなるよう最大の便宜を図った。巻末には、「語彙編」として、「新出語句」をひとまとめにして提示した。
テキスト4は、モンゴル語の名詞類、動詞類、不変化詞類という三つの語の形態的分類に基づき、学習すべき基礎例文を収集し、
配列した点に最大の特徴がある。すなわち、1~199までは、単純な名詞類や不変化詞類によって構成された句や文、200~699までは、
動詞の形動詞や3種の副動詞を用いた平易な句や文、700~899までは、動詞の4種の終止形語尾、900~1000までは、各種の命令法及び
その他の副動詞、条件法によって構成された文等の学習を、段階的に行うことができるよう工夫してある。
テキスト5は、モンゴル語と日本語の小辞典であるが、いくつかの点で学習者に大きな便宜を与えるよう新しい工夫が
なされている。その一つが、名詞の複数形や「隠れたн」等、現在のモンゴル語・ハルハ方言の口語形式として出現する様々な
バリエーションを「文法メモ」として盛り込んだ点にある。また、キリル文字の見出し語に対応するウイグル式モンゴル文字の綴りを
網羅的に記載した点にある。これにより、現行のキリル文字モンゴル語文法では、説明不可能な動詞の副動詞語尾-ж、-чの使い分け
等に対し、一定の回答を提供できるようにした。さらに、もう一つの大きな特徴は、モンゴル語における借用語に関し、従来のチベット、
漢語、サンスクリット、ロシア、ギリシャ、イラン、アラビア語系以外に、著者が長く取り組んできたモンゴル語におけるチュルク語系
借用語の明示を十分に充実させた点にある。
6. 文化講演
文化講演は、8月21日の3時限(12:45~13:45)と4時限(13:50~14:50)の2時間にわたり、山口周子により行われた。
前半は、自己紹介の後、モンゴル仏教学に関する参考文献の紹介、さらには、「モンゴル」の名が歴史上いつどのように出現したか、
という問題から始まり、その後、今回の主なテーマとなるモンゴルに仏教がどのように伝来したかを、13cの第1次弘通(ぐつう)、
及び16~17cの第2次弘通の経緯と背景を詳しく概説した。後半は、モンゴルに伝わる仏教美術をパワーポイントを用い、
その名称と役割を受講生たちに熱く語り、彼らをモンゴル仏教の神秘的世界にしばしいざなった。
7. 研修の成果
今回の研修の最大の成果は、受講生11名全員が、何はともあれ最後まで出席し、無事修了式を迎え、修了証書を手にしたことにある。
言語研修も後半となった第4週目には、モンゴル語単語50題(各2点、計100点)の小テストとモンゴル語会話の書き取りテストを
一回ずつ行い、受講生の理解度を確かめた。その結果は、受講生11名のうち、9名が95点以上、2名が80点台という高得点であった。
このことから、受講生全員がキリル文字によるハルハ・モンゴル語の最低限の「書く(бичих)」というレベルは、
この一か月の間で十分にクリアできたものと判断した。
今回の研修を通じて、外国語教授法にはdirect methodを始めとする様々な方法があるが、「文法の体系的習得」なくしては、
その発展や応用もあり得ないことを身をもって体験した。その意味では、塩谷の担当した93時間のうち、半数近くの43時間を、
テキスト1「モンゴル語文法問題集」にあてたことは大成功であり、これは単に文法の習得のみならず、ひいては
「読む(унших)」、「聴く(сонсох)」、「話す(ярих)」というレベルの向上にも大いに役立つ
ものという認識をあらたにした。
受講生から、今回の研修により、モンゴル語の初級・中級文法を最後まで体系的に勉強することができ、その基礎作りをするとともに、
今後の大いなる自信にもつながったという喜ばしい声が数多く聞かれたことは、今回の研修の成功を物語るものである。
8. 研修の成果と課題
この5週間の研修で、アカン語の基本的な語彙と文法を習得し、簡単な会話ができ、また簡単な文を読み書きできるようになる
という目標を、受講生全員がほぼ達成できた。
受講生の上達ぶりを確信したのが、最終日の自由発表の時であった。事前にいくつかの絵を渡し、各自選んだ絵に関して自由に
ストーリーを作ってアカン語で発表することが課題だった。受講生全員が、1人5分以上かけて自作のストーリーを発表してくれたが、
その内容もさることながら、文法の正しさと発音のすばらしさに、私たち講師は驚嘆した。外国人講師は、「ガーナ人よりも上手い」
とほめたたえた(アカン語を第二言語として話すガーナ人は、文法や声調が間違っていることが多い)。
研修のもう一つの成果は、アカン語の本格的な教材を日本語で初めて作成したことである。今のところ英語で書かれた外国人向けの
テキストが2,3あるものの、表記が誤っていたり、書記法が不完全だったり、扱う事項が表面的であったり偏りがあったりと、
初心者の独習に使えるとはとても言えなかった。本研修向けに作成したテキストは、重要な語彙、文法を厳選し、詳しく解説している
ので、受講生だけでなく初心者の独習にも役立ててもらえると確信する。
今後の課題としては、まず、本研修を修了した受講生たちのために、中級・上級レベルの教材および学習環境を整備していく
ことである。実際、数人の受講生から、将来アカン語研修第二弾を開催してほしいという強い要望があった。
本研修には9名もの受講生が集まったが、これは、アフリカをフィールドとする研究者が増えていることや、ヨーロッパ諸語のような
公用語ではなく現地では現地語で話すという傾向の表れだろう。今後も増えると思われるアカン語やアフリカ諸語の教授に対する
要請に応えることも、私たちアフリカ言語研究者の1つの使命であると考える。
また、中嶋の精魂込めて作成した『モンゴル語・日本語小辞典』は、語彙の豊富さ、訳出の正確さはもちろんのこと、
借用語の起源をも明確にした点等、斬新さが見られ、受講生の評判が良かったことは特筆すべき点である。
さらに、研修期間中、125時間すべてを日本人講師とペアで担当したバダムハンドは、生のモンゴル語で、とりわけ「発音」
指導に終始徹底し、受講生にいつも笑顔で優しく接したことは、受講生のモンゴル語学習意欲の向上に大いに力となったことにも
言及すべきであろう。受講生からのモンゴル語のみならず、モンゴルの文化習慣等に関する質問にも、彼女は、
誠心誠意可能な限り回答し、言語研修の成功に大きな一役を担ったことに対し、この場を借りて心から御礼の言葉を述べたいと思う。
受講生の中には、第1週目から学んだ単語を駆使しながら、日記をつけて添削を望む積極的な者も数人いた。
また、言語研修後半には、今後、モンゴル文字(縦文字)によるモンゴル語研修やモンゴル語上級コースを望む声も少なからず聞かれた。
最後に、研修終了日となった9月2日の閉講式にて、主任講師の塩谷が受講生全員に対し、言語学習には、「情熱」、「執着」、
「謙虚」の三つの要素が不可欠であると助言して、2009年度東京外国語大学AA研主催のモンゴル語研修の全日程を無事終了した。
(文責 塩谷茂樹)
![]()
モンゴル語授業風景
|