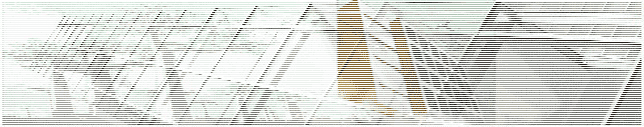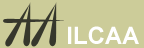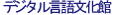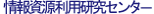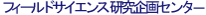|
講師報告:
1. 期間と時間
アカン語研修は、2009年8月3日~2009年9月4日の5週間、土日を除く25日間にわたって行われた。
毎回4時間の授業が行われ(10:00~12:10および13:00~15:10)、総研修時間は100時間であった。
2. 講師
| 主任講師: |
古閑恭子(高知大学准教授) |
| 外国人講師: | サミュエル・アンポンサー(東京国際大学大学院生) |
| 文化講演講師: |
ジョセフィン・アサンテ
ウィンチェスター・ニ・テテ(パーカッショニスト)
サミュエル・アンポンサー(東京国際大学大学院生)
八木繁実(美)(多摩アフリカセンター所長) |
3. 教材
外国人向けのアカン語テキストは、英語で書かれたものは2,3あるが、日本語によるアカン語の教材はこれまで皆無であった。
また、英語で書かれたものも、記述が誤っていたり書記法が不完全だったり、あるいは文法事項の解説が表面的だったり取り上げ方に
偏りがあったりと、初心者が体系的に学習するには不十分であった。音声教材についても、入手できるものはないに等しい。
そこで本研修では、アカン語初心者が効率よく体系的に語彙と文法を習得するための教材として、以下の3点を作成した。
3.1 『Let’s study Akan!』(古閑恭子、サミュエル・アンポンサー著)
アカン語を学ぶ上で必須の語彙・文法事項を盛り込んだテキストである。全20課からなり、各課は、ダイアローグ、語彙、
文法、例文、練習問題から構成される。ダイアローグと例文には、そのまま使えそうな自然な表現をできるだけ多く取り入れた。
また、各課末にはガーナの生活や習慣などへの関心を喚起するコラムを設け、さらに随所に現地で撮った写真をちりばめ、
現地の様子をイメージしながら楽しく学べるよう工夫した。巻末には、ガーナ地図および言語地図、アカン語に豊かなことわざ、
アカン語の歌を付けた。
3.2 『Akan vocabulary』(古閑恭子著)
上記テキストに掲載されたすべての語彙を収録した語彙集である。基本的な語義のみを示した簡便なもので、本格的な学習には向かないが、
予習・復習の際に活用してもらうべく作成した。信用できる現代アカン語辞書がほとんどない現状の中で、本格的な辞書作成が急務であり、
本語彙集をその足がかりとしたい。
3.3 『CD: Let’s study Akan!』
上記のテキストに掲載されたダイアローグ、語彙、例文および練習問題解答を収録した補助音声教材である。吹き込みは、
ネイティブスピーカーのアンポンサーさん(本研修外国人講師)とアサンテさん(本研修文化講演担当者)に、収録は
(株)サクシードに依頼した。アカン語の音声資料がほとんどない現状を考えても、本音声教材は貴重な存在だと思われる。
4. 受講生
受講生は合計9名で、大学学部生4名、大学院生4名(うち1名は東京外国語大学大学院単位履修生)、大学教員1名という構成であった。
受講生のうち4名はガーナ研究に携わる人たちで、そのうち3名はガーナの滞在経験があり、1年以上滞在経験のある人もいた。
動機としては、研究上アカン語を使うこれらのガーナ研究者の他、アフリカのドキュメンタリー等をテレビで見て関心を持った人、
さまざまな語学歴があり言語学的関心から受講した人が集まった。全員がガーナの言語や文化に強く関心を持ち、非常に熱心だった。
研修の行き帰りに受講生に会うと、携帯プレーヤーで教材のCDを聞いていたり、テキストを読みふけっていたりしていてこちらに
気づかないこともあった。アカン語で夢を見ました、という人もいた。授業中は多くの質問が飛び交い、ガーナの言語文化に関する
議論に発展することもしばしばだった。かなり専門的な鋭い質問もなされたりするので、講師は念入りに準備をしなければならなかった。
授業中だけでなく、休み時間や昼食時間も、アカン語について、ガーナについて、話が尽きることはなかった。また、研修期間中に、
アフリカ料理店とガーナ料理店に受講生たちと出かける機会を設け、アフリカ、ガーナ料理を堪能しつつ親睦を深めた。
5. 会場
8月12日~14日の3日間の全学閉館期間のみ府中市生涯学習センターを使用し、残る22日はAA研マルチメディア会議室(304)を使用した。
6. 授業
授業(4時間)は、おおむね以下のように行った。
6.1 復習
毎回(月曜を除く)最初の15分~30分程度を前日の復習に充てた。方法は、内容に応じて、講師が作成した復習テストを実施する、
外国人講師と既習事項を使って会話する、写真や絵を使って質問に答えたり文を作ったりする、というものである。
6.2 導入
まずCDを用いてダイアローグを2回聞き、新出語彙を外国人講師のあとにつけて2回ずつ発音した。必要に応じて、
形態構造や語源などについて説明した。
6.3 文法
各課には、アカン語に重要と思われる文法事項を取り上げた(第1課「文字と発音」を除く)。アカン語は、形態、統語構造が
比較的シンプルな言語である。多くの例文を用いて、構造と規則性を効率的に理解できるよう工夫した。
6.4 練習
語彙と文法の習得と定着のため、和文アカン語訳、穴埋め問題、入れ替え問題、絵や写真を使った会話など、内容に応じて
適宜練習問題を行った。講師がホワイトボードに書いた絵が思った以上に好評で、人物(特にやし酒を飲む人物)が講師に似ていると
噂だった。
さて、特に受講生を悩ませたのが、動詞活用形の声調であった。動詞活用形の声調は語根の構造によって異なるが、
目的語の有無によって違いが出る場合もあり、声調のみによって活用形の区別がなされることもある。この声調の克服が最後まで
多くの受講生の課題であったが、熱心な学習の成果あって、修了までには全員がある程度の正確さをもって発音できるようになった。
6.5 語彙
各課末には、「身のまわりのもの」、「身につけるもの」などテーマ別に語彙リストを付け、1回あたり30~50の単語を覚えた。
大変だと嘆く声も聞かれたが、苦労の甲斐あって修了時までにはテキストに出てくる語彙も合わせて1000語以上の語彙力を身に
つけることができた。
6.6 アカン語コーナー
毎回、授業の最後の15分くらい、生きたアカン語に触れる時間を設けた。内容は、アカン語のドラマ、読み物、歌、ことわざである。
ドラマは、王位継承問題を扱った『Obaa hemaa女王』で、生きたアカン語の教材として適しているだけでなく、ガーナの社会、
文化や習慣の学習にも最適であった。読み物は、小学校のアカン語の教科書の一部を、歌とことわざは、テキストに付録として
つけたものを使用した。
6.7 復習テスト
毎週金曜日は、1週間分の復習テストを実施し、語彙と文法事項の理解度を確認した。テストは、和文アカン語訳、
アカン語和訳などの筆記試験、外国人講師との自由会話形式、絵を用いた会話形式など、適宜内容に合わせて行った。
7. 文化講演
毎週金曜日の後半2時間、外国人講師および外部講師による計5回の文化講演を行った。4回目と5回目は、公開で開催した。
| 第一回: | 8月7日(金)「ガーナの料理」
講師 ジョセフィン・アサンテ |
第二回: | 8月14日(金)「ガーナの太鼓音楽」
講師 ウィンチェスター・ニ・テテ(パーカッショニスト) |
第三回: | 8月21日(金)「ガーナの貧困と経済格差」
講師 サミュエル・アンポンサー(東京国際大学大学院生、本研修外国人講師) |
第四回: | 8月28日(金)「アフリカの暮らしと昆虫と音楽I」
八木繁実(美)(多摩アフリカセンター所長) |
第五回: | 9月4日(金)「アフリカの暮らしと昆虫と音楽II」
八木繁実(美)(多摩アフリカセンター所長) |
8. 研修の成果と課題
この5週間の研修で、アカン語の基本的な語彙と文法を習得し、簡単な会話ができ、また簡単な文を読み書きできるようになる
という目標を、受講生全員がほぼ達成できた。
受講生の上達ぶりを確信したのが、最終日の自由発表の時であった。事前にいくつかの絵を渡し、各自選んだ絵に関して自由に
ストーリーを作ってアカン語で発表することが課題だった。受講生全員が、1人5分以上かけて自作のストーリーを発表してくれたが、
その内容もさることながら、文法の正しさと発音のすばらしさに、私たち講師は驚嘆した。外国人講師は、「ガーナ人よりも上手い」
とほめたたえた(アカン語を第二言語として話すガーナ人は、文法や声調が間違っていることが多い)。
研修のもう一つの成果は、アカン語の本格的な教材を日本語で初めて作成したことである。今のところ英語で書かれた外国人向けの
テキストが2,3あるものの、表記が誤っていたり、書記法が不完全だったり、扱う事項が表面的であったり偏りがあったりと、
初心者の独習に使えるとはとても言えなかった。本研修向けに作成したテキストは、重要な語彙、文法を厳選し、詳しく解説している
ので、受講生だけでなく初心者の独習にも役立ててもらえると確信する。
今後の課題としては、まず、本研修を修了した受講生たちのために、中級・上級レベルの教材および学習環境を整備していく
ことである。実際、数人の受講生から、将来アカン語研修第二弾を開催してほしいという強い要望があった。
本研修には9名もの受講生が集まったが、これは、アフリカをフィールドとする研究者が増えていることや、ヨーロッパ諸語のような
公用語ではなく現地では現地語で話すという傾向の表れだろう。今後も増えると思われるアカン語やアフリカ諸語の教授に対する
要請に応えることも、私たちアフリカ言語研究者の1つの使命であると考える。
9. おわりに
修了式で、外国人講師のアンポンサーさんが、次のようにあいさつした。私が初めて日本に留学したとき、この日本で、
日本人に自分の母語を教える日が来るなど、想像もしなかった―。私自身、およそ10年間アカン語の研究に携わってきたが、
教えることになるとは考えたこともなかった。この記念すべき初のアカン語研修を担当させていただいたことを本当に幸せに思う。
そして、めでたく研修を修了した9名が、日本で、ガーナで、アカン語を思う存分使って交流や研究を進めてくれれば、
講師としてこれほどうれしいことはない。
研修に当たっては、多くの方々にお世話になった。外国人講師のアンポンサーさんは、博士論文執筆に忙しい中での仕事だった。
彼の温かく、ユーモアあふれる人柄が、終始授業を楽しく和やかなものにしてくれた。文化講演を快くひきうけてくださった
アサンテさん、テテさん、八木さん、それから100時間ともに学んだ9人の受講生の皆さんにも感謝したい。最後に、このような
貴重な機会を与えてくださったアジア・アフリカ言語文化研究所所長の栗原浩英先生、言語研修専門委員会委員長稗田乃先生を
始めとする委員会の諸先生方、情報資源利用研究センターおよび研究協力課の皆様に、心からお礼申し上げる。
![]()
アカン語文化講演
|