
▲展示パネル
クリックで拡大します |
■和紙(楮斐紙)に金属活字印刷した最古の例「日本のカテキスモ」(1586年、リスボン刊)
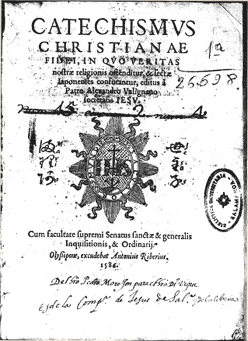 日本での漢字の印刷のはじめは、神護景雲四年(770年)百万塔陀羅尼と見るのが一般的ですが、これを「印刷」には分類しない説もあります。鎌倉、室町期の寺社の経典印刷は盛んですが、これは「漢字を用いた頁を版画として印刷するもの」で、文字としての漢字ー字ー字を、それぞれ独立に印字可能としたもの、つまり活字印刷ではありません。
日本での漢字の印刷のはじめは、神護景雲四年(770年)百万塔陀羅尼と見るのが一般的ですが、これを「印刷」には分類しない説もあります。鎌倉、室町期の寺社の経典印刷は盛んですが、これは「漢字を用いた頁を版画として印刷するもの」で、文字としての漢字ー字ー字を、それぞれ独立に印字可能としたもの、つまり活字印刷ではありません。
日本での「活字」印刷で最も古いのはイエズス会の「キリシタン版」で、金属活字とプレス印刷機で日本の和紙(楮斐紙)に刷版するという、東西テクノロジーの大胆な組み合わせによるものです。 この東西テクノロジーの邂逅の最古の例は1586年「日本のカテキスモ」(リスボン刊)。その後のイエズス会の漢字仮名交じり印刷の技術革新はめざましく、『落葉集』(1586年)、『ぎやどぺかどる』 (1599年)の行草・連綿体(字と字とを連ねて書く書体)の金属活字印刷技術は精細を極め、漢字数も2,500種を超え(現在の「常用漢字」は1,945字)、1600年の『朗詠雑筆』では、ついに書道手本自体を金属活字印刷するに至っています。
行書体や、それらを連綿させた字体を作ったのは、あたかも手写本のような外見を与えるためですが、欧文組版同様、プロポーショナルピッチ(字面に合わせた活字の間隔)で文字幅が変動し、しかも行末は揃えるという難題があるので、字ごとに丈の異なる複数の字体を用意して調整しています。一方、日本の古活字版(木活字版)は、活字の丈自体は固定し、1活字に詰め込む字数の方を変えて、この問題をあっさり解決しました。活字版の大欠点は、筆写本の持つ「墨継ぎ」の濃淡のリズムが活字版では表現しようがない事で、おまけに句読点もないため、(展覧中の「大鏡」のような)平仮名の勝った印字面では、いきおい「弁慶がなぎなた」式の誤読がしばしば生じます。活字版には、この対抗策として「連綿体」を活用した形跡があり、展覧中の「大鏡」巻2、5丁オモテ(左頁)2行目「めをしのごふ」(目、押し拭う) のように、「をし」を連綿にする事で「目を、しのごふ」のような誤読の回避効果も期待した可能性があります。キリシタン文献での、この「連綿による誤読回避」は徹底的で、語の切れ目で連綿が起る事は全くありません。一方、慶長〜寛永期古活字版ではさほど厳密でもなく、今後の研究が必要です。
|
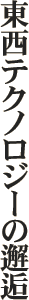 |