
▲展示パネル
クリックで拡大します |
中国古文字における甲骨文字
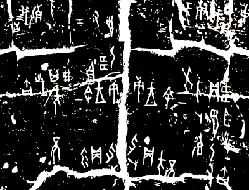 先秦時代の中国で用いられた諸種の文字は、書写材料にしたがい、おおよそ甲骨文(亀の甲や牛の肩胛骨等に刻まれた文字)、金文(青銅器の銘文)と簡帛文(竹や木の札および絹に書かれた文字)に分けることができます。 先秦時代の中国で用いられた諸種の文字は、書写材料にしたがい、おおよそ甲骨文(亀の甲や牛の肩胛骨等に刻まれた文字)、金文(青銅器の銘文)と簡帛文(竹や木の札および絹に書かれた文字)に分けることができます。
三つの中では、甲骨文は比較的古く、出土資料が限られた時間的・地域的空間に集中します。殷代後期の都と言われる、中国河南省安陽の「殷墟」の周辺で出土したものが大半を占め、その他は、陝西省岐山県のいわゆる「周原」で窖に埋蔵されていた西周初期の甲骨です。資料に纏まりがあって文例の相互比較を行いやすく、正確な言語学的分析が可能です。現代の筆跡鑑定を思わせる、書体の比較によって、資料は幾つかの類型に分けられます。貞人(占いを行う人)の名前が記されていない場合でも、その貞人が所属している筆者集団がおおよそ特定できるほどです。下に示すのは、「王卜辞」という種類の甲骨資料に関して、各類型を年代順に整理した表です(「武丁」等は殷王の名前)。
卜辞とは、「うらない」あるいは「占卜」の記録で、甲骨資料において大多数を占めます。殷には、青銅器の銘文が短く、簡帛等の書写材料を用いた文字資料も発見されていません。この状況において、卜辞を中心とした甲骨資料を基に綴られた殷王朝の歴史は常に神秘主義的な色彩を帯びます。しかし、中国特有の文書行政が高度な発展をみた戦国時代にも、例えば楚では、殷墟の卜辞にそっくりの占いの記録が竹簡に記されています。卜辞の発見が必ずしも神権政治と結びつかない証しであり、史料の気まぐれな残り方に惑わされてはいけないという警鐘とも言えます。
|
 |