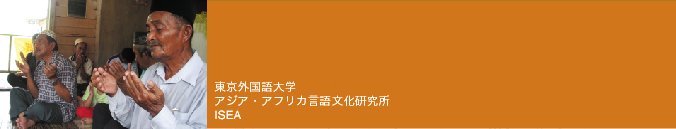
|
インドネシア語新聞翻訳 2010年12月19日(日) 【デティック紙】 イスラーム教義は「メリークリスマス」という挨拶を禁じたことはない 【デン・ハーグ】 ソフィヤン・シレガル教授は、ロッテルダムのナスハ・モスク管理者とヨーロッパのインドネシア・イスラーム教徒知識人協会(略称ICMI)との提携で金曜日〔12月17日〕に行われたイスラーム勉強会で発表された資料の内容を示しながら、本紙に対して土曜日(12月18日)にそのように述べた。 特にオランダ在住のイスラーム教徒にとって、〔キリスト教徒に対する挨拶である〕「メリークリスマス」という挨拶のルールについては、ほぼ毎年質問の対象になるため、このテーマは取り上げられる。 同教授によれば、コーランやハディースの中で、クリスマスの日などに非イスラーム教徒に対して挨拶や祝いの言葉を述べることをはっきりと禁じている節は一つもないという。 「それどころかコーラン『女性の章』の第86節(訳注2)では、イスラーム教徒は誰からの言葉であっても、〔相手が誰であろうと〕挨拶を返すように指示されている」とし、同教授はさらに述べた。 非イスラーム教徒に対して挨拶を述べてはいけないと宣言する人々は、コーランまたはハディースからの立論や論証を提示するべきだ。そしてそのような立論はない。 〔預言者ムハンマドの妻であった〕アイシヤーが伝えたハディースの中には「ユダヤ人やキリスト教徒に対して挨拶を述べてはいけない」と読み取れるものもあるが、これは当時のバニ・クライザー(訳注3)との戦いの背景や事情においてのことだ。 「同様に、非イスラーム教徒に関する禁止事項の多くは、一般に彼らがイスラーム教徒と戦っているか、あるいは戦闘態勢にあることと関連がある」と同教授は説明した。 特にオランダやヨーロッパ、インドネシアのイスラーム教徒は戦闘状態にはないため、異文化の人々と交流することは合法だ、と指示されている。 善、正義、公平、〔義務ではない〕慈善行為の一つの形とは、挨拶を交わすことを含め、人々が交流する際にはお互いを尊重し合うことだ。 このことは「試される女の章」第9節(訳注4)にも合致している。「啓典の民(訳注5)によって屠殺された動物を食べることは法的にハラルであり、啓典の民の女性と結婚することも法的に許されている。上記のことでさえ許可されているのだから、〔非イスラーム教徒への〕挨拶を禁じることはあり得ない」とこのイスラーム法分野の博士である同教授は述べた。 この〔章句の解釈の〕場合、イスラーム教徒と戦っている非イスラーム教徒との交流はハラムだ。したがって、戦闘の可能性のない非イスラーム教徒はその節の例外〔すなわちハラル〕とされるが、イスラーム教徒と戦っている非イスラーム教徒との交流は、法的にハラムだ〔そのため、ヨーロッパやインドネシアのイスラーム教徒は、戦闘状態にはないヨーロッパないしはインドネシアに住むキリスト教徒に対して「メリークリスマス」と挨拶することが許されていることになる〕。 戦闘の可能性のない非イスラーム教徒に対して挨拶を許可しているウラマ(訳注6)は以下のように数多く存在する。イブヌ・マスウド、アブ・ウママー、イブヌ・アッバス、アル・アウザイ、アン・ナコイ、アットバリなどだ。 訳注 (翻訳者:川名桂子) |