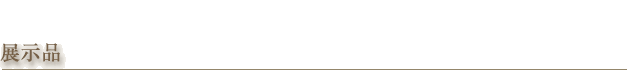 |
||||||
 [作品27]
[作品27]■カンダハールのアフガニスタン王、アフマド・シャーの廟 Temple of Ahmed Shauh, King of Afghaunistaun, Candaha (英語原文をよむ) この廟には、ドゥッラーニー部の創始者であるアフマド・シャーの遺体が収められており、王宮すなわち城塞(その稜堡(りょうほ)がここに描かれている)の近くある。そこは町から登っていく高台の上にあり、この町の代表的な建築物となっている。この廟は、素晴らしい形をしたドームと高いミナレットを持ち、白い石で造られ、六角形をしている。トルコ風のさまざまな大きさのアーチを持ち、色つきのタイルで装飾され、優美な色で彩られている。東洋の墓廟の豪華な意匠や妖精の造ったような華麗さに精通した目にとって、この建築にはありふれていない点はなく、その様式においても全く印象的ではない。しかし、それでも、独特の透明な空気のなかで見ると、この上品な建物は「雄牛のこぶ」山の暗い色合いの中に浮かび上がり、これが作り出す全体的な調和は非常に魅力的である。どんな芸術家も美を愛する人も、次のような全体の光景に添えられた驚くべき効果に魅了されずに、通り過ぎることはできないだろう。ラクダの長い列が、野菜や秣(まぐさ)をたくさん積んで、行き交っていた。前景を占めている絵のような材木や果物の商人たちが、膝を曲げた駄獣から荷物を下して、バーザールの人々や町の住人に商品を売り、あるいは交換しようとしている。商人達はまた、縞模様の日よけの下に座っているのが見え、朝の一服を喫いながら、国からのガプすなわち噂話を聞こうとしたり、お気に入りの闘鶏用のウズラを隣人のと戦わせたりしている。あるいは、新鮮なメロンや桃、葡萄や他の甘い果物を味わっているが、これらは彼らの廻りに大きな山のように積み上げられており、また、冷やすためにつるされて、この小さな店のテントの梁から誘惑している。 ■ウズラ さて、ウズラについて一言述べよう。1年のある季節においては、誰もが、どこにいてもまたどんな状態であっても、小さな鞄に入れて、不幸なウズラをぶるぶる震わせている。誇り高き族長は、訪問の式典の際に、ウズラをぶるぶる震わせている。馬丁はあなたの馬の手綱を引くと同時に、自分のウズラをぶるぶる震わせている。白髭の80代の老人は、杖を手におぼつかない足取りを支えていたが、彼もウズラをぴくぴくさせるために1本の指を残すことができる。バラ色の顔をした舌もよく回らない子どもたちも賭けに夢中になって、自分のウズラを2倍、3倍にぶるぶる震わせている。こうして絶え間なく続く行為は、もちろん、この小さな生物を苛ただせるが、こうして1日中閉じ込められても、勇気をもってこれに耐えると考えられている。ふさわしい相手と顔を合わせたら、両者をそれぞれの反対側におき、その間の地面に雑穀の餌を2,3粒おく。それから輪が作られ、大勢が多額の賭をする。彼らは、生き死にと同じくらいに、賭の結果に興味を持っている。小さな嘴で餌を突く最初の一突きが、挑戦を意味し、戦いが始まる。ウズラは非常に猛々しく戦い、しばしば、どちらかが死ぬまで戦う。 ■インヴェラリティーの殺害 「雄牛のこぶ」 を再びこの絵の中で紹介する。我々が最初にアフガニスタンを占領した際、軍がカンダハールに宿営していたとき、私の従兄弟で第16女王槍騎兵連隊のウィルマー大尉は、山の向こうの谷での釣りから山道(山の左側である)を帰る途中、危うく殺されそうになった。彼は、友人で同僚のインヴェラリティーと一緒だったが、彼はウィルマーの少し前に隘路に入り、ウィルマーの小さな毛のこわいテリアがそれに続いた。不運なスポーツ仲間に追いつこうと急いでいたところ、ウィルマーは自分の犬が急に戻ってきたのに驚いた。犬は山道の入口から彼に会うために飛び出してきて、異常に動揺して、哀れそうにクンクン鳴いていたのである。このことで、彼はよからぬことが起こったとわかった。しかし、彼は先へ進み、岩だらけの道を登っていると、急に武装したドゥッラーニーの攻撃を受けた。彼の友人はすでに滅多切りにされていた。彼が飛び越えたこの友人のずたずたの命を絶たれた遺体は、道を塞ぐ障壁となっていた。暗殺者は8人ほどであり、彼の足下はおぼつかず、彼の防御のための武器は短い桜の杖だけであった。彼をねらった打撃をかわすために樹皮まで斬りつけられたものの、この杖が彼の命を救ったのである。というのは、この杖で何人かの暗殺者を打ち倒し、彼の気持ちの強さと命がけの防御の結果、利口なお気に入りの犬と一緒に彼は無傷でキャンプに戻ることができた。可哀相なインヴェラリティーの遺体は後ほど回収され、宿営地と殺害された場所の間に埋葬された。この犯人達が、やがて捕まり、処刑されたことを知って満足である。 ■アフマド・シャー・ドゥッラーニー しかし、私はアフマド・シャーの廟に戻らなければならない。ここで眠っている王はアフガン人から「無謬な王」と呼ばれており、彼らの国が生んだ偉大な君主であった。敵、味方を問わず、あらゆる東洋諸国の人々の間では、今でも彼の軍事的才能、心の高貴さ、寛大さ、決断力などが、非常な敬意を込めて、未だに語りぐさとなっている。彼の美徳の多さは、彼が勝利の数と同じくらい多かった。彼の勝利のなかにはデリーの征服が含まれている。アフマド・シャーは息子のティームールとともにヤムナー川を渡った後、マラーター勢力との激しい戦いののち、1759年にこの町を陥落させた。マラーター勢力は首都を奪回し、パーニパットに陣取って、ドゥッラーニーの王と対峙すべく準備を整えた。アフマド・シャーは少ない軍勢と2、3の大砲で、10万の兵と200の大砲を擁したマラーターのほとんど全軍を壊滅させた。こうしてインドはアフガン人の慈悲にすがることになった。しかし、政策と寛容さが、あまりに遠い地域で、彼にそれ以上、勝利を広げることをゆるさなかった。一方、彼の敵であるシク教徒たちは、その星は昇りつつあり、彼自身の山岳地方と彼の力による征服の場との間に位置していた。そして、彼の不在の間に本国では反乱が広まっていた。そこで、彼にしたがって戦ったインドの有力者たちに重要な地位を委ね、1761年に首都であるカンダハールに帰った。後に、彼は傲慢で増長していたシク教徒達を懲らしめるためにパンジャーブに戻り、彼らを派手に打ち破った。そして再び首都に戻り、そこで1773年ここで顔の癌のため亡くなった。彼はその科学や軍事の技術に加えて学問を好み、学者や宗教者を援助した。 ■墓廟の聖性 晩年になって、彼は聖者になりたいと強く願っていた。これについては陛下の望みはかなえられた。というのは、彼の廟は完璧な聖性を持っているとみなされており、貴人や有力者がこもるための場所として頼られているからである。彼らはこの世界に不満であったり、疲れていたりして、ここで信仰を告白して瞑想し、祈るのである。また、しばしば、殺人者やあらゆる程度の犯罪者の避難所としても用いられ、正義も権力も地位も、王自身の手ですら、ここでは彼らを苦しめ、手を出すことはできない。私が信じるに、未だにいかなるヨーロッパ人もこの神聖な建物の敷居をまたぐことを許されたことはない。私も、他の人々同様、しばしば試みたのだが、我々が不信仰者の頭を外庭に見せるやいなや、それは、そこに多数いるムッラーたちやハーッジーたち(巡礼者たち)にとっての合図であり、彼らはシッシッと嫌悪の叫び声をあげて、我々を追い出したのである。アフマド・シャーのあとはマシュハド生まれの彼の息子ティームールが次ぎ、カーブルを彼の領国の首都とし、ここで亡くなった。 ■英軍騎兵の健闘 ドゥッラーニー部は、素晴らしいその不正規騎兵によって称えられており、非常な疲労に耐え、非常に長い行軍をこなすことができた。カンダハールの諸地区では、彼らはその大胆かつ突然の攻撃で我々を絶えずなやませ、軍のこの部門における不十分さを彼らが完全に悟ると、その攻撃は増えた。我々にとって不幸なことに、このあたりは平坦で、騎兵の移動や配置に特に適しており、あらゆる機会に数え切れない数の集団を彼らは戦場に投入した。彼らが我々に数的に上回っていたという優位は認めるものの、私は我々自身の小さな正規・不正規の騎兵隊に全くの賞賛を与えずにはいられない。彼らはこの賞賛を立派に勝ち取ったのであり、ほとんど例外なく賞賛は彼らに与えられたのである。数において少なく、彼らは遠征の間中、戦場においても宿営においても、果てしない困難に直面した。彼らには多くのことが期待されていたが、過労が続き、飼葉が不足した結果として彼らが体力的な弱さに苦しんでいるときには、何も彼らの務めをより効果的にせず、より大きな意欲や快活さをもたらすこともできなかった。 ■ドッラーニー騎兵 完全装備ドゥッラーニーの騎兵のゴル すなわち部隊は目に心地よいものである。小さな密集体形で進む際に、何と立派に見えることだろう。彼らの軍馬の技術、長くなびく髭と整った顔立ち、色とりどりの長衣にゆったりと覆われた頑健な体、あらゆる形と結び方のターバン。精巧に作られた武器が彼らの腿と背中からぶら下がる。鉄の胴甲、鎖帷子(かたびら)と羽根飾りのついた兜を身につけているものもいれば、ペルシアの羊皮の帽子や金色の帽子を被っている者もおり、彼らの真っ黒な髪の毛がその下から豊にはみだしていた。今、槍と三日月刃を振り回し、紋章の入った刺繍の施された旗を高く掲げ、彼らは手綱を引いて派手に飾った馬を半回転させ、あるいは飛び出して、手綱を握ったまま歓喜の叫びを上げてライフルを撃つ。どの騎手もよく喋り、感情と身振りにあふれている。彼らの銀の突起のある金属で覆われた鎧は陽気に音を立て、彼らの太鼓は軍の行進に拍子を合わせる。 |


