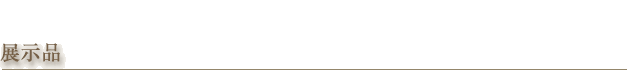 |
||||||
 [作品3]
[作品3]■シャー・シュジャー・アル=ムルクの宮殿の内部 Interior of the Palace of Shauh Shujau ool Moolk (英語原文をよむ) シャー・シュジャー・アル=ムルク(世界の勇敢な王)は、ティームールの年少の方の息子で、アフマド・シャーの孫であった。彼はシャー・ザマーンの弟であったが、ザマーンは、自分の[異母]兄であり、年長のゆえに王位を約束されていたフマーユーンを打ち破り、彼を盲目にして王位に就いた。ザマーンは、今度は彼の異母兄弟であるマフムードによって捕らえられ、マフムードはジャグダラクの森の中で、彼の両目を刃針で突き刺して、カーブルのバーラー・ヒサールに彼を監禁した。シャー・マフムードは彼の異母兄弟であるシュジャーによって退位させられ、盲計は免れたものの、バーラー・ヒサールに監禁された。この次はシャー・シュジャーが王位を失った。その後、何度か王位奪還を試みたが、失敗に終わり、彼は逃亡した。つまり、あるバーラクザイ族の貴人によって呼び戻されたが、おり悪く示した極度の虚栄心のため再び王位を失ったのである。彼の兄弟であるアイユーブ(ヨブ)が代わりに王位に就いたが、ドースト・ムハンマドによってその座を追われた。ドースト・ムハンマドはイギリスによって退位させられ、その座を、幾度も王位から退けられた不人気のシャー・シュジャーに譲ることとなった。最終的にシャー・シュジャーは、暗殺の犠牲となり、カーブルの暴動の際に殺された。彼の息子であるファトフ・ジャングとシャープールが引き続き数日間統治したが、国から追放されてラーホールの敵方の宮廷に亡命を求めた。その後、アフガンのクロムウェル[ドースト・ムハンマド]が支配権を再び得て、それをいまだ保持し続けている。 ■シャーの行列 私がシャー・シュジャーに初めて会ったのは、彼が冬の宮殿のあるジャラーラーバードから、夏の王宮のあるカーブルへの行進中で、廷臣やイギリスの使節団、そして軍隊に付き添われていた。全軍は陛下の首都への帰還を歓迎するために駆り出されたが、その催しのすさまじい壮観さは筆舌につくしがたい。私はチャマネ・シャー、すなわちスィヤーフ・サングの山々の狭い峠の上にいたが、ジャラーラーバード街道から絵のように美しい、さまざまな色の従者たちがそこへ入ってきた。まっさきに、引き具に鈴を付けて、まどろむような歩みにあわせて鈴を鳴らし、長々と伸ばした首に房を取り付けられ、装飾品で飾られた、ヒトコブラクダが現れた。旋回軽砲を運ぶ数百のヒトコブラクダがいた。各々の軽砲は緑と緋色の旗で飾られており、その旗は野蛮に見える乗り手たちの周りではためいていた。その乗り手たちはラクダの上に座り、顎鬚、粗毛の帽子がかろうじて人間に見える彼らの顔にうっとうしく被さっているが、弾薬をいい加減に彼らのジャンジャール 砲、すなわち砲台付軽砲に込めてしゃがれ声のとき鬨の声とともに気ままに発砲した。結果として、多くの乗り手がほぼ佐官になれ、喜びのあまり、この世のものとは思えぬような狙撃兵たちは、羽飾りはとりさり、頬髯を焦がした。この大音響の砲兵隊の通過に続き、王室の馬たちが、金と宝石が散りばめられた馬飾りを煌めかせながらぴたりと続き、それぞれ手で曳かれていった。その後、王室家政官、刑罰執行官、そして棒、剣、太鼓、旗の持ち手が、鋭く尖った角のある緋色の帽子を被ってやって来て、道を塞ぐことによって道を開きつつ、混乱を引き起こすによって秩序を回復しつつ進んでいった。ガチャガチャと音をたてて進むアフガンの騎兵部隊がその後に続いた。彼らは、頭からつま先まで羽飾りをつけて武装して、太鼓を打ち鳴らし、通り過ぎる際には突起のある装飾された馬具が音を立てていた。その後には、脚を露出した長髪の厩番たちが続いた。その後には、特命全権公使の護衛である、青と銀色の騎兵部隊の一団が堂々と進み、その後に陛下その人がいた。 ■シャーの服装 シャーの騎乗ぶりは堂々たるもので、立派に背筋を伸ばして座っていた。彼はどこからどこまで王に見えた。皇帝のビロードの帽子、すなわち王冠(コラーフ)には、その上部から伸びた枝にエメラルドのペンダントの葉がつき、彼の額を取り囲み、高価な宝石の数々が帯をなして煌いていた。その衣装は体にぴったりとした紫の繻子織りのチュニックで、金と宝石が刺繍されていた。そして、肩から手首まで宝石類でびっしり覆われた腕輪がいくつもはめられていた。つま先の尖った鉄のかかとの高い粒起なめし革製のブーツ、そして薄く精密なカシミヤショールの腰帯、そしてそこから華麗なイスファハーンの偃月刀(えんげつとう)が吊るされ、その中にものものしい短刀(ペーシュカブズ)が差されて、彼の盛装は完成していた。シャーは容姿端麗で、身なりも良かったので、誰もその年齢を推測することはできなかった。肌の色は明るい褐色がかったオリーブ色であった。顔つきは、過度な尊大さにもの悲しさが混ぜ合わさっているのが特徴であった。端正な眉、切れ長の黒い目、そして漆黒の顎髭が表情を十倍に豊かにし、その顎鬚の長さと見事さは語り種となっていた。耳から豊かに垂れ下がり、まっすぐに座っても、彼の宝石で飾られた鞍の上を掃くほどであり、ただの1本になるまで先が細くなっていたのである。 ■お付きの者たち 陛下はウィリアム・マクノーテン士爵に話しかけた。マクノーテン士爵は陛下の少し右手後方で騎乗しており、シャーザーダたち(皇子たち)と一緒であった。その後にはニザーム・アッ=ドウラ(国家の柱)と他の高官たち、将軍たちが、家来などとともに、ターバン、三角帽子、羊毛の帽子、かぶと、椀型の帽子、丸い帽子、そしてチャークー を身に付けた名士たちの絵のような一行の流れとなって続いた。東の宿営地に常駐しているベンガル軽歩兵連隊、不正規連隊、アフガン騎兵連隊が圧倒的な多数で取り囲み、一行のしんがりを務めていた。王の一行がカーブルの狭く曲がりくねった道を通った時には、すべての戸口、窓、そして屋根は、ファランギー(ヨーロッパ人)の王と呼んだところの王を見ることを切望した見物人で混雑した。多くの佳人たちがしっかりとヴェールをまとって、平らな屋根の上でいくつも列を成していたが、無数の生きている幕の壁のようで、筆舌に尽くしがたい。女性たちも、各々の氏族を示すきらびやかで絵のように美しい衣装をまとって群れをなしている男性も、この機会に喜びや忠誠心をみじんも見せることはなかった。むしろ逆に、すべての者たちは静止して立ち、腕を胸のところで組みながら数珠を数えて、無言のまま執拗に見ていた。幾人かの老齢のムッラーのつぶやいた王のための祈りの言葉。嘆願を王の耳に届けようと試みて失敗したものの慌てた声。騎兵の馬の蹄の音。シャーヘ・ドッラエ・ドゥッラーニー[ドゥッラーニーの真珠の王]、シャーたちの中のシャー、ドゥッラーニー朝の真珠たる王の権力、美徳、威厳を称揚する官僚の大声。これらを除いては沈黙を破るものはなかった。 ■宮殿にて 宮殿に到着すると、騎馬隊全体が停止して下馬し、陛下がゆっくりと威厳をもって鞍から降りた。将校たちの肩に半ば寄りかかるようにして、彼は謁見(えっけん)場に続く階段を上り、そして、我々の上のムーア式アーチの窓に現れ、以前と同じように彼の大理石のタフト、すなわち玉座に支えられていた。彼がみずから座ると、自動操作のように彼の顔が一連の極端な自尊心に満ちた表情を形作り、大砲が鳴り響いた。ウィリアム士爵と彼の部下たちは、羽毛で飾った三角帽子を低いお辞儀の際に地面に振り下ろし、将校たちは右手を敬礼のために上げた。しかし、これらの我々の忠誠を示す態度に最低限の返礼や挨拶もなかった。強大な大英帝国の代表団にたいして、半分閉じられた目でちらりと見ただけで、すぐに王の表情はその高慢な無関心さを取り戻した。長い静止が続き、手の動き方でわかるもう結構だという軽い身振りで、我々を神聖な御前から追い出した。無知な我々には最も無礼な謁見であると思われるものに、少なからずむかむかした。 その玉座は大変に古いものであると言われている。それは八角形で白い大理石から作られ、脚で支えられており、同じ素材の踏み台があった。王が座った際には、下の四角い中庭より臣下は王の姿を見ることができる。窓のアーチと柱は木製で、彫刻が彫られ絵が画かれている。その部屋の側面は、きらびやかな漆喰の上にさまざまな模様の浮き彫り細工が施された壁龕(へきがん)で埋められている。そして、天井には花々や渦巻きの装飾がふんだんに描き加えられている。 ■翌年の宮廷 私がカーブルを訪問した翌年に、なんと恐ろしい革命が起こったことだろう。王、公使、駐在官そして政務官、将軍や兵士、すべてが殺害され、一掃されてしまった。つまり、世界における最も誇り高き君主の宮殿は軍人たちの存在により汚されたのである。神聖な玉座、談話室、コイン・ゲームの台。そして、今や、アーチ型の窓にはまさしくその将校たちの幾人かが群がり、煙草を吸ったり、おしゃべりをしたりしている。彼らは即位の儀式の際に、大変卑しい者の場に位置し、彼らが踏み歩いた床の如く、高貴な王にはほとんど気付かれることはないような下手に立っていた。アフガン人たち自身でさえ、宮殿のかつての聖性を忘れ去ってしまっていた。というのは、私が内部をスケッチした際に、幼いシャープール皇子(我々が王として残した、亡きシャーの末の息子)のワズィールは、また王家と同じ部族に属していたが、当の大理石の玉座に長々と寝そべり、娯楽のために跳ね回ったり、曲芸を演じたりする宮廷の道化の戯れ言に聞き入っていた。絵の中では彼はそこに座って描かれている。シュジャー! シュジャー! このように汝自身のサドーザイ族があっけなく汝を忘れた時、汝の栄光はまさに失われたのだ。あまりに確かに汝の家系の王位は永遠に失われた。 |


