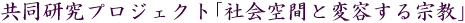 |
| 丂 |
| 崱屻偺尋媶夛偵偮偄偰 |
| 丂 |
| 袎飲髪詠v傪偳偆峫偊傞偐丂惣堜檡巕 |
| 丂 |
| 丂偙偺嫟摨尋媶僾儘僕僃僋僩偺偐偐偘傞乽幮夛嬻娫乿偲偄偆奣擮偵偮偄偰丄壗傪偳偺傛偆偵柧傜偐偵偡傞偙偲傪傔偞偟偰偄傞偺偐傪彮偟惍棟偟偰偍偒偨偄丅 |
| 丂 |
| 嘥丂栤戣愝掕偺攚宨 |
| 丂傑偢丄乽幮夛嬻娫乿偲偄偆僞乕儉偺敪憐偺攚宨偲側偭偨偺偼丄嬤擭偺媫懍側僌儘乕僶儖壔偱偁傞丅崱擔丄悽奅偺帄傞偲偙傠偱宱嵪丄幮夛丄暥壔偵傢偨傞僌儘乕僶儖壔丄偍傛傃偦傟偵偲傕側偆嬤戙揑側傞傕偺偑恖傃偲偺惗妶偵媫寖偵攇媦偟偰偄傞丅摿偵忣曬嶻嬈偺媫懍側奼戝傗徚旓幮夛偺弌尰偼丄奒媺揑丄柉懓揑側嵎堎偁傞偄偼抧堟娫偺奿嵎偺暆傪峀偘傞偲偲傕偵丄恖乆偺幮夛揑宱尡偺懡條壔傗戝婯柾側堏摦丄儌價儕僥傿傪惗傒偩偟偰偒偨丅偲傝傢偗搶撿傾僕傾偱偼丄1980擭戙屻敿埲崀偺媫懍側宱嵪惉挿偲偦傟偵懕偔1997擭偺捠壿婋婡傪宱尡偡傞側偐偱丄偦偺嬤戙惈偺偁傝曽偼扨慄揑側惉挿恄榖偱偼側偔暋嶨側條憡傪帵偟偰偄傞丅堦斒揑偵丄惣墷幮夛偵婲尮偡傞乽嬤戙壔乿偲偄偆晛曊揑側揮姺儌僨儖偼丄廆嫵傗庺弍偐傜偺夝曻丄崌棟揑側抦幆偲僔僗僥儉偺宍惉傪婎慴偲偟丄廬棃偺姷廗傗揱摑偵巟偊傜傟偨幮夛偑柉庡庡媊丄姱椈惂搙丄帒杮庡媊惗嶻僔僗僥儉偲偄偭偨儊僇僯僘儉偵抲偒姺偊傜傟偰偄偔夁掱傪偝偟偰偄傞丅偨偟偐偵乽嬤戙壔乿偼幮夛偺嬒幙壔偵岦偐偆嫮戝側椡偲偟偰嶌梡偟偰偒偨偑丄偦傟偵捈柺偡傞恖傃偲偺懳墳偼偐側傜偢偟傕嬒幙揑偱偼側偄丅椺偊偽嬤擭丄搶撿傾僕傾偱偼惣墷儌僨儖偲偼堎側偭偨嬤戙惈傪庡挘偡傞僀僗儔乕儉暅嫽塣摦傗暓嫵僫僔儑僫儕僘儉偑崙柉崙壠偺榞傪墇偊偰嫽棽偟偮偮偁傞丅傑偨崙嵺揑偁傞偄偼僩儔儞僗丒僫僔儑僫儖側楢実偵婎斦傪偍偔NGO傗NPO側偳偺柉娫慻怐偺戜摢偼丄奺抧偺揱摑暥壔傗姷廗偁傞偄偼抧堟幮夛傪撈帺偺嬤戙惈偺側偐偱嵞曇惉偡傞廳梫側栶妱傪偼偨偟偮偮偁傞丅偁傞堄枴偱偼丄愭擔偺傾儊儕僇偺摨帪懡敪僥儘偱傕柧帵揑偵帵偝傟偨傛偆偵丄嬒幙側庡懱偲偟偰偺崙柉崙壠偼偡偱偵廔傢傝傪偮偘丄偝傑偞傑側儗儀儖偺偝傑偞傑側庡懱偑嶖憥偟偰丄偄傑傗惗妶悽奅傪峔惉偟偰偄傞偲傕偄偊傞丅偦偆偟偨僌儘乕僶儖壔偵敽偆怴偨側帠懺傪懆偊傞偺偵廬棃偺曽朄榑傪尒捈偡昁梫偑偁傠偆丅 |
| 丂 |
| 嘦丂曽朄偲偟偰偺乽幮夛嬻娫乿 |
| 丂揱摑揑側恖椶妛偺峫偊偱偼丄恖傃偲偑嫃廧偡傞応強傗娐嫬丄偦偙偵偍偗傞斵傜偺巚峫傗峴堊傪偁偨偐傕帺慠揑偵峔惉偝傟偨僙僢僩偲偟偰懆偊傛偆偲偟偰偒偨丅偦偺傛偆側尋媶曽朄偼柉懓丄抧堟傗廤抍傪慡懱榑揑偵懆偊傞乽僐儈儏僯僥傿尋媶乿偲尵傢傟傞丅偙偺尋媶僾儘僕僃僋僩偼僐儈儏僯僥傿尋媶偑慜採偲偟偰偒偨応強丄恖丄峴堊傪摑堦揑偵昤偔慡懱榑偐傜扙媝偟丄恖傃偲偺巚峫偲峴堊偑怴偨側堄枴偲壙抣傪嶌傝忋偘惗惉偟偰偄偔乽幮夛嬻娫乿偲偄偆奣擮傪峫偊偰傒偨偄丅偙傟偼傾僷僪僁儔僀偺偄偆扙椞堟壔偝傟偨儘乕僇儕僥傿偲偦偺僱僢僩儚乕僋偐傜側傞偲峫偊傞偙偲傕偱偒傛偆丅乮偪側傒偵傾僷僪僁儔僀偼尰戙悽奅偵偍偗傞locality偺惗嶻偵捈愙塭嬁傪媦傏偡俁偮偺梫慺偲偟偰丄 |
| 丂 |
| 尃椡乗崙柉崙壠 |
| 恖乗僨傿傾僗億儔偺棳傟 |
| 儊僨傿傾乗揹巕丒償傽乕僠儍儖丂僐儈儏僯僥傿丂傪偁偘偰偄傞丅乯 |
| 丂 |
| 偙偆偟偨僌儘乕僶儖壔偵傛偭偰壗偑偐傢偭偨偐傪師偺擇偮偺儗儀儖偱峫偊偰傒傞丅 |
| 丂 |
| 嘆 幮夛娭學 |
| 嘇 尃椡丄崙柉崙壠 |
| 丂 |
| 嘆 偼丄愭傎偳偁偘偨廬棃偺僐儈儏僯僥傿丒僗僞僨傿乕僘偺慜採偱偁傞丄応強丄恖丄峴堊偑帺慠側僙僢僩偲偟偰暔徾壔偝傟偨乽抧堟local乿丄傑偨僄儕傾丒僗僞僨傿乕僘偵偍偗傞抧棟揑嬫暘丄暥壔揑嵎堎丄崙嫬偑堦抳偡傞偲偄偆慜採偑惉棫偟側偄偲偄偆偙偲丅嘇偱偼椡丄崙柉崙壠偱偼丄屄恖偲崙壠偺娭學偑偔偢傟偰偍傝丄傑偨尃椡偺偁傝曽偵偮偄偰傕尃椡偼屄乆偺屄恖偵娧揙偡傞偺偱偼側偔丄恖乆偼條乆側嵎堎傪娷傫偩僱僢僩儚乕僋偵帺桼偵偮側偑偭偰偄偔幮夛揑僗儁乕僗偑惗傑傟偰偄傞偲偄偆偙偲傪偁偘偨丅 |
| 丂 |
| 慃撪曬崘丗幮夛壢妛偵偍偗傞乽幮夛嬻娫乿偺壜擻惈 |
| 丂 |
| 丂幮夛嬻娫偵偳偆傾僋僠儏傾儕僥傿傪梌偊傜傟傞偐丅 |
| 傑偢丄乽幮夛嬻娫乿偑偳偺傛偆偵巊傢傟偰偄傞偐傪傒傞偲丄恖暥抧棟妛偵偍偄偰偼丄乽幮夛娭學偲娐嫬偺娭學乿丄寶抸妛偵偍偄偰偼搒巗寁夋側偳偱乽嬻娫偲恖娫乿偺娭學丄偝傜偵搒巗幮夛妛傗僒僀僶乕丒僗儁乕僗側偳偱傕巊傢傟偰偄傞丅乽幮夛嬻娫乿偲偄偆僞乕儉偼丄偠偮偼僨儏儖働乕儉偺幮夛暘嬈榑偵傕巊傢傟偰偄傞偑偦偺梡偄曽偑偙偺尋媶夛偱偺巊偄曽偲偼堎側偭偰偄傞丅偙偙偱偼丄傑偢乽幮夛嬻娫乿偲偄偆僞乕儉偵傛偭偰丄憡屳偵堎幙側幮夛娭學偑揥奐偝傟丄偦傟偑嫟懚偟偰偄傞偲偄偆堎幙側応偺嫟懚傪峫偊偰偄傞丅乽幮夛嬻娫乿傪巊偆偙偲偱壗偐傜扙弌偟傛偆偲偟偰偄傞偐傪柧傜偐偵偟偰偍偔昁梫偑偁傞丅 |
| 丂 |
| 侾丂幮夛峔憿傪偸偗偩偟偰幮夛嬻娫偵岦偐偆丅 |
| 丂幮夛峔憿偼宱尡揑偵拪弌偝傟傞偑丄榑棟揑偵偼宱尡揑側傕偺傛傝愭偵偁傞丅偦傟偼挻墇揑側儗儀儖偵偁傞儌僨儖偲偄偊傞丅幮夛嬻娫偼丄宱尡偦偺傕偺偺拞偵偁傞傛偆側撪嵼揑幮夛揑僾儘僙僗偺拞偱昤幨傪峴偆丅乽幚慔僐儈儏僯僥傿榑乿偼偙偺尋媶夛偺搚戜偲側傞柉攷偱偺尋媶夛偱媍榑偝傟偨傕偺偩偑丄傗偼傝幮夛峔憿傪扙弌偟偰撪嵼揑幮夛夁掱偺昤幨偵傓偐偭偰偄傞丅偦傟偼丄尵梩傪曄偊傞偲晹暘揑僀儞僞儔僋僔儑儞偺拞偱慡懱偑嶌傜傟偰偄偔僾儘僙僗傪傒傞丅奜偐傜懆偊偰偄偔偺偱偼側偔丄嬊強揑儌僨儖丄儘乕僇儖側偲偙傠偐傜峫偊偰偄偔丄挻墇揑儌僨儖偺晄壜擻惈傪巜揈偟偰撪嵼揑僾儘僙僗傪懆偊傞昁梫偑偁傞丅 |
| 丂 |
| 俀丂摨幙偺傕偺偱偼側偔丄憡屳偵堎幙側憡屳娭學傪懆偊傞丅 |
| 丂儅儖僋僗庡媊側偳偼憡屳偵堎幙側傕偺偑偁偭偰傕曎徹朄揑偵慡懱偑摑堦偝傟傞偲峫偊傞丅偟偐偟丄偙偙偱偼昁偢偟傕慡懱偑摑堦偝傟傞偲偼峫偊側偄丅杮幙揑偵僿僥儘僕乕僯傾僗偱偁傞嬻娫傪峫偊傞丅偁傞堄枴偱暋悢惈丄応強丒峴堊丒恖偑帺慠側僙僢僩偲偟偰暔徾壔偝傟偨抧堟丄儘乕僇儖偐傜偦傟偲暿偺儗儀儖偵偁傞儅僗儊僨傿傾傗崙柉崙壠丄悽奅揑儅乕働僢僩側偳傪摨帪偵攃埇偟偰丄偦偺娫偵偁傞旝柇側偢傟傗嫟斊娭學傗掞峈側偳傪丄慡懱傪壖掕偟側偄偱攃埇偡傞丅堎幙側傕偺偑嫟懚偡傞偲偄偆偙偲傪偳偆懆偊傞偺偐偲偄偆偙偲傪栤戣堄幆偲偟偰傕偭偰偍偔丅棟榑揑偵惍棟偟偰偄偔夁掱偱偳偆偟偰傕慡懱傪摨幙側傕偺偵娨尦偡傞孹岦偑偁傞丅椺偊偽丄奐敪傗椣棟傪峫偊傞偲偒偵傕暥壔偺懡條惈傪挻偊偨晛曊揑側壙抣傪偍偟偮偗傞埑椡偑偁傞丅懡暥壔嫟惗偲偄偭偰傕丄懡暥壔傪擣傔傞偲偄偭偰傕嵟廔揑偵偼晛曊揑側壙抣傪捠偠偰嵞摑崌偟偰儂儌僕乕僯傾僗側傕偺偵偟偰偄偔孹岦偑偁傞偺偱偼側偄偐丅暋嶨宯偱傕嵟廔揑偵偼宱嵪尨棟偵娨尦偡傞傛偆側尋媶偑偨偔偝傫偁傞丅幮夛壢妛偵偍偗傞乽嬻娫乿偼丄僯儏乕僩儞偺愨懳嬻娫偲偄偭偨嬒幙揑側嬻娫丄儗償傿亖僗僩儘乕僗側偳傕偙偆偟偨嬻娫傪慜採偲偟偰偄偨丅嬒幙揑偱儂儌僕乕僯傾僗側嬻娫偺僀儊乕僕偲寛暿偟側偗傟偽偄偗側偄丅帺慠壢妛丄揘妛丄悢妛側偳杮幙揑偵僿僥儘僕乕僯傾僗側傕偺傪撪曪偟偨嬻娫偑弌偰偒偰偄傞丅恖椶妛偼僄僗僲僌儔僼傿乕側偳偱丄娨尦偱偒側偄僿僥儘僕僯僥傿傪幚慔揑側暥壔憡懳庡媊側偳偰採弌偟偰偒偨丅乽幮夛嬻娫乿傪峫偊傞拞偱偦偙傪偳偆懆偊傞偐偲偄偆栤戣採婲傪偟偰偍偒偨偄丅 |
| 丂 |
| 惣堜丄慃撪偺曬崘偵懳偟偰丄乽幮夛嬻娫乿傪條乆側帪戙條乆側抧堟偵揔墳偱偒傞傕偺偲峫偊傞偐偺偐丄偦傟偲傕俋侽擭戙偺怴偟偄尰徾傪夝柧偟偨偄偲峫偊傞偺偐乮柤榓乯丄嬻娫偲偄偆偺偼嬒幙揑僀儊乕僕偑偁傞偺偱丄傓偟傠儘僇儕僥傿偺曽偑僿僥儘僕僯僥傿傪偁傜傢偡偵偼傛傝嬤摴丄儘僇儕僥傿偑惗惉偡傞応偲偟偰偺嬻娫側傜偽尵梩偲偟偰偼丄婔壗妛揑僀儊乕僕偱棟夝偱偒傞偑丄応偲旕応乮旕応偼嬶懱揑偵偄偆偲恖乆偑摦偄偰偄傞偙偲偦偺傕偺傪旕応偲偄偆偑丄摦偒偼応傪敽偆乯偲偄偊偽偡傓乮撪杧乯偲偄偭偨媈栤傗僐儊儞僩偑側偝傟偨丅 |
| 丂傑偨丄側偤嬻娫偲帪娫偲偄傢偢嬻娫偩偗偵偟偨偺偐乮愳暲乯偲偄偆幙栤偵懳偟偰偼丄俁師尦偺嬻娫傪帪娫傪娷傔偰係師尦嬻娫傊偲悢妛揑偵峫偊傞偲偄偄丅僯儏乕僩儞揑側愨懳嬻娫偱偼丄帪娫偲嬻娫偑敾慠偲偟偰偦偺栤戣偑偱偰偔傞丄偦偺嬻娫偺僀儊乕僕偐傜寛暿偡傟偽偦偺栤戣偼偍偙傜側偄乮慃撪乯偲偺夞摎傕帵偝傟偨丅 |
| 丂傑偨丄擣抦壢妛偺曽偐傜偺乽嬻娫乿偺懆偊曽偵偮偄偰偼丄崅栘嫟摨尋媶堳偐傜師偺傛偆側僐儊儞僩偑偁偭偨丅 |
| 丂嬻娫偼恖娫傕娷傫偩摦暔偺堏摦壜擻惈丄娭學壜擻惈偵傛偭偰偟偐掕媊偱偒側偄丅媋偵偲偭偰偺嬻娫丄擫偵偲偭偰偺嬻娫偲偄偆傛偆偵掕媊偝傟傞丅僄僀僕僃儞僩偺峴堊壜擻惈偑寢壥揑偵嬻娫傪掕媊偟偰偄偔丅摦暔偺峴堊壜擻惈丄恎懱偲悽奅偑僙僢僩偵側偭偰掕媊偝傟傞丅夛嬻娫傕嶌摦偵傛偭偰暵偠偰偄偭偰丄寢壥偲偟偰嬻娫偑惗惉偝傟偰偄偔埵憡嬻娫偺傛偆側傕偺偲偟偰僀儊乕僕偝傟傞丅嬻娫偺栤戣偼丄帪娫偺巜揈偑偁偭偨偑丄嬻娫偺側偐偱偱偼側偔丄嬻娫偑惗惉偟偰偄偔丄堎幙惈傕偡偱偵擇偮偺懚嵼偡傞嬻娫偑偁傞偲偄偆偱偼側偔丄嶌摦偵傛偭偰堎幙側傕偺偑惗惉偝傟丄寢壥揑偵僿僥儘僕乕僯傾僗側嬻娫偑惗惉偟偰偄偔丅摉偺峴堊幰偵偲偭偰偼嬻娫偺嫬奅偑尒偊側偄丅偲偙傠偑偦偙偵嬻娫偑偁傞傛偆偵擣幆偟偰偟傑偆偲偄偆偺偑幮夛偺晄巚媍丅撪嵼惈偲堎幙惈傪娷傔偰幮夛嬻娫偺栤戣傪峫偊傞偲丄摉偺峴堊幰偺僷乕僗儁僋僥傿僽偐傜偼嬻娫偺嫬奅偑尒偊側偄丅峴堊偵傛偭偰嬻娫偼惗惉偝傟偰偄偔丅 |
| 丂傕偭偲傕丄偙偆偟偨乽幮夛嬻娫乿偺奣擮傪偳偺傛偆偵幚嵺偵梡偄丄偦傟偵傛偭偰壗偑怴偨偵傢偐傞偺偐偲偄偆偙偲偑丄傕偭偲傕廳梫側偙偲偱偁傞偑丄偦傟偼偙傟偐傜偺壽戣偱偁傞丅偙偙偱偼丄偲傝偁偊偢弌敪揰偲偟偰乽幮夛嬻娫乿偺奣擮偵偮偄偰偺妎彂傪帵偟偰偍偒偨偄丅 |
| 丂 |