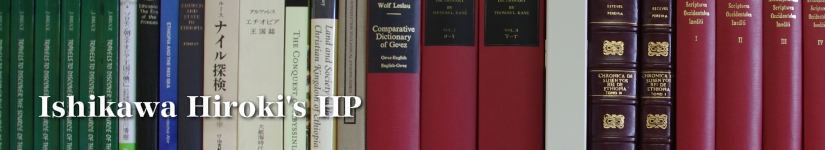葉桜を眺めながら藤沢周平の世界に浸る~短編小説の妙、そしてひとの居場所~
華やかな満開の桜が美しいことは言うまでもないが、私は瑞々しい新緑の葉桜もまた好きである。
その日休日だった私は、買い物の帰りに、4月の初めに妻と花見に訪れた公園を訪れた。すっかり葉桜となった桜の木を眺めながら、私はある短編小説を思い出していた。それは藤沢周平という作家の作品であった。
1927年鶴岡に生まれた藤沢周平は江戸時代を舞台に武士や庶民を描いた時代小説の名手として知られる。藤沢周平の時代小説は大きく3つの種類に分けることができる。1つ目は、江戸に暮らす庶民や下級武士の哀歓を描くもの、2つ目は実在した歴史上の人物を主人公とするもの、そして3つ目が東北地方のある藩の人びとの生き様を描いたものである。
東北地方を舞台とした一連の作品は、登場する藩の名称にちなんで「海坂藩もの」と呼ばれる。『たそがれ清兵衛』『隠し剣 鬼の爪』『蝉しぐれ』『武士の一分』『花のあと』など、映画化されたものも少なくない。いずれかのタイトルを目にしたことがある方は多いのではなかろうか。
小学生の頃から歴史好きであった私は、中学に入ってから歴史に題材をとった小説をよく読むようになった。時代小説の分野では、『鬼平犯科帳』で知られる池波正太郎、瀬戸内海や九州を舞台とする小説を数多く残した白石一郎などの作品を愛読していた。私が藤沢周平作品を読み始めたのはやや遅く、大学生になってからのことであったように思う。父親が『清左衛門残日録』をはじめとする藤沢周平作品を好み、その影響を受けて手に取ったのがきっかけであった。
藤沢周平作品に登場する海坂藩のモデルとなったのは、庄内平野を領有した庄内藩である。庄内藩は、徳川四天王と呼ばれた酒井忠次の孫忠勝を藩祖とし、藤沢周平の生まれ故郷である鶴岡を城下町としていた。意外なことに「海坂藩もの」と総称される作品群のなかで海坂藩という名称が登場する作品は少ない。しかしそれらの作品に記されている藩内の地理や風土、城下町の構造は概ね一致しており、世界観を共有している。
「海坂藩もの」の一つに『山桜』という短編小説がある。鶴岡で山桜が咲くのは、東京などでは桜がすっかり葉桜となる4月の下旬から連休にかけてであるという。名作の多い藤沢周平作品のなかでも、山桜を題名とするこの短編小説に私はとりわけ魅了されている。
『山桜』の主人公は、最初の嫁ぎ先で夫に先立たれて実家に戻され、その後再婚して磯村家に嫁いだ野江という女性である。野江の実家は、家禄百二十石を頂き、父親は郡奉行を勤める藩内では上士に分類される家であった。それに対して家禄六十五石の磯村家は、勘定方に勤めながら金貸しを行い、一家をあげて蓄財に狂奔しているような家であった。必死に磯村家に溶け込もうと努力したもののうまくいかず、自分を「出戻りの嫁」と軽んじている磯村家の者たちが欲しがったのは、自分ではなく実家との縁組ではなかったかと感じながら、野江は鬱々とした日々を過ごしていた。
山桜が咲き始めたある日、野江は若くして亡くなった叔母の墓参りのため郊外の寺を訪れた。そしてその帰り道に、ある山桜の木の下で手塚弥一郎という武士に偶然出会う。手塚は最初の嫁ぎ先から実家に戻った後、野江に持ち込まれた縁談相手の1人であった。手塚が剣の名手であると聞いた野江は、前夫の友人で、粗暴で酒癖の悪い剣術道場の高弟を思い出して尻込みした。その様子を見て野江の両親も強く勧めることはせず、その縁談は流れてしまった。
しかし実際に会ってみると、手塚は粗暴な感じなどまったくない、「男にしてはやさしすぎるほどおだやかな光」を目にたたえた男であった。去り際に「いまは、おしあわせでござろうな」という手塚の問いに、「はい」と答えざるをえない自分をあわれに思う一方で、手塚が自分を気遣ってくれていたことを知って野江は励まされた。そしてそれまでの投げやりな気分をあらため、磯村家の嫁としてやり直すことを心に誓う。
その年の暮、手塚が城内で諏訪平右衛門を殺害するという事件が起こる。諏訪は藩祖と戦場の苦労を共にした名家老の末裔であったが、富農と結んで農民たちを苦しめ、受け取った賄賂で豪奢な生活をしている藩の厄介者であった。帰宅した磯村からこの事件について聞いた野江は、夫が手塚を嘲笑したあげく、自分に対してあらぬ疑いをかけたことに怒る。そしてそれがきっかけとなり、彼女は離縁される。
実家に戻った野江は、家老らが諏訪殺害後大目付のもとに出頭した手塚をすぐに処罰せず、藩主の帰国を待ってその裁断を仰ぐという決定をしたことを父から聞かされる。それを聞いて野江はひとまずほっとしたものの、その後手塚の身を案じながら日々過ごすようになる。そして再び山桜の花が咲くころ、野江は叔母の墓参りに行く。
墓参りを終え、手塚に出会った山桜の木を再び訪れた野江は、その一枝を手に手塚の実家を訪れることを思い立つ。それが「世間のしきたりを越えた、大胆なこと」であることを重々自覚していた野江は、門前払いされることも覚悟していた。
しかし出迎えた手塚の母は、彼女の突然の訪問をとがめることなどしなかった。そして挨拶より先に、野江が抱いている山桜を見て、「おや、きれいな桜ですこと」と眼をほそめた。花から野江に、問いかけるように移した手塚の母の眼はやさしかった。野江が名乗ると、手塚の母は、「いつかあなたが、こうしてこの家を訪ねてみえるのではないかと、心待ちにしておりました」と言い、家にあがるようやさしくすすめた。
履物を脱ぎかけた野江は、不意に玄関の式台に手をかけ、土間にうずくまった。ほとばしるように眼から涙があふれ落ちるのを感じながら、野江は思う。「とり返しのつかない回り道をしたことが、はっきりとわかっていた。ここが私の来る家だったのだ。この家が、そうだったのだ。なぜもっと早く気づかなかったのだろう」……
『山桜』は文庫本で20ページあまりの非常に短い作品である。花曇りのなか野江が叔母の墓参りをする冒頭から、最後の場面に至るまで、おだやかな自然描写を織り交ぜながら、物語は一切のよどみなく淡々と進んでいく。武家社会のしきたりと自分が置かれた逆境のなかで苦しむ野江の心境が、手塚との出会いを経て変化していく様子の描写には、「どうしたらこのように繊細にひとの心のひだを表現することができるのだろうか」と感嘆せずにはいられない。
とりわけ、深く、重い後悔の念から解放された野江が、ようやく自分の居場所を見つけた喜びを感じながら涙を落とす最後の場面は印象深い。野江とは異なる道のりではあったものの、私もだいぶ遠回りをしてから家庭を持ち、これから生きていくうえでの居場所をようやく手に入れた。読むたびにこの最後の場面には心打たれてきたが、結婚して妻と暮らすようになってからあらためて読み返してみると、文章から静かに溢れ出す、野江の深い喜びを実感できるようになった気がする。そしてその喜びの温もりまで描きだした藤沢周平の文才に驚嘆してしまう。
ひとしきり余韻を味わった後、いつも気にかかるのは野江のその後である。「帰国した藩主は手塚弥一郎にどのように処遇するのであろうか」「野江は手塚家に嫁ぎ、幸せに暮らすことができたのだろうか」などととりとめもなく考えてしまう。しかしこの『山桜』という短編小説が珠玉の名作である理由は、あまりにも潔いその終わり方にあると思う。それゆえ内容をふくらませることにより、その潔さを減じてしまった映画版は惜しまれる。
たとえ長編小説といえども、主人公の人生をすべて描き切ることなどできない。字数が限られた短編小説ではなおさらのことである。しかし短編小説は、登場人物の人生の一面を切り取ることにより、読者に奥深く鮮烈な印象を与えることができる。それこそが短編小説の妙であり、『山桜』において藤沢周平はそれを見事に示したように思う。そしてそれは物書きであるならば誰もが憧れることであろう。
ある高名な落語家は、藤沢周平作品を全て読み終えてしまった後のさびしさを考えて、数編読まずに残していたという。物書きであるなら、まず願うのは「自分が書いたものを誰かに読んでもらいたい」ということであり、「全ての作品を読んでみたい」と思われることまで欲張る人はそうそういないのではなかろうか。まして全て読み終えてしまうことをためらわせ、実際に未読の作品をあえて残すような読者を生み出した藤沢周平作品の奥深さにはただただ感服するしかない。
「山桜」を読んでから、私は鶴岡を訪れることを願うようになった。かつての城下町を歩きながら、そして山間にひっそりと咲く山桜を眺めながら、野江をはじめとする海坂藩の人びとの息づかいを感じてみたい。そうすれば、藤沢周平があれほど繊細に人びとの心情を描くことができた理由を少しでも体感できるのではなかろうか。
いつか山桜が咲く頃、妻とともに鶴岡を訪れたいと思う。
2015年4月26日
*『山桜』は藤沢周平の短編11編をおさめた新潮文庫の『時雨みち』に収録されています。

4月下旬に入り、すっかり葉桜となった近所の公園の桜の木。