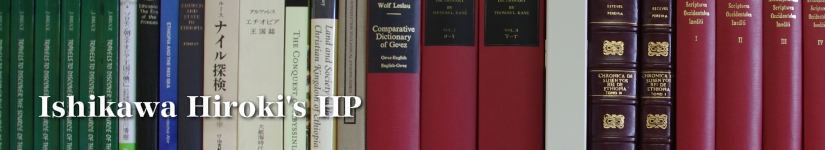非凡なる者、凡庸なる者~仏像を見て、歴史学研究について考える~(奈良、日本)
その日、私は奈良を訪れていた。所用が昼すぎに終わり、東京に戻るにはまだ時間があったため、私は仏像を見に行くことにした。
奈良を訪れるのはそれが3回目であった。修学旅行で訪れたことがあるはずであるが、はるか昔のことであり、ほとんど当時の記憶はない。数年前にある学会の学術大会に参加するため訪れた際には、土曜日の午前中から日曜日の夕方まで大会の会場に缶詰状態であり、外を出歩く余裕などなかった。そのため私にとって奈良は初めて訪れるのも同然の土地であった。
私は興福寺や東大寺といった寺を訪れ、仏像を見て回った。もちろん興福寺阿修羅像の端正な美しさや東大寺大仏殿盧舎那仏の壮大さには感嘆したものの、私が見たかったのは「慶派」と呼ばれる仏師たちによって製作された仏像であった。
慶派に興味を持つようになったきっかけは、高校生の頃に『芸術新潮』の「仏師・西村公朝が語る運慶の革命」という特集を読んだことであった。当時私は実家に毎月届く『芸術新潮』を楽しみにしており、必ず特集に目を通していた。数多くの仏像の修理にあたった高名な仏師である西村公朝氏が慶派について語ったその特集は、私にとって特に印象に残り、心惹かれるものであった。
慶派とは平安時代末期の奈良の仏師康慶に始まる仏師の一派のことである。平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて、慶派の仏師たちはリアリズムにあふれた「鎌倉彫刻」と呼ばれる新しい様式の仏像を創り出した。それは日本美術史上における重大な革新の一つであった。隆々たる筋骨とすさまじい形相で知られる東大寺南大門仁王像は、康慶の子であった運慶と、康慶の弟子であった快慶の共同作であった。
慶派の最大の特徴はリアリズムの追求であり、その姿勢は妥協を許さぬものであった。慶派の仏師たちは、実際に生きているかのような仏像を彫りあげたうえで、時にはそれを大胆に切断し、首や手足の角度を微妙に変えることすら行った。西村氏によれば、それは製作の途上で明らかになった問題点を修正して芸術的効果をあげるとともに、人間とは微妙に異なる動きを取り入れることによって、仏としてのリアルさを表現するためであったという。彼らが創りあげた仏像は、混乱する時代のなかで、仏にすがろうとした同時代の人びとが求めていたものであった。
穏やかな語り口のなかに、本質をつく鋭さを内包した西村氏の解説を通じて、飽くことなくリアリズムを追及しようとした慶派の仏師たちの姿勢に私が感嘆したことは確かである。しかしその特集を読み終えた私が最も心惹かれたのは、運慶亡き後の慶派の運命であった。
生涯リアリズムを追求した運慶が亡くなった後、慶派の仏師たちはそれぞれに試行錯誤を繰り返しながら己のリアリズムを追求した。その中には三十三間堂の神母天像や迦楼羅像のように、楽器の音に耳を澄ますという一瞬の行為を表現することにより、三次元から四次元の世界に足を踏み入れることに成功した名作も生まれた。
しかし仏師たちのなかには、仏像を彫り、その上に別の木材で頭巾をつくって被せた者、さらには衣服を木彫で表現するのではなく、裸の仏像をつくり、そこに衣服を着せてしまう者まで現れた。西村氏の言葉を借りれば、それは「運慶が目指したものとは全く違った方向」のリアリズムであり、「慶派のリアリズムは、ある意味で行き着くところまで行ってしまった」のである。
鎌倉時代に入り、法然、親鸞、日蓮といった僧たちが鎌倉新仏教と呼ばれる新しい形の仏教を広め、人びとはそれを熱烈に受け入れた。「南無阿弥陀仏」という名号や「南無妙法蓮華経」という題目を唱えることによって、人びとは仏像を拝まずとも仏とともにあることができるようになった。そうした時代の流れに慶派の仏師たちは飲み込まれ、そして消えていった。
『芸術新潮』のその特集を読んで以来、運慶が目指したものとは全く違った方向に向かってしまった彼の弟子たちは、私にとって気にかかる存在となった。そして私は、時折思い出しては、彼らについて考えるようになった……
そのようなことを思い出しながら、日が傾くまで仏像めぐりをした私は帰途についた。そして京都に向かう車内で、私は自分が運慶の不肖の弟子たちに心惹かれる理由について考えた。
芸術の世界は、新たな価値観を創造し、後世まで記憶される一握りの非凡なる者と、彼らが見出したものを創意工夫なく継承し、あるいは創意工夫が過ぎて異なる方向に歩みを進めてしまい、忘れ去られていく大勢の凡庸なる者によって構成されている。
一握りの非凡なる者と大勢の凡庸なる者から構成されることは社会も同じである。幸か不幸か、私は非凡な人びとに接する機会に恵まれてきた。人並み外れた才能など持ち合わせておらず、時には度が過ぎて的外れに思われるほどの愚直な方法でしか己を表現できない私は、非凡な人びとと接するたびに我が身の凡庸さを痛切に感じてきた。
そのような私は、リアリズムの追求という師の目標を受け継ぎながら、おそらく愚直に努力を重ねた末に、師が目指したものとは全く違った方向に進んでしまった運慶の弟子たちに自らの姿を重ね、だからこそ彼らに惹かれるのかもしれない。
芸術研究においては、非凡なる者の営為を明らかにすることが何よりも重要であるのかもしれない。しかし社会というものが数多くの凡庸なる者から構成されている以上、彼らの人生の軌跡、そしてそれを取り巻く状況を丁寧にたどり、彼らが生きた社会の在りようを描き出すことは、歴史学研究者の重要な務めではなかろうか……
ふと気づくと、いつのまにか夜のとばりが下りていた。車窓に映るほの暗い田園風景を眺めながら、私は考え続けた。
「慶派の仏師たちはどのような思いで運慶の作品を見上げ、そしてどのようにして己の信じることを実現しようとしたのだろうか」「彼らの思いを、そして彼らが生きた社会を、歴史学研究はどこまで明らかにできるのであろうか」……
2013年7月18日
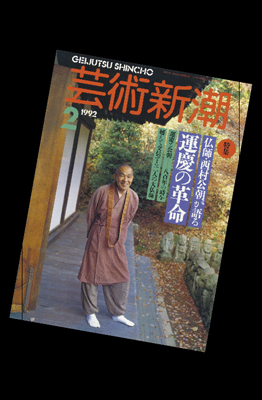
慶派の特集が組まれた『芸術新潮』1992年2月号。毎月届くこの雑誌に目を通したことは、その後の人生において重要な糧になっている。