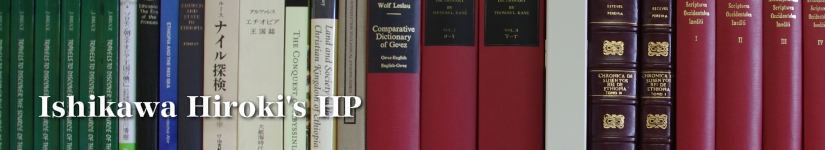研究者として『容疑者Xの献身』に涙する
天才的な洞察力ゆえに「ガリレオ」とあだ名される物理学者の湯川学が難事件を解決していくというガリレオ・シリーズは、東野圭吾の代表作である。福山雅治主演でテレビドラマ化・映画化されることによって、その人気と知名度がさらに高まったことはよく知られている。
『容疑者Xの献身』は、ガリレオ・シリーズ初の長編で、直木賞を受賞した作品でもある。内容は、湯川の大学時代の友人であり、現在は高校教師である石神哲哉という数学の天才が、殺人を犯したアパートの隣室の母娘を救うために完全犯罪を企て、湯川がその謎に挑むというものである。
石神は「ずんぐりした体型で、顔も丸く、大きい。そのくせ目は糸のように細い。頭髪は短くて薄く、そのせいで五十歳近くに見える」という、風采のあがらない人物である。しかし彼は天才湯川が天才と認めるほどの数学の才能の持ち主であった。
石神は大学に残って数学の研究に生涯を捧げるつもりであった。しかし高齢で持病を持つ両親の面倒をみるために、数学者として身を立てる道をあきらめ、高校の数学教師となった。彼は数学の価値を全く理解しようとしない高校生相手に数学の初歩を教えながら、誰にも知られずに数学の研究を続けるという鬱々とした人生を送っていた。
そんな彼が住む部屋の隣に花岡靖子と美里という母娘が引っ越してきた。それからしばらくしたある日、石神は隣室で異変が起こったことに気づく。彼は隣室を訪ね、靖子たちが心ならずも殺人を犯したことをすぐに見抜くと、その隠蔽を申し出た。彼は殺害された靖子の元夫と背格好がよく似たホームレスを殺害し、その死体を元夫のものとして偽装することによって靖子と美里のアリバイを作り、彼女たちを守ろうとする。
殺害日時が1日ずらされたことによって生み出された完璧なアリバイ、そして石神が用意周到に仕掛けた罠にはまって、警察の捜査は行き詰る。しかし依頼を受けて捜査に関わるようになった湯川は、真実を見抜いてしまう。それに気づいた石神は警察に出頭し、妄想に取り憑かれたストーカーに扮して自ら罪を被るという、周到に用意していた最後の手段を使ってまで、靖子たちを守ろうとした。しかしそれを湯川から伝え聞いた靖子は耐え切れずに真相を告白してしまう。それを知った石神は「絶望と混乱の入り混じった悲鳴」をあげ、「魂を吐き出しているように」叫び続けた……
この小説のブックレビューを見ると、「石神の純愛に感動した」といった感想が数多く見受けられる。しかしそれらに交じって「いくら靖子に恋をしていたとしても、石神がそこまでして彼女たちを守ろうとした理由が分からない」という疑問も目につく。
なぜ石神はこれほどまでの「献身」をするに至ったのであろうか?
映画では詳細は省略されてしまったが、小説には石神が靖子たちを守ろうとした理由が次のように描写されている。
その日、石神は死ぬ準備をしていた。「数学しか取り柄のない自分が、その道に進まないのであれば、もはや自分に存在価値はない」との思いからであった。そこに偶然靖子たちが引越しの挨拶に訪れた。石神は彼女たちの目の美しさに「数学の問題が解かれる美しさと本質的には同じ」ものを感じ、生きる喜びを得る。石神にとって彼女たちは「自分が手を出してはいけない崇高なるもの」となった。「彼女たちがいなければ、今の自分もない」のだから、元夫に苦しめられた挙句に窮地に陥った靖子たちを身を挺して救うことは石神にとって当然のことであった。
小説を読み進めてこの場面に至り、石神が靖子たちを救おうとした理由を知ったとき、私は思わず涙した。
数年前、私も研究を続けることを断念せざるをえないところまで追いつめられていた。その一方で、研究のイロハも知らないような人物が、私と同じ地域の歴史研究を専門にしていると称し、ある大学の教授を務めていた。その上その人物は再三にわたる研究者からの厳しい批判に一切耳を貸さず、「どうしてこれほど史実をふまえずに文章を書くことができるのか」と慨嘆されるほど杜撰な内容の書籍を濫造していた。学界で匙を投げられて久しいその人物を、世間の一部は私の研究分野の専門家と見なして持ち上げていた。
目指しているものと現実とのあまりの落差の狭間で、私は「15年近く必死に努力したあげく、なぜこのような仕打ちを受けなければならないのか」と苦しみ、もがいていた。いくら努力しても事態は一向に好転せず、それどころか理不尽としか言いようのない出来事が立て続けに起こった。私にはそれらに耐えるだけの気力は残っていなかった。私はある決意を固め、淡々とそのための準備を始めた。
その時の心境を色で表すならば、それは白でも黒でも灰色でもなく、筒井康隆が『家族八景』の一話で描いたような、ただ「虚無の色」としか言いようのない恐ろしい色であった。正直に打ち明ければ、今でも何かの拍子にその色を突然思い出し、我を失うことがある。
その後いくつかの出来事が重なり、私は「もうしばらく研究を続け、せめて研究者として生きた証を残そう」と考えるようになった。『容疑者Xの献身』が出版され、普段ミステリー小説をほとんど読まない私が書店でたまたま手に取って購入したのは、ちょうどその頃であった。
創作上の人物ではあるものの、自分の存在をかけて取り組んできたものを捨てざるをえない状況に追い込まれ、死を選ぼうとした石神の気持ちが、私にはよく分かった。そしてそれを思いとどまらせ、再び自分が大切にしてきたものに向き合わせてくれた人びとへの感謝の念の深さも……
1990年代に入り、将来少子化によって学生の数が減り、それに伴って大学の教員ポストも減少することは明らかになった。しかし各地の大学では「大学院重点化」という美名のもとに、学部定員を大学院定員に振り替えるという制度改革が推し進められ、大学院生の数が急激に増加していった。それからおよそ20年が経過し、就職先が一向に増加せず、人文系ではむしろ減少するという状況のなかで、博士号を取得しても就職できないオーバードクターが年を追うごとに増加するという、以前から懸念されていた惨状が現実のものになっている。
大学院、特に人文系のそれへの進学が自己責任であることに私も異論はない。またこのような時代であっても易々と就職できるような学識・器量を持つ人物が存在することも確かである。しかし採用する側の浅慮や縁故に大きく作用されて決定がなされるような、理不尽で次元の低い人事が大学で横行していること、また極めて高いレベルの研究を続けてもなかなか就職できない学問分野がある一方で、論文はおろか、まともな文章すらろくに書けないような人物が次々に就職していく分野が多々存在することも確かである。
先日、私は「いつまで研究を続けることができるのだろうか」と悩み、苦しむ日々からようやく解放された。
これまでの道のりがあまりにも長く、苦しく、そして周囲の人びとに迷惑や心配をかけてきたものであったため、様々な思いが脳裏に去来し、なかなか気持ちを整理できない。
しかし1つだけ心の中で確かな思いがある。それは「『容疑者Xの献身』を読んで思わず涙したあの苦しかった日々を忘れず、研究者として生きられることに感謝しながら、これからの人生を歩んでゆこう」という思いである。
2012年11月3日

漆黒に薔薇を配したこの装丁を見るたびに、この薔薇の意味するところについて考える。