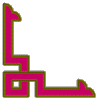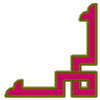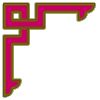
縁は異なもの。再び、出会う
星 泉
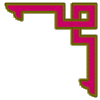
あれは三十年前の春、インドでのできごとであった。私は縁あってチベット語研究者である母のお腹に宿ることになった。 それから十月十日の間、私は日本語とチベット語という二つのリズムに身を浸しつづけ、この世に生を受けることとなった。これはもう観念するしかない。
私の胎教はすでにしてチベット語で行なわれていたのである。運命は運命として受け入れるしかない。なぜチベット語を研究対象として選んだのかと問われると、私はついふざけてこんな説明をしてしまう。私にはそもそも「選んだ」という意識が希薄なのでうまく答えられないのだ。気がついたらすでにチベット語の世界に片足をつっこんでいて、あれっと思っているうちにもう片方の足もそのまま踏み出していた。
私が幼いころから、わが家にはチベットにまつわるものがたくさんあった。うちにチベット人が長いこと住んでいたことも何度かある。私が一歳半くらいのときにはチベット人の女性、ベティさんが一緒に暮らしていた。チベット人のお坊さんが住んでいたこともある。父も母もチベット語 ができるので、チベット人が一緒に住んでいる間はうちではいつもチベット語がとびかっていた。夜寝る前に母が聞かせてくれる「おはなし」もほとんど母が採集したチベットの民話だった。ただ、何分にも小さな子供であったから、日々チベットに接していながら、異文化として受け止めることもなかった。そしてそのうち学校生活に飲み込まれていき、次第にチベットは私の中で存在感を失っていった。
長い空白ののちチベットと再会したのは大学入学後のことである。母の授業でチベット語を習い始めたのである。これは辛い再会だったと言うべきだろう。なまじ幼いころからチベット語に触れる機会が多かったため、簡単に覚えられるだろうとたかを括ってしまったのが苦労の始まりだった。それに加えて母に教わるという精神的なプレッシャーに襲われ、私は逃げ腰になる。万年初級の劣等生とからかわれているうちに、本当に堂々たる劣等生になっていた。
そんな私も、大学三年の春休みに友人と出かけたインド旅行で、ベティさんを訪ねたことをきっかけに風向きが変わる。折しもチベット暦の正月であった。ベティさんは一家の正月の祝の席に招いてくれ、私と友人は正月の前後の一週間、家に泊めてもらうことになった。そのころの一家はたくさんの親戚たちであふれかえっていて、それは賑やかだった。私にとっては大家族の中で過ごすことだけでも新鮮で、単純に楽しかった。子供たちにあんたのチベット語は妙ちきりんだと笑われるのでさえ、愉快でたまらなかった。こうしてその一家の三歳児として迎えられた私は、「田舎のおばあちゃんちに遊びにいく」といっては何度も一家を訪ねるようになる。コドモなので間違えてばかりだったが上達は早かった。もちろんメモを持ち歩いて調査は忘れなかったが、そのせいで「新聞記者に憧れる幼稚園児」にされてしまったこともある。
そんな風にして早六年という歳月が経った。これまでに書いた論文はみなチベット語の文法がテーマだったし、AA研にも、チベット語の研究ということで迎えられた。どうも本当のところはぼおっとしているうちに親にはめられたという気もするが、まあよい。今やあの時の三歳児も青春時代を迎え、文学にうつつをぬかすようにもなった。チベット語の世界は広く、深い。恐ろしさを肌身に感じつつ、今、嬉々として異文化に立ち向かっている。