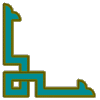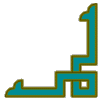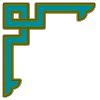
チベット人の名前
文:カンツォ(中央民族大学) 訳:星 泉
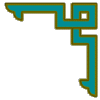
はじめに/個人の名について/家の名について
ラマの名について/おわりに /参考文献
/人名検索
<はじめに>
雪山の高みに暮らすチベット人は、世界の他の民族と同様に、固有の歴史や文化、言語を持っており、また独特の習慣も持っています。チベット人の名前の付け方もまた、チベットの社会や宗教、山や谷などの土地と深い関係があることは言うまでもありません。それでは以下、チベットの人名について概略をお話ししましょう。
人名というと、家の名と個人の名が思い浮かぶと思いますが、我々チベット人には、貴族や大商人などの御大家でもなければ、家の名はありません。家の名については後でお話しするとして、まず個人の名にどのようなものがあるかについてご紹介します。
<個人の名について>
名前の種類と意味/名前の形式/命名改名/同名の場合の工夫
[名前の種類と意味]
個人の名のうち大多数を占めるのは、仏教にゆかりの深い名前です。仏の教えという意味のテンバ、仏の教えを司る者という意味のテンジン、ターラー菩薩という意味のドマ、金剛という意味のドージェ、吉祥という意味のタシ、仏陀という意味のサンゲーなど、数多くのものがあります。
また、仏教と関係のない名前もあります。よくあるのは、生まれた日の曜日を名前(の一部)として名付けるものです。すべての曜日に当たる名前を列挙してみると、日曜日のニマ、月曜日のダワ、火曜日のミンマー、水曜日のラクパ、木曜日のプブ、金曜日のパサン、土曜日のペンバとなります。
さらに仏教色の薄い名前としては、家族の願いが込められた名前があります。例えば、男の子の誕生を待ち望む家庭に女の子ばかり生まれるというときには生まれた女の子に、男の子を連れてくる子、という意味のプティーという名前を付けたりします。また、子供がたくさん生まれて困っている家庭などでは、子作り打ち止めという意味のツァムジューという名前を付けたりします。生まれたときに死にかけた子供には、死んで戻ってきた子という意味のシローという名前をつける習慣もあります。他にも子供が病気でたくさん死んでしまった家などでは、今度こそ悪霊に子供の命がさらわれたりしないようにという願いを込めて、新しく生まれた子に犬の糞という意味のキキャーとか豚の糞という意味のパキャーといった汚い名前をわざわざ付けることもあります。 また男の子は悪霊に命が狙われやすいからといって、男の子に女の名前をつけたりすることもあります。
少し時代をさかのぼって、文化大革命の時代の名前について説明 しておきましょう。文革時代は中国の他の民族と同じように、チベット人の名前も、政治的な意味を込めた名前がたくさん付けられました。チベット語に意訳した名前もありましたし、漢語をそのまま使って名付ける場合もありました。例えば、チベット語に意訳した名前の例としては、革命という意味のサルジェ、紅旗という意味のタルマー、解放という意味のチンドゥーなどがあります。また、漢語をそのまま使った例としては、永紅、紅英、衛東などがあります。文化大革命が終わった後は、普通のチベット名に改名した人たちもいますが、今もなお使い続けている人もいます。
地方によってはこのような習慣もあります。子供が生まれたときに、その家のおじいさんやおばあさんが60歳や70歳、 80歳を迎えたときに、その年齢を名前として付けたりします。例えばおじいさんが60歳のときの子供ならトゥクチュ(六十)、80歳のときの子供ならギャチュ(八十)などのようになります。こうした命名の習慣は漢族の習慣がチベット族の間に広まったものではないでしょうか。特に漢族居住区と接した地域に住んでいるチベット族に多く見られる名前のようです。
さて、チベット人の名前の種類と名前のもつ意味についてざっとお話ししましたので、次にチベット人の名前が普通どういう形をしているかということ、地域による差異、また名前の呼び方などについてご紹介します。
[名前の形式]
一般のチベット人の名前は、4音節の形をしたものが多く、例えば、ドージェ・ツェリン、テンジン・チュター、ツェリン・ドマ、パサン・トゥンドゥーなどのようになっています。チベット人の名前についてよく知らない外国の人は、ドージェ・ツェリンなどというと、ドージェが姓でツェリンが名前か、あるいはその逆かなどと考えるようですが、そうではなく、両方とも名前です。先に説明したように、普通のチベット人には姓はないのです。
普通名前を呼ぶときは、呼びやすいように、テンジン・チュターをテンチューとか、ツェリン・ドマをツェドゥンといったように、第2音節と第4音節を省略して呼んだりします。また、最初の2 音節、または後半の2音節だけで呼ぶ習慣もあります。しかしながら、第1音節と第3音節を省略して呼び名とする習慣はありません。
これ以外にも、2音節だけの名前を付けることもあります。例えば、私の名前はカンツォといいますが、これ以外の名前はありません。よく日本人に「カンが家の名でツォがあなたの名前ですか」と聞かれるのですが、そうではないのです。
アムド地方では、3音節の名前が多く見られます。例えばドゥマ・ ツ、リンチェン・ヒチー、ドゥジ・ジャー、フトゥンドゥ・タルなどです(訳者注:ここのカナ表記はアムド方言をもとにしています)
一般のチベット人は姓を持ちませんが、チベット族居住区と漢族居住区の隣接地域に住むチベット人たちは、漢族の姓を持っていることもあります。その場合、漢族の姓にチベットの名を付けて、例えば王ツェテン、張ダワ、楊ドマといったような名前を持っていることがあります。
[命名]
命名は、両親や祖父母など家族の者がするか、またはラマに命名 を依頼して付けてもらうかのいずれかが多いようです。ラマに名前を付けてもらう場合は、子供が生まれて一ヶ月すると、お寺に初参りに行くのですが、その前後にラマにお願いして命名してもらいます。また、家族が名付ける場合は、特に田舎に多いのですが、子供が生まれた曜日の名前と他の名前を組み合わせて付けたりします。もちろん、曜日の名前を付けないこともあります。
最近はチベット族と漢族が結婚するケースも増えていますが、そうした場合の命名について申しますと、生まれた子供に漢語の名前を付けることもありますし、また漢語の名前とチベット語の名前の両方を付けることもあります。
[改名]
幼い頃の名前が改名されることもあります。私の場合、幼名は幸福という意味のデキーでしたが、後に私の母が、デキーという名前は世間に多すぎるからと言って、私の生まれたチベット西部のガリー地方にある二つの聖地にちなんだ名前を付けてくれました。それがカンツォという今の名前です。カンは聖山カン・リンポチェ(カイラス山)のカン、ツォは聖なる湖マパムユムツォ(マナサロワール湖)のツォなんですよ。
改名が行われるのは多くの場合、お寺に入門したときです。曜日の名前などで呼ばれていた子供も、お寺に入ると仏教にちなんだ法名を新しく付けてもらいます。多くの場合、僧坊長や学堂長などをしているラマが命名するようです。ラマは自分の名前の一部と新たな名前を一つ組み合わせて命名します。
[同名の場合の工夫]
さてまたチベット人の名前には似たようなものが多いこともあって、同じ職場の中でも時々パサンという名前の人が 三人もいたり、またドマという名前の人が四人もいたりすることがあります。そうしたときにはまわりの人々は区別するために、年齢順にター・パサン(大パサン)、トゥン・パサン(中パサン)、シャオ・パサン(小パサン)と呼 んだりします。私の知っている限りでは、この大中小はチベット 語ではなく漢語を使うことが多いようです。
他にも出身地を冠して区別することもあります。例えば チュシュー・パサンだとか、トゥールン・パサンなどと呼び分けます。みんながそのように呼ぶので、自分でも書類を書くときなどにその呼び名を使うこともあります。
同様に、その人の職種から呼び名が付いたり、また身体の特徴から呼び名が付いたりすることもあります。例えばシンソー・パサン(大工のパサン)とか、マチェン・パサン(料理人のパサン)、ゴチェン・パサン(大頭のパサン)などのようになります。
<家の名について>
先ほど家の名を持っているのは貴族や大商人などの御大家であると申しました。貴族はそこでここではまず貴族の家の名について少し説明いたしましょう。
貴族は家の名として、普通、父方の系譜を示す名前か領有地の名前を冠しています。日本の習慣と同じように、呼ぶときには家の名に個人の名を続けます*。例えばカプシュー・チューゲー・ニマという名前の中のカプシューは父方の系譜を示す名前で、チューゲー・ニマは個人の名前です。また、チャバ・ツェテン・プンツォーという名前の中のチャバは領有地の名前で、ツェテン・プンツォーが個人の名前です。
また、本家から分家した場合、分家であることを家の名の中で明示します。本家の名前の一部に部分という意味を表すスーを付けると、それが分家である印です。例えばシャスーという家の名 は、シャタ家からの分家です。ですから、シャタ・ガンデン・ ペンジョーという人とシャスー・ギュミー・ドージェは親戚関係にあることが分かります。
家の名の前にヤプシーとあれば、その家はダライラマか パンチェンラマを輩出した家系であることを示します。例えばヤプシー・プンカンという家は、ダライラマ11世が出た家ですし、ヤプシー・ランドゥンはダライラマ13世を輩出した家です。
婚姻関係を結ぶと、家の名はどうなるのでしょうか。貴族の娘が嫁に行ったら、嫁ぎ先の家の名前を名乗ります。例えばユトー家の娘ツェテン・ドカーがガプー家に嫁ぐと、ガプー・ツェテン・ドカーとなります。また、貴族の息子が婿に行く場合は、婿として行った先の家の名を名乗ります。例えばホルカン家の息子 ガワン・ジンミーがガプー家に婿に行くと、ガプー・ガワン・ジンミーとなります。
また、最近は姓を持たない人が、出身地を姓として名乗ることもあります。特に文章を書く人がペンネームのようにして、出身地の地名に続けて自分の名前を連ねているのを雑誌等でよく見かけます。また、外国に出たチベット人が姓として出身地の地名を使うこともよくあるようです。
<ラマの名について>
チベットのラマたちは、自分の出身の寺やラプラン(ラマの私邸 )の名前、地位の名称などを名字のようにして使う習慣があります。例えばサキャ・ドージェ・ダンドゥーという名前のうち、サキャというのはサキャ寺のことです。ダライラマ・テンジン・ギャツォという名前のうちダライラマというのはかつて清朝の時代に皇帝から授けられた称号です。
<おわりに>
チベット人の名前について簡単にご紹介してきましたが、チベットは広大で、地域によって異なる様々な習慣がありますから、人名についてもまだまだ私の知らないことが多々あると思います。私の知識の及ばない点についてはどうかご容赦ください。
<参考文献>
『蔵族人名研究』王貴著。民族出版社。北京。1991年。
『西蔵風土記』赤列曲札著。西蔵人民出版社。拉薩。1982年初版 。1996年第3版。
<人名検索>
現代のチベットの地名や人名の表記法や読み方を、チベット語、 カナ、漢語(ピンイン)のいずれからも調べることができます。 利用にはJavaが必要です。検索ページはこちらです。